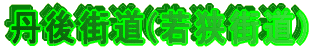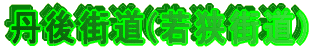◎ 小浜(小浜市)
嶺南の中央、若狭地方の中心に位置した小浜は、北川の中、下流域と南川下流域の沖積地にあり、小浜湾岸のデルタ地帯に形成された平野に市街地ができました。
小浜東部の府中に若狭国府、国分に国分寺跡がありますように、北川中、下流域は、古代以来、一貫して若狭国の中心でした。
中世以降、繁栄の中心は湾岸に移り湊町小浜が栄え、近世初めには京極氏がデルタの低湿地に城下町を開き、酒井氏がこれを引き継いで整備拡充しました。
その経済基盤になったのは、米作、菜種の二毛作を中心とした若狭第一の平野の生産力であり、
また、北川の断層谷から琵琶湖北西岸へ通じる若狭街道(九里半街道)でした。
◎ 小浜湊(小浜市)
小浜湾東岸に臨む中世以降の天然の良港で、北川の断層谷にある熊川宿(上中町熊川)の中継地と若狭街道(九里半街道)を利用して琵琶湖に通じていました。
こうして畿内と日本海側諸地方を結ぶ中継貿易港として栄え、近世初めには敦賀湊と並ぶ日本海岸屈指の港になりました。
ただ、南北朝期以前は北の古津(小浜市甲ヶ崎付近)が湊だったようで、室町初期から湊は、
北川の北方にある西津荘に移ったようです。現在も残っている大湊、小湊は、その遺名でないかといわれます。
西津荘には皇室料税所今富名もあり、若狭守護所も一時、同荘にあったようです。
この頃から船の出入が目立つようになり、入津を管理する政所が問丸に置かれました。
応永15年(1408)南蛮船が着岸して生象や孔雀などを日本国王に進物とし、同19年(1412)にも着岸して、問丸本阿弥を宿所としております。
寛永年間(1624〜1643)頃から小浜湊は賑わしくなり、延宝9年(1681)には米、大豆24万3千俵が入津、
その前年は四十物7万3千箇入津、船数は1,055艘前後ありました。
元禄中期(1688〜1703)まで街道の馬が3,4百疋いて、そのうえ川舟もあったといわれます。
しかし、寛文12年(1672)河村瑞賢の西廻り航路が確立して中継交易の荷を奪われ、湊は衰退しますが、
寛政年間(1788〜1800)から北海道の松前、蝦夷と大坂を結ぶ北前船によって湊の機能を維持しました。
|