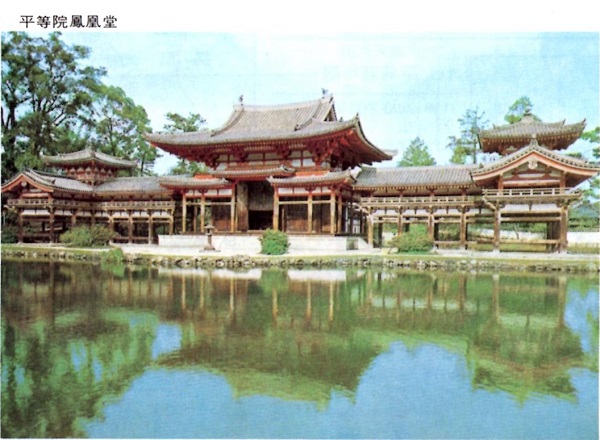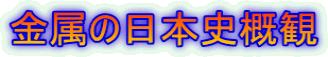
1 平安時代中期(摂関制時代・藤原氏専制) 967(康保4)年~1068(治暦4)年までの約100年間、この時代は天皇の外戚である藤原氏が摂政や関白となり政治を行った。 即ち形式的な律令によらないもので、日本化された形で自然に摂関が出てきたのである。 班田収受の実施は困難となり、国家的事業(国史、鋳銭、外征、使節)の財源がなく、貴族は私有地の荘園を背景に文化を享楽した。 文化は外国依存から国文学中心になるなど、あらゆるものが国風化し、仏教は浄土教が全盛となった。 2 鋳銭中止と流通経済の変化 894(寛平6)年9月、遣唐使の廃止以後も、唐商人、五代商人、続いて宋商人、そして高麗商人が頻繁に来航し、中国商品に対する日本人の欲求は衰えなかった。 日本は受動的ではあったが、11世紀頃から貿易を活発化させていった。 日本商人も統制貿易の間隙を縫って活動していた。事実、日本は大陸商人にとって好市場の一つであり、 最も大量に取引された輸入品は唐物といわれた香料、薬品、染料、絹織物(綾、錦)、美術工芸原料品(竹木類)、鳥獣、銅銭などであった。 この時期の貿易は中継貿易であり、中国商人によって日本から持ち出されたのは、金、水銀、硫黄、真珠、木材、工芸品(蒔絵、屏風、扇、刀剣)などであった。 総体的にみると輸入品には加工品が多く、輸出品には原料品が多かった。
この頃、日本は特殊商人を成長させる地盤が発達しつつあり、彼らは商品を求めて国内各地に市場開拓を始めていた。 これに貨幣流通の問題が関連してくるが、貨幣(銅銭)の鋳造・発行は、律令制の財政基盤の一つとして前時代に引き続き行われていたものの次第に信用を失い、 朝廷は958(天徳2)年に12番目の貨幣、乾元大宝を発行して以後、公式貨幣の鋳造を中止してしまった。 しかし、国内市場経済は発達段階にあり、貨幣の需要が強くなっていった。また、10世紀になると銅銭の破銭を嫌って選ぶ風習が現れ、貨幣の流通を奨励していた。 ところが、中国との貿易が頻繁になると中国銅銭の方が良質であるため、それが流通するようになる。 さらに宋との貿易が盛んになるにつれ、宋銭を輸入して、その流通が全面的に展開されていく。 特に1074(承保元)年、中国(宋)が宋銭の輸出を解禁してから特に激しくなっていった。 3 鉱山の稼行状況 この時期、鉱業に関した記事が少なくなる。朝廷は財源が乏しくなり国家的事業を継続できず、採銅所などもこの頃、中止・閉鎖されたと考えられる。
4 鉄製品の利用と農業技術の発展 11世紀、田堵・名主層が成長するには、生産手段としての耕地や農具を所有することが必須であった。この時期に農業技術が発展し、農具の鍬、鎌といった鉄製農具が普及していった。 ある大名田堵について「兼て水干の年を思い、鋤鍬を調え、暗に腴迫(ゆはく)の地を度(はか)り、馬鍬、唐鋤を繕い」「農業の輩、鋤鍬をもって先とす」(『新猿楽記』)と記している。 馬鍬、唐鋤とあるが、この頃、牛耕、馬耕が始まっており、馬耕より牛耕が一般的だったようである。 こうした農業技術の発展は農業生産力を高め、村落における手工業生産を増大させ、市の発展や田舎わたらい商人の活躍へと波及し、地方の特産物を生み出していった。 『新猿楽記』に各地の手工品や農産品、海産品が次表のように記してある。赤字は金属製品である。
これらの特産品は、多くが自家生産であるが、有力な長者といわれた私営田領主層は、平安京や国衙にあった工房組織を採り入れたのであろう。 また、各種製品の生産発展は、一方で手工業者の独立を可能にし、京都やその周辺で職人の私工房経営者を成長させていった。 5 鍛冶・鋳物師の金属製品 ◆刀工と名刀 940(天慶3)年、平将門の乱を平貞盛が平定したときの褒賞の刀と伝承される「小烏丸」(御物)がある。鑑定によれば鍛造の特徴から平安中期頃の大和鍛冶の作とみられている。 刀工の発祥は「大和伝」が最も古いとされ、続いて「山城伝」、「備前伝」が興ったとみられる。 この三伝法が今日に至るまで刀剣製作の基本的な技法となり、特に大和伝は奈良を中心に各地の寺社領へと広まったため、その影響下にある刀工が多いという。 次に源頼光が大江山の酒呑童子を斬ったとされる「童子切」(伯耆国・安綱作・国宝)やキツネに合鎚を打たせた 伝説のある「小狐丸」(山城国・三条宗近作)などが、この時期を代表する日本刀である。 「童子切」の作者、安綱は出雲・伯耆国境の刀工で、古伝書には9世紀初めの人とされるが、作品を見る限りでは平安中期、10世紀末頃とみるのが刀剣史で通説となっている。 安綱のほか山城(京)の三条小鍛冶宗近、古備前友成などが現存の在銘作のある最古の刀工といわれる。 |