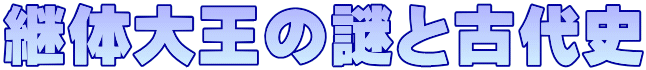 

 |
 |
| 岩戸山古墳(福岡県八女市吉田) |
石人山古墳(福岡県八女郡広川町) |
15 継体大王の治世… 筑紫・磐井の乱
継体大王21年(西紀527年?)、筑紫で磐井の乱が起こった。この乱は、古代史上最大の動乱であり、『日本書紀』は次のように記している。
「二十一年の夏、六月(みなつき)の壬辰(みずのえたつ)の朔(ついたち)甲午(きのえうまのひ)に、近江毛野臣、衆(いくさ)六万を率て、任那に往きて、新羅に破られし南加羅・啄己呑(とくことん)を為復(かえ)し興建(た)てて、任那に合せむとす。
是(ここ)に、筑紫の国造・磐井、陰(ひそか)に叛逆(そむ)くことを謨(はか)りて、猶予(うらもい)して年を経(ふ)。
事の成り難きことを恐りて、恒に間隙(ひま)を伺ふ。新羅、是を知りて、秘に貨賂(まいない)を磐井が所(もと)に行(おく)りて、勧むらく、毛野臣の軍を防遏(た)へよと。
是に磐井、火(ひのくに)・豊(とよのくに)、二つの国に掩(おそ)ひ拠りて、使修職(つかへまつ)らず。」
「二十二年の冬、十一月(しもつき)の甲寅(きのえとら)の朔(ついたち)甲子(きのえねのひ)に、大将軍・物部大連麁鹿火、親(みずか)ら賊(あた)の帥(ひとごのかみ注:首魁)磐井と、筑紫の御井郡(みいのこほり)に交戦(あひたたか)ふ。
旗鼓(はたつつみ)相望み、塵埃(ちり)相接(あひつ)げり。機(はかりこと)を両(ふた)つの陣(いくさ)の間に決(さだ)めて、万死(みをす)つる地(ところ)を避(さ)らず。遂に磐井を斬りて、果して疆場(さかひ)を定む。」
これを訳すと「西紀527年?、大和政権は近江毛野臣に6万の大軍を預け朝鮮へ出兵することになった。
任那の南加羅・啄己呑の地が新羅に合併されたのを回復するためであった。ところが新羅は筑紫君磐井に賄賂を贈り、軍勢の渡海を妨げさせた。
かねてより大和政権に反感を抱いていた磐井は、筑紫・火(肥前・肥後)、豊(豊前・豊後)一帯の北部九州に勢力を張って反旗を翻し、外は海路を塞いで諸外国の船を自領に誘致し、内は近江毛野臣の率いる外征軍を中途に釘付けにした。
大王は大伴金村らに諮り、物部麁鹿火を磐井討伐の将軍に起用、麁鹿火は翌年(西紀528年?)、筑後国御井郡(福岡県久留米市)において決戦の末、磐井を斬り反乱を鎮定した。
磐井の子、葛子は父の罪に連座して殺されることを恐れ、糟屋(かすや)屯倉注1(みやけ)を献上した。次の年(西紀529年?)、外征軍はようやく朝鮮に渡っていくことができた。」と伝えている。
『古事記』には次のように簡記されている。
「この御世、筑紫君石井、天皇の命に従わず、無礼多し。故に、物部荒甲之大連、大伴金村連の二人を遣して、石井を殺しき。」とある。
つまり、この御世に、筑紫石井が天皇の命に従わず、無礼が多くあった。そこで物部荒甲之大連と大伴金村連の二人を遣して、石井を殺したというものである。
この乱の記述には、いくつかの疑問点があり、次にざっと列挙してみた。
(1) 乱の正確な年代が分からない。起きたのは継体大王の治世中で
も、終息したのは次の安閑大王の代ではないのか。
(2) 磐井は新羅の勢力と本当に連携をもったのか。
(3) 近江毛野臣はなぜ自ら率いる六万の兵をもって、磐井を鎮圧しよ
うとしなかったのか。
(4) 近江毛野臣と磐井とは前からの知り合いだったのか。
(5) 磐井は筑紫の国造であったのか。
(6) 磐井征討軍は物部氏だけであったのか、それとも大伴・物部両氏
であったのか。
『日本書紀』は物部麁鹿火一人を将軍として派遣し、『古事記』は麁鹿火と大伴金村の二人を派遣したことになっている。
(7) 磐井の子、葛子は、なぜ糟屋屯倉を献上しただけで死を免れたの
か。
注1:屯倉(みやけ)…大和王権の支配制度の一つ。全国に設置した直轄地を表す語でもあり、後に地方行政組織の先駆けとも考えられる。
まず疑問点(1)は『継体紀』全体に関係する大きな問題である。これについて、ある研究者は『継体紀』の終わり頃の記事を3年切り下げると『百済本記』と筋書きが合うと考える。
磐井の乱の始まりは、継体21年(西紀527年)になっているが、これを3年切り下げると継体24年(西紀530年)となり、南加羅(金官国)滅亡の2年前となり、丁度年代的に合うという。
磐井の乱が終わって、近江毛野が朝鮮に渡るのが西紀531年、そこで新羅の名将、異斯夫との会談を避けている間に南加羅(金官国)は滅亡に追い込まれた。
その直前の継体23年(西紀529年)、高麗王・己能未多干岐(このまたかんき)が来日し、大和政権に援軍を要請している。
これに対し継体大王は一度断るが、後で思い返して援軍を出す。その後、高麗(大加羅)は、かなり長く国を保ったものの、西紀562年に滅亡した。
このように磐井の乱以後の年代は、3年引き下げることによって、ほぼ実際に近くなるのではないかという。
次に疑問点(2)も大きな問題である。この頃、新羅は南加羅を併合できるかどうかという大きな課題を抱えていた。
当然あらゆる手を使い自国の有利を図ったと考えられる。したがって磐井を抱き込むことは、当然有り得たであろうし、磐井にとっても有利なことであったに違いない。
次に疑問点(3)であるが、これは不思議なところである。ただ、ここには年代の錯誤があるのではないかと、ある研究者は推測する。
南加羅の滅亡は西紀532年であり、西紀527年には、まだ滅亡していなかった。したがって毛野の使命は、これから九州で兵士を徴発してから南加羅に向かう予定ではなかったか。
年代として西紀529年か530年頃を考えたいところである。しかし、磐井の乱が発生し、兵士徴発は困難を極めたことであろう。
次に疑問点(4)であるが、磐井は毛野に対して「今こそ使者たれ、昔は吾が伴として肩を摩り肘を触りつつ、共器にして同食いき。安ぞ率爾に使となりて余をして爾が前に自伏わしめん」と揚言し、抵抗に踏み切ったという。
これをみると、毛野と磐井は昔からの友達だったようにみえるが、九州育ちの磐井と近江生まれの毛野が、どうして友達のような仲だったのか。
これに対し、ある研究者は、磐井がまだ若い頃、「靭大伴(ゆげいのおおとも)」として、大王の身辺に奉仕したので、その頃毛野と知り合ったのであろう」と考えている。
次に疑問点(5)であるが、ある研究者は、磐井は国造ではなかった、九州における国造制は7世紀になってからだという。
しかし、他の研究者は国造の設置は地域によって、かなりの差があるから、磐井が国造であった可能性もあると解釈する。
次に疑問点(6)であるが、これについて、ある研究者は戦後における物部氏と大伴氏の関係部民の数を調べ、物部が圧倒的に有利な状況にあることを報告している。
したがって、物部氏が主将として従事したことは疑いないとしながら、大伴金村も補佐的に従事したかも知れぬとしている。
次に疑問点(7)であるが、戦後処理として、磐井の子、葛子は糟屋屯倉を献上して死罪を免れたという。これほどの大乱を起して、どうして簡単に死を免れ得たのか。
磐井の乱は九州の独立戦争だったともいわれるが、敗戦の結果、九州の独立は頓挫したが、意外なことに九州の独立は、なお続いていったようである。
敗戦にも拘らず九州独立王国の観があるのはどういうわけか。一つは、大和政権は屯倉政策で十分であるとの自信があったのではないか。
継体大王は屯倉政策を九州のみならず全国に広げていくつもりだった。
もう一つは、高麗を中心とする北加羅の問題があった。高麗王、己能末多干岐(このまたかんき)は、わざわざ来日して新羅の西進を食い止めるため、援軍の派兵を要請した。
このとき、継体大王は直ぐには承認せず、朝鮮にいる近江毛野に訓令を送るに留めた。しかし、その後考え直した。
それから約30年、高麗(大加羅)問題は、日朝関係の中心となっていく。新羅からきた嫁を送り返してまで、大和に心を寄せてきた高麗王を見放す訳にはいかなかった。
そのためにも九州をある程度自立させ、葛子にも生きて働いて貰わなければならなかった。これが九州が比較的自立を保ち得た理由ではないかという。
16 継体大王の治世…近江毛野臣の朝鮮出兵
『日本書記』には、継体は磐井の乱平定後の西紀529年、6万の兵とともに近江毛野臣を朝鮮半島へ派遣したと伝える。
当時の半島は、南部の加耶諸国侵攻をめぐって百済と新羅が激しく対立していた。
毛野臣は、大和政権と関係の深い鉄の産地で知られる金官国(現金海市)への新羅侵攻を防ぐという使命を帯びていた。
しかし、その活動はことごとく失敗に終わり、西紀532年、金官国は新羅に降伏する。
毛野臣は「傲慢な性格で、政治に熟達せず、融和の心がない」と『日本書紀』に酷評される人物だが、どのような人物であったのか。
ある研究者は、「謎の多い人だが、淀川を遡った琵琶湖南方を拠点とし、継体を支持した有力豪族の一つで、近江国造につながる家柄の人物であった」と考える。
さらに「継体からの勅命は、軍事行動ではなく外交交渉だった可能性が高い」と見る。
「『日本書紀』に6万の兵とあるが、半島では新羅の兵数千人に囲まれて退却している。
それほど大きな兵力を率いていたのではないだろう。百済と新羅を調停する役割を担っていたのではないか」ともいう。
とにかく近江毛野臣は朝鮮半島へ出兵すると、加耶諸国の大国の一つ、金官国の西に位置した安羅国に入った。
しかし百済、新羅の使者と会談することができないばかりか、横暴な振る舞いで現地の反感まで買ってしまう。
ある研究者は「金官国滅亡は毛野臣の外交能力の欠如だけが原因ではない」と指摘し、
「大伴金村が百済の南下を認めたことが、元々の始まりであるが、突き詰めれば継体の責任になる。
しかし、認めなかったとしても、百済の進出を止めることはできなかっただろう」と考える。
外交上の成果が得られないまま毛野臣は半島にとどまり、継体が帰国を促すため使者を送るが、「むなしく帰るのでは面目が立たない。大命を果たしたい」と帰国を拒否する。
結局、百済に安羅侵攻のきっかけまで与えてしまい、西紀530年、ついに召還されるが、帰国の途中、対馬で病死する。亡骸は淀川を遡り近江に運ばれた。
毛野臣の妻は、その時の葬列の様子を「枚方ゆ 笛吹き上る 近江のや 毛野の若子い 笛吹き上る(枚方を通り、笛を吹いて舟が上っていく。近江の毛野の若様が笛を吹いて上っていく)」と歌に詠んでいる。
朝鮮半島南東海岸部に近い加耶諸国の一国、安羅(韓国・慶尚南道の咸安〔ハマン〕郡)の東に位置する加耶国、金官(南加羅、現在の金海市)が新羅に攻められたとき、
安羅国から要請を受けた継体大王は、近江毛野臣を派遣した。しかし新羅の侵攻を止めることができず、最終的には安羅国も西紀550年代に滅亡した。
|
 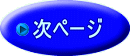 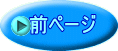
|