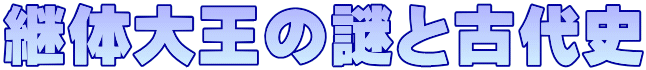 

 |
12 相次ぐ遷都で大和入りに20年要したのはなぜか。
『日本書紀』によれば「五年の冬十月、都を山背の筒城に遷す」とある。さらに十二年春三月、「遷りて弟国に都す」とあり、二十年秋九月、「遷りて磐余玉穂に都す」とある。
とくにこの二十年条には「一本に云わく、七年なりと」との注がついており、この文言は継体紀全体の紀年を考えるうえで重要な問題をはらんでいるので、ここでは立ち入らないで、なぜこのように「遷都」が頻繁に行われたかを考えてみたい。
最初の樟葉宮は、今は楠葉と書き、大阪府枚方市の北端に近い淀川左岸で、船橋川が淀川に合流する附近と考えられる。
次の筒城宮は、今は綴喜と書き、京都府綴喜郡田辺町多々羅の普賢寺谷付近と推定されている。
第三の弟国は、今は乙訓と書き、京都府長岡京市と向日市の境界に近い井ノ内付近と考えられている。
樟葉は、桂川・宇治川・木津川の三河川が集まって淀川となる合流点に近く、水陸交通の要衝である。
崇神朝(第10代崇神大王)の武埴安彦(たけはにやすひこ)注1の乱に際し、最後の戦場となった場所と伝えられ、古来大きな戦場となったのは重要な地点であることを証する。
筒城もまた交通の要衝である。北山城・河内・大和・南近江に通じる道の十字路に位置する。付近には興戸遺跡・薪遺跡(京都府田辺町)など5、6世紀の集落遺跡がある。
郷士塚四号墳(京都府田辺町)からは鉄鉗や鉄槌などの鍛冶道具が出土している。多々羅という地名自体、鉄生産を示唆している。
弟国もまた交通の要路にある。近くの今里遺跡(京都府長岡京市)は弥生前期から古墳時代に至る大集落で、ここの弥生時代の甕の61%が近江系であるという。
またその西の粟生(京都府長岡京市)の光明寺には、越前系の舟形石棺の蓋が残されている。すなわち近江・越前と縁故のある土地柄であったと考えられる。
以上の三宮地と近接した位置にあるのが、継体大王陵としてほぼ確実視される大阪府高槻市の今城塚古墳である。
とくに注目すべきは、今城塚古墳・弟国宮・筒城宮の三地点がほぼ二等辺三角形をなし、その重心に近い位置に樟葉宮が存在するという事実である。
いわば初期継体王権の最重要三角地帯ともいうべき場所であり、その中枢を最初の樟葉宮が占めている。
これは淀川中流域に継体大王の特別な縁故があったことを示すもので、越前・近江以外にも地盤があったとみるほかはない。これは茨田連の線だけで説明がつくであろうか。
さらに細かくみるならば、この「遷都」が樟葉ー筒城ー弟国ー磐余玉穂の順になっていることが注目される。
樟葉から筒城宮への移動は大和へ一歩近づいたことになるが、そこから弟国宮への動きは、再び北へ退いたことになる。
この後退を余儀なくさせたものは何であったろうか。これら三つの宮を遍歴していたころの継体は、果たして天下の主となっていたのであろうか。
中央豪族との妥協が成って、継体が実際に大王位についたのは、樟葉に宮を置いたときか、それとも大和入りを果たした時だったのだろうか。
継体大王を純然たる地方豪族とみる研究者は、大和の豪族達が地方出身の継体大王を正式の王と認めず、大和入りに反対したと考えている。
その反対勢力とは、葛城氏とその同族勢力(蘇我氏、巨勢氏、平群氏など)で、仁徳系の一部の王族を立てて、大和盆地西部に勢力を張っていたという。
一方、別の研究者は大和には継体大王支持勢力の大伴氏、物部氏の本拠があり、全く入ることが出来なかった訳はなく、琵琶湖から淀川流域を勢力圏としていたので入る必要がなかった。
樟葉には河内馬飼首氏や茨田連らが、筒城宮のある山背には息長氏(息長グループ)がおり、弟国にも有力な支持者がいたと考えられるという。
注1:武埴安彦の乱…第8代孝元大王が北河内一帯を大和国に併呑したとき、地元の豪族、河内青玉(かわちのあおたま)の娘、埴安媛(はにやすひめ)を娶り、生まれたのが武埴安彦である。この皇子は河内に住まい独自に兵を養って、やがて河内から山背辺りまで勢力を広げていた。第10代崇神大王のとき、四道将軍を派遣し天下統一に向け動き出した頃、謀反を起こし、主戦場となった樟葉の地で成敗されたという。
|
 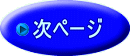 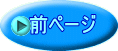
|