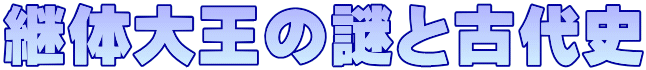 

 |
 |
| 坂井市丸岡町女形谷てんのう堂跡 |
坂井市丸岡町女形谷てんのう堂位置図 |
7 継体大王進出の背景
5世紀末に第21代雄略大王が没すると、第22代清寧大王が即位するが、清寧大王には跡継ぎの皇子がいなかったので、その没後は第17代履中大王の娘・飯豊青皇女(いいとよのあおのひめみこ)が一時天下の政治を執った。
その間に履中の孫にあたる二人の兄弟が播磨から迎えられ、弟の顕宋大王(第23代)、兄の仁賢大王(第24代)の順に大王位に就く。
仁賢大王の没後は子の武烈大王(第25代)が即位するが、武烈にも子がなく、武烈が没すると皇統は断絶の危機に見舞われた。
こうして6世紀初頭、第26代継体大王の即位までの、わずか2,30年の間に4人の大王が立ち、その間、飯豊青皇女の執政という異例の事態もあって、大王位を巡って大和政権のなかで争いや混乱が生じたと考えられる。
そのような中で、越前から応神大王の五世孫と称する皇族ぎりぎりの継体大王が登場した。
大和朝廷の大王として迎えられるということは、その実力が広く万民に認められなければならない。その実力の背景には、次のような要素があったのではないだろうか。
その一つがやはり農業で、中でも米であろう。5世紀末から6世紀初頭になると、鉄製農機具の普及や地方の組織力の強化などで、かなり大きな川の流域にも、灌漑農業が行われるようになったことであろう。
継体大王が登場した時は正しくそうした時代であった。全国的に農業生産は飛躍的に増加したであろうが、特に越前のような大河九頭竜川の流域においては、それが著しかったに違いない。
次に越前若狭は当時有数の製塩国であった。『日本書紀』の武烈大王即位前紀に興味ある説話が伝わるように、大和朝廷が北陸の塩に依存する一時期があったことを示唆している。ある時期、角鹿(敦賀)の塩の価値は相当高かったと思われる。
この「角鹿の海の塩」は、単に敦賀湾の塩だけを意味するのでなく、敦賀湊で集散される越前若狭の塩全体を指していると考えられる。越前から近江にかけて勢力を張る継体の実力は、この塩全体に大きな影響をもたらしたに違いない。
次に鉄と馬の問題がある。福井市天神山七号墳の発掘調査によって、第一主体部から鉄の刀剣11本、第二主体部から約40本の鉄刀剣が出土した。
このように鉄の刀剣が惜しみなく副葬されていることは、鉄の貯蔵にかなり余裕が出来ていたことを示す。越前における鉄生産遺跡は、細呂木遺跡(あわら市・旧金津町)がある。
その年代は未だ定説を得ていないが、5世紀中頃から6世紀中頃までを含んだ遺跡であり、この地の鉄生産は加賀海岸から運ばれた砂鉄に拠っていた。
継体大王の父・彦主人王が西北近江の別業において、鉄鉱石からの採鉄に従事していたとすれば、これは継体大王へ大きく貢献したことになろう。
馬については、考古学的には不透明であるが、継体の中央進出に重要な情報をもたらした河内馬飼首荒籠は、馬の飼育に携わった河内の豪族と考えられる。
荒籠の本拠地は、大阪府の四条畷市から東大阪市と推測され、そのあたりには馬具を出す遺跡が多いと言われる。
早くから馬の飼育を業とする河内の豪族と通交を深めた継体大王は、勢力圏の拡大に相当な野心があったといえる。
さらには三国湊、敦賀湊を窓口とした海外との交流も挙げられる。
こうして越前、近江、美濃、尾張、河内と勢力を拡大させ、継体を中心に姻族で結ばれた地方豪族連合の力は、大和朝廷にとっては侮りがたい勢力になっていたに違いない。
8 継体大王の后妃
継体大王は仁賢大王の皇女・手白髪皇女と婚姻しているが、これは応神大王五世の孫という王統の薄い大王にとって、即位の正当性を得るための手段であったと考えられる。
『古事記』には七人、『日本書紀』には九人の后妃が記されているが、これほど多くの后妃をもった大王は珍しく、その出身地をみると多くの地域に大王の勢力圏ができ、豪族連合の支持基盤が形成されたことが窺える。
| 后妃 |
日本書紀 |
古事記 |
父 |
関連地域 |
備考 |
| 皇后 |
手白香皇女 |
手白髪命 |
仁賢 |
|
子に欽明 |
| 元后 |
目子媛 |
目子郞女 |
尾張連草香 |
尾張国 |
子に安閑、宣化 |
| 妃 |
雅子媛 |
若比売 |
三尾君角折の妹 |
越前国足羽郡 |
|
| 妃 |
広媛 |
黒比売 |
坂田大跨王 |
近江国坂田郡 |
|
| 妃 |
麻積娘子 |
麻組郞女 |
息長真手王 |
近江国坂田郡 |
|
| 妃 |
関媛 |
― |
茨田連小望 |
河内国茨田郡 |
|
| 妃 |
倭媛 |
倭比売 |
三尾君堅楲 |
越前国坂井郡 |
|
| 妃 |
荑媛 |
安倍之波延比売 |
和珥臣河内 |
|
|
| 妃 |
広媛 |
― |
根王 |
|
|
前記9人の妃を分析すると、中央豪族と地方豪族とが、ほぼ半数ずついるのが注目される。
地方豪族としては、尾張を筆頭に、近江系三家、越前系二家があげられ、中央豪族としては、手白香皇女を初め、茨田連、和珥臣が数えられる。
これをみると継体一族の数代にわたる苦心が潜んでいるように思われる。
9 継体大王の支持勢力の基盤
(1) 越前国三国(福井県坂井市)
母振媛の出身地であり、継体の成長に関わる地域でもある。継体の母系に関しては、それが三尾氏の系譜にほかならないこと、継体に妃を出した二つの三尾氏は越前の豪族であることはすでに論じた。
『古事記』が三尾氏と同祖とする羽咋氏は、能登の豪族である。『国造本紀』は加我国造も三尾氏と同祖とする。
継体の母方の祖父乎波智君は、余奴臣の祖、名は阿那爾比弥を娶っており、この余奴臣は江沼臣であろうという通説を支持したい。
すなわち加賀の南半の江沼郡は、継体の祖母の勢力圏であった。このように、継体大王の母系一族は、北陸一帯から近江西北部に勢威を張っていたとみることができよう。
6世紀に入ると越前平野の北東部に数多くの前方後円墳が出現(椀貸山古墳45㍍、甘南備山古墳58㍍)している。
(2) 近江国高島郡三尾(滋賀県高島市)
継体の出生地であり、琵琶湖さらには淀川にかけての水運を基盤に豊かな経済力があった。
琵琶湖の北から山を越えると越前・若狭があり、日本海から直接、朝鮮半島などと貿易をしていた可能性がある。
この地には父の彦主人王の墓という伝承のある「田中王塚古墳」があり、宮内庁が陵墓参考地としている。長さ70㍍ほどの古墳時代中期の帆立貝式古墳である。
また、6世紀前半の前方後円墳と想定される鴨稲荷山古墳もあり、近江高島の勢力が5世紀代から比較的大きな勢力をもっていたと考えられる。
(3) 近江国坂田郡(滋賀県長浜市・米原市)
現在の長浜市あたりに坂田氏が、米原あたりに息長氏が勢力地をもっていたようである。
坂田氏は広媛、息長氏は麻積娘子を継体の妃にしている。坂田氏勢力地の姉川流域に坂田古墳群が築かれ、5世紀後半から首長墓の造営が盛んになる。また、息長氏勢力地の天野川流域には息長古墳群が造られている。
継体大王の父系である息長氏もしくは息長グループの系図をみると、継体大王に妃を入れた坂田大跨王と息長真手王も、おそらく継体大王の近親者であり、湖北の有力者であったであろう。
一方、酒人公については『新撰姓氏録』左京皇別には「坂田酒人真人」と記され、息長真人と同祖とする。
坂田氏・酒人氏は元来別氏であったのが合体して一氏となったのか、それとも酒人氏は坂田氏から分かれ、坂田酒人氏と名乗っていたのを『日本書紀』が前半を落として記載したのかは明らかでない。
いずれにしても息長グループは、継体と婚を結ぶに及んで、皇親としてさらに勢力を伸ばすに至ったと考えられる。
しかし、それ以前から息長氏が無名の氏族だったわけではない。『上宮記』で継体の曽祖父となっている意富富等王の妹、踐坂之大中比弥王は、允恭大王の皇后、忍坂大中姫命と同一人物であろう。
このことは『古事記』の系譜とほとんど一致することからも確かめられる。しかも近江の坂田の出身であったことは、大中姫の妹が、その母とともに近江の坂田にいたとの記述から確実であろう。
息長氏(もしくは坂田氏)は、数代前に皇后を出すほどの名族であったことから、このグループの支持は、継体の声望を大いに高めたに違いない。
(4) 尾張国(愛知県名古屋市)
尾張の大豪族、尾張連草香の娘、目子媛と婚姻関係を結び、生まれた勾大兄と檜隈高田皇子が安閑、宣化として二代続いて大王位に就いている。
尾張勢力が継体大王の擁立に果たした役割は大きかったと考えられる。
古墳時代の前期、中期に大規模な古墳がほとんど見られなかった濃尾平野に、6世紀に入った古墳後期になり、大規模な前方後円墳がいくつも営まれている。
その中でも名古屋市の断夫山古墳(150㍍)は、古墳後期に限れば東日本最大の前方後円墳であり、尾張連草香の墓の可能性が高いといわれる。
(5) 美濃国牟義都(岐阜県武芸町・美濃市・武儀町)
継体の父系で、もう一つ注目すべきは、継体の祖父、乎非王が、牟義都国造偉自牟良の娘を娶った記述である。
牟義都は『和名類聚抄』にいう美濃国武芸郡(岐阜県武芸川町・美濃市・武儀町のあたり)であろう。
近江と美濃は隣国とはいえ、美濃市あたりとは若干隔たっており、むしろ越前と比較的近距離にあることに注意しておきたい。
(6) 淀川流域
淀川流域の継体大王の関連地には、宮を構えた樟葉(枚方市)、筒城(京田辺市)、弟国(長岡京市周辺)がある。
『日本書紀』に継体大王の妃として茨田連小望の女・関媛の記載がある。
茨田氏は現在の守口市、門真市、寝屋川市を勢力地にしていた。継体大王は三島に葬られたが、淀川流域は継体ゆかりの地が集中しており、支持勢力の中枢をなしていたことだろう。
河内馬飼首は、馬の飼育、調習と貴人の従駕などを職掌とした河内の馬飼の伴造氏族だったが、馬匹関係だけにとどまらず、大伴氏や物部氏といった有力軍事氏族と密接な関係があったと考えられる。
河内馬飼首の本貫は現在の四条畷市から東大阪市あたりで、四条畷市の蔀屋北遺跡はこれまでの調査で出土した馬の遺体や馬具などから『日本書紀』に深く関わる集落であることが判明している。
こうした豪族らと縁組を成し得たということは、継体自身の実力がすでに相当世に認められていたことの表われである。
このように、継体大王の父系・母系、並びにその姻戚、また継体の数多い妃の姻族を連ねるならば、
能登・加賀・越前・近江・美濃・尾張・河内と、あたかも畿内を東辺から包むような地方豪族連合の姿が浮かび出てくる。これこそ、継体を大王に押し上げた最大の原動力であったろう。
|
 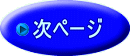 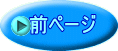
|