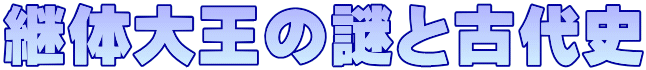 

 |
 |
| 滋賀県高島市水尾神社 |
福井県坂井市大湊神社 |
4 生誕地と出身地
継体大王の生誕地と出身地は、『古事記』には近江の出身とされ、『日本書紀』には近江で生まれ、後に越前で育ったと記されている。
『古事記』を重んじる古代史研究者は、継体大王の生まれ育った所は近江国高島郡三尾であると解し、『日本書紀」の記述は捏造の可能性があるという。
しかし、最近は地名研究など様々なアプローチが行われ、『日本書紀』は「史書として公的に取り組んだもので、
所伝を含めて丁寧に公平に記されている」と、これを重んじる研究者も増えている。
また「『日本書紀』は母方、『古事記』は父方をとらえて書いているだけのこと。どちらも真実に近いのではないか」と解する研究者もいる。
このように研究者によって『古事記』『日本書紀』に対する評価、信頼度に相当な個人差がある。
私は歴史の展開からみて『日本書紀』『上宮記』の記述を史実と捉えた方が自然に理解でき、
『古事記』のたった一行の記述で、出身地まで近江とする考えには賛同できない一人である。
5 出自の謎
継体大王の出自であるが、 『古事記』には次の一文しかない。
「大王既崩、無下可レ知二日続一之王上。故、品太(応神)大王五世之孫、袁本杼命、自二近淡海国一、令二上坐一而、合レ於二手白髪命一、授二奉天下一也。」
つまり「品太(応神)大王の五代目の子孫の男大迹(継体)王を近江国から上京させ、手白香皇女と結婚させて、
天下をお授け申し上げた」という一文だけで、継体大王の出自が「品太(応神)五世孫」としか記されていない。
一方『日本書紀』には、かなり詳しく次のように記されている。
「男大迹大王(更の名は彦太尊)は、誉田大王(応神大王)の五世の孫、彦主人王の子なり。母を振媛と曰す。振媛は活目大王(垂仁大王)の七世の孫なり。
大王の父、振媛が顔容姝妙しくして、甚だ媺色有りということを聞きて、近江国の高嶋郡の別業より、使を遣して、三国の坂中井に聘へて、納れて妃としたまふ。
遂に大王を生む。大王幼年くして、父の王薨せましぬ。振媛廼ち嘆きて曰く、『妾、今遠く桑梓を離れたり。
安ぞ能く膝養ることを得む。余、高向に帰寧ひがてらに大王を奉養らむ』といふ」(『日本書紀 巻第十七』)。
つまり、『日本書紀』には、父母の名や父方が応神大王の五世孫、母方が垂仁大王の後裔であることが記されている。
しかし、応神のあと継体大王の父彦主人王に至る三代の祖先の名が記されておらず、母方も垂仁のあと継体大王の母に至るまでの歴代の名が記されていない。
この空白部分があるため出自に謎が生じ、系譜に対する疑問を生じさせている。
その系譜の疑問部分を埋めてくれたのが『釈日本紀』に引用された『上宮記一云』の所伝である。
『釈日本紀』は、鎌倉時代末に卜部兼方によって書かれた『日本書紀』の注釈書であるが、
この中に現在散逸して残っていない古い書物の断片がいくつも引用されている。
『上宮記』の逸文もその一つで、そこには『古事記』『日本書紀』に記されていない継体大王の詳しい出自系譜が引用されている。それが次の記述である。
「上宮記に曰く。一に云ふ。凡牟都和希(ほむつわけ)王、涇俣那加都比古(くいまたなかつひこ)の女子、名弟比売麻和加(おとひめまわか)を娶りて生める児、
若野毛二俣王(わかぬけふたまたおう)、母々恩己麻和加中比売(ももしきまわかなかつひめ)を娶りて生める児、太郎子(おおいらつこ)、一名意富富等王(おほほどおう)
妹践坂大中比弥王(ほむさかおおなかつひめ)、弟田宮中比売(たみやなかつひめ)、弟布遅波良己等布斯郞女(ふじわらことふしいらつめ)の四人なり。
此意富富等王、中斯知命(なかしち)を娶りて生める児、乎非(おひ)王、牟岐都国造(むぎつこくぞう)、
名伊自牟良君(いじむらのきみ)の女子、名久留比売(くるひめ)命を娶りて生める児、汗斯王。
伊久牟尼利比古(いくむにりひこ)大王の児、伊和都久和希(いわつくわき)の児、伊波智和希(いわちわき)の児、
伊波己里和気(いわこりわき)の児、麻和加介(まわかけ)の児、阿加波智君(あかはちのきみ)の児、乎波智君(おはちのきみ)、
余奴臣(よぬのおみ)の祖、名阿那爾比売(あなにひめ)を娶りて生める児、都奴牟斯君(つぬむし)、妹、布利比弥命(ふりひめ)」。
この「上宮記一云」の所伝が信用できるのか。継体大王の出自「応神五世孫」という系譜は信用できるのかという点で疑問を抱く研究者も存在する。
ここから王族説を否定し、継体大王は王位を簒奪し「新王朝」を開いた地方豪族であるという考えの研究者も出現し、その考えを支持する研究者もいるという。
このように継体大王を考える上で、その出自が最も大きな謎となり、継体は王族だったのか、地方豪族だったのだろうか。
この点について、今も研究者の間で意見が分かれており、王族だったとしても傍系で、当時でも即位の正統性が問題になったであろうといわれる。
|
 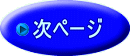 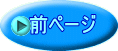
|