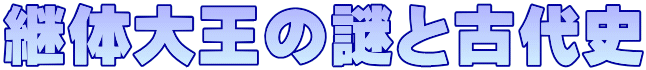 

 |
| 福井市の足羽山頂に立つ継体天皇の石像 |
1 はじめに
福井市の足羽山頂に晩年の継体大王であろう、弓杖(ゆんずえ)を手にした穏やかな風貌の石像が越前平野を見下ろしている。
この石像は、明治16年(1883年)足羽山の石工たちの奉仕によって造られたといわれる。
初めて石像を見た少年時代、大王は越前平野に水を引き入れ、水田を豊かにしてくれたと教えられた記憶がある。
あれから半世紀以上の歳月が流れ、県内各地に大王に関する伝承地があることも知った。しかし、それ以上の知識を深める気は起きなかった。
定年後、郷土史を読み始めた頃、新聞紙上に継体大王即位1500年の特集記事が連載され、改めて大王に対する関心をもつようになった。
以来、余暇を利用し大王関係の記事や書物を読んできたが、いつしか月日だけが過ぎ、理解不十分なまま現在に至っている。
理解したことと言えば、継体大王は謎に満ちた人物であり、古代史には不明な点が多い事であった。
そのため、多くの古代史研究者が謎の間隙を埋めるため諸説を発表し、それらを読むほど複雑さが増すだけである。
そこで大王に関する謎を一つ一つ取り出しながら、自己流に解釈し、知識を整理していくことにした。
従って、次に記すことは古代史研究者の諸説を主観的に理解し、繋ぎ合わせたに過ぎないことを予め断っておきたい。
2 古代の文献史料
日本の古代を記した文献史料の代表は、言うまでもなく『古事記』と『日本書紀』である。
『古事記』は奈良時代の歴史書で三巻あり、天武天皇の勅命で稗田阿礼(ひえだのあれ)が誦習(しょうしゅう)した
帝紀や先代旧辞を、元明天皇の命により太安万侶(おおのやすまろ)が文章に記録したものである。
和銅5年(西暦712年)に献進された日本最古の歴史書であるが、天皇による支配を正当化しようとしたもので、
上巻は神代、中巻は神武天皇から応神天皇まで、下巻は仁徳天皇から推古天皇までの記事を収めてあり、神話、伝説、歌謡なども含まれている。
一方、『日本書紀』も『古事記』同様、奈良時代最初の勅撰正史の歴史書であり、六国史の第一に挙げられ、30巻からなっている。舎人親王らの編により、養老4年(西紀720年)に成立した。
資料として帝紀、旧辞のほか寺院の縁起、諸家の記録、中国、朝鮮の史料などを広く用い、神代から持統天皇までを漢文の編年体で記したものである。
継体大王を中心とした古代史は、これら古代文献史料を基に、考古学、地学、その他の古代史料を参考にして古代史研究者が諸説を発表している。
3 天皇と大王の表記
「継体」という呼び方は、奈良時代にできた、死後に贈る中国風の称号で[諡(おくりな)]である。
『日本書記』では継体のことをを男大迹、『古事記』では袁本杼、これより古いとされる『上宮記』では乎富等と表記され、「おおと(ど)」と発音していたと考えられている。
6世紀前半には、まだ天皇という言葉は使われておらず、大王が用いられていた。だから当時の表現によると「男大迹大王」などとなる。
しかし現代では、「天皇」号が成立してからの呼び方で「継体天皇」とするか、大王だけ当時の言い方を尊重して「継体大王」とするのが一般的である。
ここでは古代史に想いを馳せる意味から「天皇」を「大王」と記し、「継体大王」と表現して記していくことにする。
|
 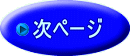
|