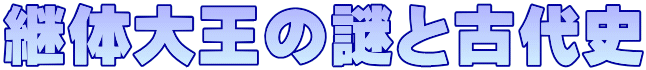 

 |
 |
| 今城塚古墳 |
今城塚古墳公園埴輪祭祀場 |
20 古墳からみた継体王権
(1) 継体大王陵と手白香皇后陵
継体大王陵は『延喜式』諸陵寮によれば、摂津国嶋上郡三嶋野に所在していたことになっている。
現在、宮内庁によって管理されている継体大王陵は太田茶臼山古墳(大阪府茨木市、前方後円墳、226㍍)であるが、これは嶋下郡に属し、墳丘形態や埴輪などから5世紀中頃に比定されている。
一方、嶋上郡に所在する6世紀前半の二重周溝をもつ大規模な前方後円墳には今城塚古墳があり、これが継体大王陵であると古くから指摘されている。
そうすると、継体大王は三嶋野と有縁の人物となる。三嶋野には、古墳時代前期の弁天山B一号墳(大阪府高槻市、前方後円墳、墳丘長100㍍)や
中期の太田茶臼山古墳をへて、後期の今城塚古墳へと連綿と続く三嶋野古墳群があり、継体大王はこの系譜に連なる人物と考えるのが自然であろう。
継体大王の父・彦主人王は「近江国高島郡三尾の別業」(『日本書紀』)、「弥乎国高島宮」(『上宮記』)にいたとあるが、その本貫地については記載がない。
しかし、継体大王と深いかかわりのある三嶋野をその本貫地とすれば合理的に理解することができる。三嶋野は継体大王の有縁の土地であったのではないだろうか。
ただ現実に、三嶋野(大阪府高槻市)に何故継体の墓があるのかという問題を的確に説明することは難しい。
継体の住居でもない、生まれ故郷でもないところに、何故墓を造ったのだろうか。
そこには未だに知られていない何らかの理由があるのではないか。さらに現在継体陵となっている太田茶臼山古墳は、一体誰の墓なのか。
今のところ、説得力のある説は出されていない。一番有力なのは、継体の曽祖父の意富富等(オオホト)王であるが、意富富等王と、この地との関連を説明することができない。
一方、手白香皇后陵(衾田墓)は、『延喜式』諸陵寮によると、大和国山辺郡にあり、城上郡にあった崇神大王陵(山辺道勾岡上陵)の陵戸に兼ね守らしめたことになっている。
崇神大王陵は柳本古墳群(奈良県天理市)に所在した可能性が強く、それに北接する山辺郡内における6世紀前半代の比較的大規模な前方後円墳は、
大和古墳群(奈良県桜井市・天理市)の西山塚古墳が衾田墓である蓋然性が極めて大きい。
しかも、新池埴輪窯跡(大阪府高槻市)で焼成された埴輪が、太田茶臼山古墳や今城塚古墳はもとより
西山塚古墳にまで搬入されていることは、そのことを一層裏付けているようである。
継体大王に始まる王権は、すでに応神大王の正統な系譜ではなく、その后の手白香皇后を通じて
大和の王統につながるといわれ、継体大王は入り婿の形で王統の継続性を主張したと考えられている。
それゆえ継体大王陵は、その前の応神王朝の墳墓の地である古市(大阪府羽曳野市)・百舌鳥(同堺市)の両古墳群を離れた継体大王有縁の地、三嶋野に営まれたのであろう。
また、応神王朝につながる手白香皇后陵をその父、仁賢大王陵の所在する古市古墳群中に営まず、
初期大和政権の大王墓の営まれた大和古墳群中に営んだところに、継体王権の旧王統を引き継いだという自負と真意が汲み取れる。
これ以後の大王墓については、今城塚古墳と同じ剣菱形前方後円墳であり、古市古墳群の西方の高鷲の地に営まれた安閑大王陵に比定される
河内大塚古墳(大阪府豊中市、330㍍)や、奈良盆地南部の身狭の地に営まれた欽明大王陵に比定される見瀬丸山古墳(奈良県橿原市、310㍍)などがあげられる。
これら二つの古墳は、その始祖である今城塚古墳の近くに営まれることもなく、また旧来の有力な古墳のなかに含まれるわけでもない。
その巨大さにより、大王権力が従来に増して隔絶したことが理解されるが、その地理的・氏族的基盤を離れていることが注目される。
この段階の大王墓は、連合政権としての大和政権の盟主の地位を示すものから、諸豪族から完全に超越した権威として確立したものに変質したものと理解される。
また、それは単なる同盟の盟主として従来のようにその構成員が交替しうる性格のものでなくなっていることを示すもので、
その権力を支える勢力の動向とも関連して、転々と陵墓は移動するようになったと考えられている。
|
 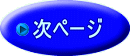 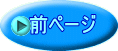
|