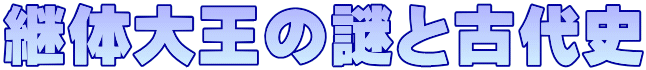 

 |
 |
| 安閑大王陵 |
宣化大王陵 |
21 安閑・宣化・欽明の治世
大王位を継いだと伝えられる継体の3人の皇子たちは、どのような生涯を送ったのであろうか。
(1) 安閑大王の治世
継体大王から譲位を受けた安閑大王は、『百済本記』の記事に従えば、1日しか生きられなかったことになる。
しかし、『日本書紀』の安閑大王は在位2年で短いものの、その後も平然と生き続けている。
殊に安閑2年5月には、筑紫の穂波屯倉をはじめ、26ヵ所の屯倉設置が記録されている。
これについてある研究者は「安閑は継体の長子であり、即位時は69歳であった。
この治世わずか2年間に約40ヵ所にも及ぶ屯倉が国内各地に設置されたとするのは、不自然である。
安閑は、大王即位以前から、大和政権の政治に重大な発言力があった…。安閑紀に載せられた多数の屯倉設置記事は、
安閑が継体即位当初から行ってきた内政の成果を『日本書紀』の編者が一括して『大王』段階の治績とした結果によるものであろう」と記している。
これによると安閑大王は、継体治世の20数年間、一貫して屯倉設置に努力し、その成果を一括して安閑2年に発表したことになる。
これに反し別の安閑像として、継体没後、再起の気力もなくなり、幽閉同様の悲惨な生活の末、亡くなったと記す研究者もいる。
しかし、安閑大王は安閑元年12月には、武蔵国造家の争いに干渉して、笠原直小杵(かさはらのあたいおき)を殺している。
あたかも大王家の新しい勢威を示すかのようで、この頃、安閑大王の気力はまだ十分充実しているように見える。だが安閑2年12月、後継者がないまま崩御した。
(2) 宣化大王の治世
安閑大王の跡を継いだ同母の弟・宣化大王は、在位4年であるが、どうも影が薄い。
3人の皇女は、欽明大王の后妃となり、子孫を残した。治世の記事はほとんどない。ただ、蘇我稲目を初めて大臣としたのが注目される。
|
 |
 |
| 欽明天皇磯城嶋金刺宮址 |
欽明大王陵遠景 |
(3)「欽明即位前紀」の狼説話
「欽明即位前紀」に狼の説話記事がある。この説話に歴史の真実が隠されていないだろうか。
2匹の狼が血塗れになって、相争っている姿こそ、欽明対安閑・宣化の一色触発の状況を語っているのではないか。
秦大津父(はたのおおつち)が狼を引き分けて、血まみれの毛を拭い洗って放してやった時、
「お陰で助かりました」と狼が感謝したというのも、時の氏神を待ち望む第三者の存在を暗示しているかのようだ。
欽明の治世41年という「上宮聖徳法王帝説」の記事や、仏教伝来を欽明7年戌午の年(西紀538年)とする
「元興寺縁起」の説を、動かすことができないとすれば、二朝並立を認めざるを得ないだろう。
そうした対立は、宣化の融和的態度によって、次第に解消に向い、8年後には両朝合一に至ったと考えられる。
(4) 欽明大王の治世
欽明朝は大王制の第一次開花期である。継体大王が重んじた会議尊重の精神は、改変されることなく継承された。
蘇我氏の主導によって、吉備の国に白猪・児嶋の屯倉を設置し、屯倉制度も順調に発展しつつあった。
西紀538年に百済の聖王が仏教を伝えてきた。しかし、それ以前、継体大王の治世16年に、梁の人・司馬達等が渡来し、仏教を伝えていたことを説く人は少ない。
司馬達等は、後年飛鳥寺の大仏を造った鳥(止利)仏師の祖父に当たる人である。
この時代、朝鮮問題は益々混迷化し、西紀562年に大加羅国(高霊)も遂に滅ぼされるに至った。
西紀570年、高句麗国が初めて国使を遣わして、加賀海岸に到着した。これが高句麗と初めて国交が開けた年であると言われる。
欽明朝は、継体大王が築いた大王制の礎を順調に継承し、発展させた時代と言えよう。
22 おわりに
古代の伝承・説話と史実とは区別しなければならないが、継体大王を育んだ歴史と地域を見つめ直したい思いがあった。
『日本書紀』によると、近江の彦主人王と越前の振媛が結婚し、近江で生まれた。
彦主人王が若くして亡くなったため、振媛は越前の高向(現在の坂井市)に戻って子育てする。
その後、継体がどのように過ごしたかは不明であるが、武烈大王が亡くなって後継者がなく、西紀507年に大和政権から迎えられ、樟葉宮(大阪府枚方市)で即位した。
継体は応神大王五世の孫と書かれているが、その間の詳しい系図は省略され、皇統かどうかを疑う人もいる。
即位後、三つの宮を移り、西紀531年に大和の磐余玉穂宮で崩御した。その間、朝鮮半島における任那四国割譲など外交上の大きな出来事があり、九州の豪族磐井との戦争もあった。
まさに激動の生涯を送った大王であった。その後安閑、宣化、欽明と3人の子が大王位を継承し、今の皇室へと続いている。
『日本書紀』の崩年は83歳と書かれている。そこから逆算すると即位が58歳、生まれたのは西暦450年ごろと推測される。
継体という名は後でつけられた諡(おくりな)であり、元は男大迹(おほど)王と呼ばれた。
一方、『古事記』には、即位にあたって近江から招いたと書かれてあるだけで、越前のことは出てこない。崩年も43歳と『日本書紀』と大きく異なっている。
古代文献史料には、不明な点が多く史実を正確に把握することは至難の業である。
|
 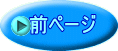
|