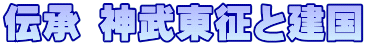 

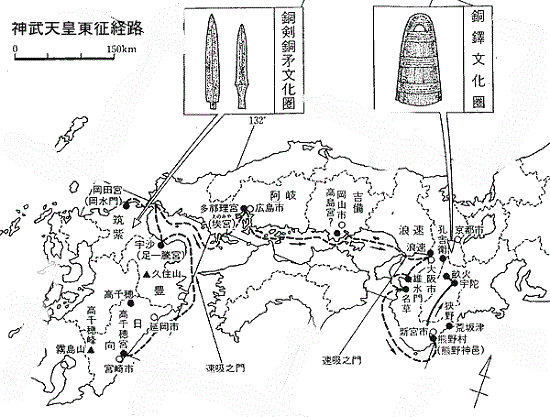 |
| 神武東征の経路図 |
25 菟田(宇陀)地方の征討
平定すべき地元勢の第一にあげられたのが、兄猾(えうかし)と弟猾(おとうかし)の兄弟を首領とする
菟田地方(奈良県宇陀市)の部族であった。~われらの軍門に降れ~と降伏を勧告した。
やってきたのは、弟猾だけだった。兄猾は戦いを挑むべく兵をあつめ、謀りごとをめぐらしている。先に帰順した弟猾は、抗戦派の動きをこのように伝えた。
その情報を確認すると、日臣あらため道臣は、部隊を率いて兄猾の本拠地へ急行した。
東征軍の兵たちが兄猾の屋敷を包囲し、弓矢を構えているところへ兄猾が出てきた。道臣が抜刀して飛び込んでいった。
さすが大王家譜代の軍団、大伴氏の祖である。この頃からすでに猛々しい武人の血が流れていたようである。
26 吉野全域を平定
ヤマト平野の南東にあたる菟田(宇陀)地方を平定したあと、狭野尊はみずから兵を率いて、菟田の西側に広がる吉野への巡行に出た。
吉野川の川沿いや台地に小部隊が散らばっていて、それらを帰順させるためである。
『日本書記』によれば、このとき奇妙な部族が行く手に現れる。まず井光(いひか)と自称する者で、井戸から出てきた光る体には尾があったという。
平安時代の史料「新撰姓氏録」では、狭野尊(神武天皇)の従者が水を汲みに行くと、光る井戸に女性がいて
「天から降りてきた神の女」であると名乗ったので、狭野尊は水光姫(みひかひめ)と名付けたという話になっている。
吉野の国樔(くず)と呼ばれる人たちも、このときに東征軍に服属した部族である。
ほかに、吉野川で梁を仕掛けて魚をとっていた小部族なども、狭野尊が兵を率いてやってくると、次々に服属した。
その結果、菟田から吉野のほぼ全域が東征軍の翼下に収まることになる。熊野、菟田、吉野は
東征軍にとって、九州を出て初めて得ることができた、いわば領地であり、勢力圏である。
28 邪馬台国側からの視点
これをヤマトの地元勢から見ればどうであろうか。時代は女王卑弥呼が登場する前である。
北九州の奴国、伊都国と並んで、ヤマト平野の北から山背(京都府)にかけてヤマトを代表する雄国が勢力を伸ばしていた。
後に中国側の文献に邪馬台国名で現れる地元勢の王国である。
この地元勢からみるなら、九州から船を列ねて乗り込んできた軍団が、一旦姿を消したかと思うと、
突如として熊野に現れ、奈良盆地の南の山間部に一つの国を作り上げてしまったことになる。
この国を邪馬台国では、熊野国と呼んだ。彼らは南九州の日向から攻め上ってきたと称しており、そのため最高指導者を日向彦と呼ぶようになる。
邪馬台国からの情報によって中国側では、この熊野国の発音を約(つづ)め、あえて侮蔑的な漢字を選んで狗奴国と表し、
日向彦を卑弥弓呼(ひみくこ)としたのではないかというのが、ここで展開している大筋の推論である。
魏志倭人伝の記述によれば~その南に狗奴国あり、男子を王となす。女王に属せず~とある。
28 狭野尊、高倉山から四方を見渡す
狭野尊(神武天皇)が熊野から菟田(宇陀)、吉野を平定して、ヤマトの攻略にかかろうとしていたときである。狭野尊は高倉山(奈良県宇陀市)に登り頂上に立った。
高倉山は標高440㍍ほどしかないが、今の桜井市の南部から飛鳥方面へかけての山々と地形が、それこそ手に取るように見渡せた。
この山々が実は東征軍のヤマト入りを阻んでいる最後の壁であり、国見丘(くにみのおか)辺りに敵勢の本陣があり、
八十梟帥(やそたける)が立て籠もっていた。そのほか南の女坂と正面の男坂にも敵は兵を配し、さらに北方の墨坂をも守っているようであった。
女坂、男坂ともに、菟田からヤマト平野に抜けることができる重要地点であり、墨坂は伊勢からヤマトへ入る要衝の地であった。敵はヤマト入りのすべての要路をすべて押えていた。
磐余(いわれ)の地には最大の敵である兄磯城(えしき)の率いる敵兵が満ち満ちていた。
磐余とは、神日本磐余彦という神武天皇の称号のもとになった由来の地名である。
ヤマト平野のこの地を攻略したからこその称号であり、この時点ではまだ磐余彦(いわれひこ)とは呼ばれていなかった。
『日本書記』には~賊の拠るところは、皆これ要害の地にして、道絶え塞がり通れるところなし~と記されている。
|
 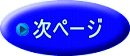 
|