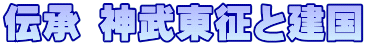 

 |
| 神武東征の経路図 |
18 河内の草香(くさか)
後に河内湖とも呼ばれるようになる内海に入ると、東征軍は沿岸に上陸地点を探り、河内の草香(東大阪市日下町)を選んで、一斉に上陸した。
沿岸の先住民らは恐れをなして、生駒の山上へ逃げていく。全軍の将、日臣は「あの山を越えねばならぬ」と云った。
東征軍の目的地、ヤマトはこの山々の向こうに広がっている。海上からきた彼らには、進攻を阻む生駒山系はため息が出るほど高く見えた。
兵に食糧を持たせ、山腹をよじ登るように行軍を始めた。~その路、狭く嶮しくして並び行くことを得ず~と『日本書紀』は記している。
この時期はまだヤマト(奈良盆地)がどういう状態にあるのか、正確な情報を東征軍は掴んでいなかったと思われる。
生駒山系を越えたところはヤマト平野の北側を占める敵勢力の本拠地であった。
19 孔舎衛坂(くさえのさか)
兵力において劣勢にあった東征軍は、山を越えれば、最悪の条件で本拠地の敵と戦わねばならなかった。平地で包囲されていたら、全滅していたに違いない。
しかし、山頂に至るまでに、このルートでの行軍は無理と判断した東征軍は、あっさり山裾まで引き返した。
そして別の道を探し出し、改めて孔舎衛坂(くさえのさか)と呼ばれる急坂を登って行った。
その頃すでにヤマト側の地元勢力は、日向からの軍団が河内に上陸し、ヤマトを征服しようとしていることを知り、全軍あげて迎え撃つ態勢を整えていた。
両軍が初めて遭遇したのは、孔舎衛坂を登ったところである。数において勝る地元勢は、たちまちのうちに東征軍を圧倒し、河内側に押し返していく。
武器は、まだ石の鏃が銅、鉄に混じって使われている時代であり、大した威力はなかった。
しかし、雨あられと矢が降り注ぐ物量の前に東征軍の強兵たちも、たじろがざるを得なかった。
この戦闘で、狭野尊の長兄、彦五瀬命が敵の矢を受けて倒れた。矢は肘の部分を抉って突き刺さっていた。
東征軍の最高幹部であり、将兵の尊敬を集めている彦五瀬命が重傷を負い、戦列を離れるのは味方にとって大きな痛手であった。
狭野尊は、ここで撤退を決意する。『日本書紀』によれば、このとき狭野尊は将たちを集め、
「われら日の神の子孫が、日に向かって敵を討つは、天道に背く行為である。ここは一旦退き、背に日の神の威光を負って戦おうではないか」と告げたという。
日臣、大久米ら幹部は皆そろって「仰せのとおりに」と奏上した。狭野尊は改めて、将兵に退却命令を出す。
東征軍、初めての事実上の敗退であった。部隊は草香の宿営地まで退き、ここで態勢を立て直そうとするが、矢を肘脛に受けた彦五瀬命の傷は重くなるばかりであった。
20 孔舎衛坂(くさえのさか)の敗退と作戦変更
草香において全軍が大声で敵を威嚇する雄叫びを上げ、闘志を取り戻したところで、初めて熊野への迂回作戦が打ち出された。
紀伊半島を回り、南東方面からヤマトへ突入を図ろうという大作戦であった。
この大作戦の真の理由は別のところにあった。生駒越えでヤマト平野に入ろうとして、東征軍はヤマトに強力な敵勢力の存在を初めて知ったのである。
作戦の基本となる情報さえ、彼らは事前に掴んでいなかった。
~東のかたに美き地あり、青山、四方をめぐる~ということで、建国するために乗り込んできたのだったが、
そのヤマト平野には当然ながら多くの民が住み、兵を備えた国が存在したのである。
草香へ退いて後、集めた情報によれば、ヤマトを守っているのが鳥見長髄彦(とみのながすねひこ)という者で、孔舎衛坂での戦いで指揮をとっていたのが、この男だという。
さらに長髄彦を従えているのが、総大将とでもいうべき饒速日(にぎはやひ)であった。もとは外来勢力であるらしい。
この饒速日の背後に、ヤマトから北方へ大きく領土を広げている国が存在しているということだった。
これに対し、ヤマト平野の南側はといえば、群小部族が割拠しており、北の先進地域の力がまだ及んでいなかった。
そこで、南側の部族を一つ一つ個別に撃破するなら、ヤマト平野の南部をとりあえず平定できるという展望が開けてくる。
狭野尊が熊野迂回作戦を決断したのには、そうした戦略上の判断があった。
|
 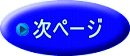 
|