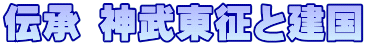 

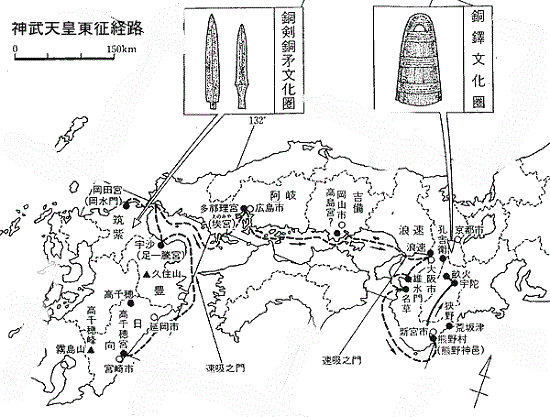 |
| 神武東征の経路図 |
9 神武東征の出発地・日向
伝承にある神武東征の出発地には、主に南九州説と北九州説の二説がある。南九州説によれば日向の高千穂を文字通り日向の国(宮崎県)とする。
舟軍で出発したのは現高千穂峰ではなく、美々津という場所であった。北九州説によれば、日向国ではなく日向と記載され、日向国の地名由来は狭野尊即位以前には存在しなかった。
日向はヒュウガではなくヒムカと読み、東向き、南向きの意あるいは美称である。また高千穂は高い山の意であり、その証拠に複数存在する。
『古事記』では天孫降臨で日向の高千穂を「韓国に向い笠沙の岬の反対側」としている。
従って天孫降臨の地が北九州の日向であれば、神武東征における日向も特段の事情がない限り
北九州の同じ土地であるというのである。ここでは南九州説で話を進めていきたい。
伝承によれば、狭野尊は高千穂の宮を出てから宮崎県児湯郡農町川北にある都農(つの)神社に寄ったとされる。
都農神社は『延喜式』に載っている小社で、祭神は大己貴(おおなむち)の神である。
さらに、狭野尊は美々津(古名は美弥、耳津とも書く)に寄港し、ここから東征の船出をしたといわれる。美々津は西方は山、東方は日向灘を望み、耳川が海に注ぐ。
美々津には立磐神社があり、狭野尊を祀る。この神社に狭野尊が順風を待つ間、少し休憩したという腰掛石があり「神武天皇進発の碑」が建っている。
なお、美々津港の入口にある黒島と八重島の間からは、古来船出をしない習慣がある。
これは狭野尊の東征軍が、この間から出航して、二度と戻らなかったので、それを忌むためといわれる。
10 宇佐(宇沙)を服属
日向を発ち、四国と九州の間の豊後水道を北上した東征軍に対し、最初に服属したのは宇佐の部族であった。
今の大分県の駅館川(やつかんがわ)を遡ったところ、有名な宇佐神宮のあるあたりだが、この地に菟狭津彦(うさつひこ)、菟狭津媛(うさつひめ)の一族がいた。
東征軍が国東(くにさき)半島をまわって宇佐に至ると、菟狭津彦らは軍船を見て恐れをなし、抵抗することなく恭順の意を表明したという。
古い土着の勢力であるが、彼らは宇佐の中津平野を占めていたにすぎない。
宇佐の国造の祖の菟狭津彦(宇佐都比古)と菟狭津媛(宇佐都比売)は宇佐の川上に足一騰(あしひとつあがり)の宮を作ってもてなしたという。
菟狭津彦は、東征軍に一族の菟狭津媛を差し出した。狭野尊は、この申し出をうけ、侍臣、天種子(あまのたねこ)の妻として菟狭津媛を賜った。
このように『日本書紀』に記してある。天種子とは、後の中臣氏の祖先である。
『先代旧事本紀』によれば、
神武天皇の時代に高御産巣日尊(たかみむすびのみこと)の孫の菟狭津彦(宇沙都比古)を国造(くにのみやつこ)に定めたと記してある。
11 岡水門(おかのみなと)に寄港
この後、東征軍は一旦関門海峡を出て、今の福岡県東部の遠賀(おんが)川の河口付近、岡水門(おかのみなと)に寄港する。
何のためにここまで来たのか、『古事記』『日本書紀』ともに触れていないが、先進地の奴国、伊都国に向かおうとして思い止まったのではないかとみられる。
奴国は、かつて倭の国々を代表する存在であった。西紀57年、後漢の光武帝から金印を贈られている。
その後、伊都国が急速に力をつけ、西紀107年に後漢に大使節団を派遣した倭国王、帥升は伊都国の王だったとみられている。
こうした先進国は当然、防衛のための武力を備えており、ときに海を渡って半島にまで攻め込んでもいた。
朝鮮の歴史書「三国史記」によれば、紀元前(BC)50年に当る年に早くも、倭人が出兵、(新羅の)辺境を侵そうとした
と記されているほか、奴国、伊都国、邪馬台国の時代にわたって、倭の進攻が記録されている。
この時代の倭国王が後漢の都まで生口160人を含めた大使節団を派遣する力をもっていたことを思えば、
兵船を列ね、対馬を経て朝鮮半島へ進攻することは充分あり得たと思われる。
そんな強国が、北九州沿岸部には古くから存在したのである。日向から出てきた東征途上の軍団が、不用意に乗り込んで戦闘状態になればどうなるか。
仮に全滅を免れたとしても、恐ろしいほどの消耗戦になることは必至であった。
東征軍にとって、長征の目的はあくまで建国であった。未来への展望を拓くことのできる豊かな土地が欲しかったのである。
12 岡水門(おかのみなと)を出航…『古事記』では滞在1年
1ヵ月も経たないうちに、東征軍は遠賀(おんが)川河口の岡水門(おかのみなと)を出発し、再び関門海峡を越えて瀬戸内海へと航行していった。
「東に美(よ)き地(くに)あり。なんぞ、行きて都となさざらん」という征討宣言の主旨からすれば、ここからが東征の本番であった。
軍船を列ねた武装兵団が、いまでいう周防灘を通過し、大小の島々の浮かぶ安芸灘から広島湾に乗り込んでくるのを眼にした周辺の国々は俄に緊張したことであろう。
それまでにも部族間の抗争は幾度となくあったであろうが、大規模な戦乱というものをこれらの国々は知らなかった。
乗り込んできたのが、瀬戸内文化圏の外側にある日向の軍団と知って、彼らの緊張は恐怖に変わっていったと考えられる。
|
 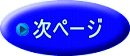 
|