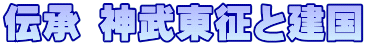 

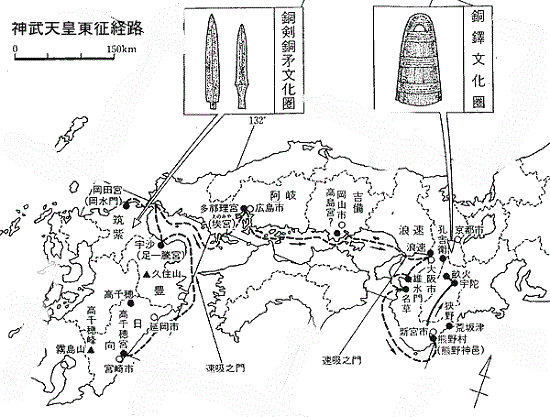 |
| 神武東征の経路図 |
7 神武東征の開始年代と時代背景
神武東征を史実とした場合、その年代をいつ頃にすべきかは、倭国大乱が前述の西紀174頃から180年頃とすれば、
狭野尊が東征のため日向を出発したのは西紀174年頃となり、その7年後の西紀181年頃にヤマト橿原で即位したことになる。
なぜなら狭野尊(磐余彦尊、神武天皇のこと。以下同じ)が建国のために東征を開始したことで、
中国歴史書にいう「倭国の大乱」に見合った様相が起きたと考えられるからである。その様相が現れ始めるのは、東征軍が瀬戸内海に軍船を乗入れた頃であろう。
『古事記』『日本書紀』には、この頃の時代背景は全く記されていない。したがって、
中国の歴史書を参考にすれば、すでに北九州の肥沃な土地に奴国や伊都国が栄え、それぞれ中国大陸に使節を派遣し、華やかな外交を展開していた。
奴国王は「漢委奴国王(かんのわのなこくおう)」という金印を後漢の皇帝から贈られ、伊都国王だったとみられる
倭王、帥升(すいしょう)は160人もの生口を使節団につけて後漢の都、洛陽に送り込んでいる。
独り日向(ひむか)の国だけは、遅れた土地にいたため時代から取り残された感があった。
現実には南九州の後進地域を拠点にしていたことが、遅れをとる最大の理由だったに違いない。
8 神武東征の宣言
狭野尊は4人兄弟の末っ子であった。父方は日向(ひむか)の高千穂の峰に天下ったと伝えられる天孫、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に連なる至高の一族である。
母は玉依姫(たまよりひめ)といった。長兄は彦五瀬(ひこいつせ)、次兄は稲飯(いなひ)、三男は三毛入野(みけいりの)と呼ばれた。
一族は日向の地に三代にわたって住みつき、優秀な家臣団に支えられ、この地の支配者として時を過ごしていた。
しかし、日向は痩せた土地が多く、銅、鉄、その他の産物も少なく、一国の都にするための条件を備えていなかった。
四代目の当主となった狭野尊は、あるとき、長兄の彦五瀬命に重大な計画を持ちかけた。~このまま、この地にいても将来の展望は開けない~というものである。
まず、この地を捨てることを決断し、一族と軍団をあげて希望の地に向け東征を開始すべきであるというものであった。
長兄の承諾を得た狭野尊は一族を集め、すべてを賭けて長征に出ることを宣言した。
『日本書紀』によれば、そのとき既に~東のかたに美(よ)き地(くに)あり。青山、四方(よも)をめぐる~
といった情報を得ていたようだが、はっきりとヤマトを狙った決断であったかどうかは分からない。
ただ、日向(宮崎県)を拠点にして兵を出すといった程度の戦略構想でなかったことは確かであろう。国を捨て、家を捨て、兵士の多くは妻子を捨てての大移動であった。
日向から海上ルートを通って行くには、多くの船舶や武器が要るし、船上で兵士たちに食わせる大量の食糧も必要であった。
少なくとも百人単位の兵団を構成し、できれば千人単位の大軍に増やして行きたい。そうしなければ夢の建国にふさわしい土地を手に入れることはできない。
『日本書紀』には、狭野尊、45歳にしての東征決断であったという。幸い一族には、他の集団にはない有利な条件がいくつか揃っていた。
一つは比類のないほど忠節かつ勇猛な家臣団が、主家を支えていたこと。後の大伴氏と久米氏である。
大伴の当主はこのころ日臣(ひのおみ)といった。久米は大伴とともに、天孫降臨のさいに皇孫、瓊瓊杵尊を守ったという伝承をもつ氏族である。
いわば大王家の譜代の兵団であった。さらには天種子(あまのたねこ)と呼ばれる家臣がいた。後の中臣氏である。
大伴氏とともに、後に大王家を支える二大軍閥となる物部氏は、この頃はヤマト地方にいて、まだ配下に加わっておらず、東征軍に敵対する勢力の一つであった。
彼らはヤマトの土着民ではなく、不思議なことに天孫族と同じように天下ってきたという伝承をもつ一族であった。
彼らが東征軍の傘下に加わるのは、軍団がヤマトに入ってからである。
『日本書紀』が採録した神話では天孫、瓊瓊杵尊が高天原から天下る際、大伴の先祖と久米の先祖が弓矢に大刀を携え、
背に矢筒を負って天孫の前に立ち、日向の襲(そ)の高千穂の峰に降り立ったとされている。
中臣氏の先祖、天児屋(あまのこやね)については、天照大神が天の岩屋に隠れる場面で、すでに登場している。
|
 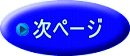 
|