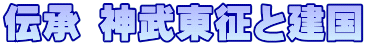 

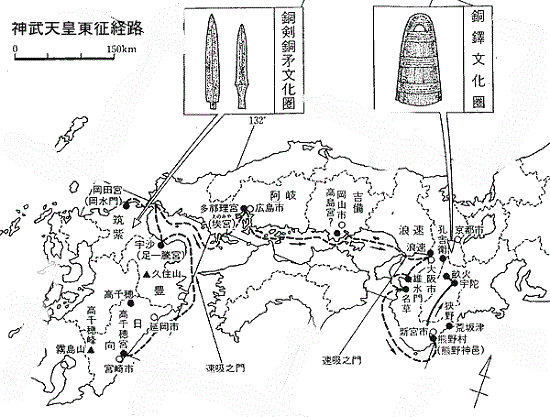 |
| 神武東征の経路図 |
4 神武東征の伝承
神武東征は、主に『日本書紀』に拠った神武天皇の事績である。内容が神話的で、神武天皇実在の真偽を含め、現在の歴史学では、そのまま史実として認められていない。
『古事記』にも神武天皇の物語があり、東征の経路などが若干異なるが大略は同じで、いずれも東征が大部分を占めている。
問題は、東征伝承の中に史実が含まれているのか、いないのかということである。しかし、最初に出くわす疑問が年代である。
日本を建国した初代神武天皇の即位日が、『日本書紀』によれば「辛酉年春正月、庚辰朔」とある。この辛酉年を西暦に換算するとBC660年に該当するという。
これが皇紀(紀元)元年の根拠になっている。ただし、『古事記』には初代から九代までの天皇の即位年は記されていない。
それはともかく、こんな先史時代に神武天皇が本当に即位したのであろうか。
併せて辛酉年=BC660年の換算は正しいのであろうか、といった疑問が湧いてくる。BC660年といえば、考古学上の区分ではまだ弥生時代前期である。
そんな先史時代に一人の英雄的人物に率いられた軍団が鉄器、銅器を持って船に乗り、水軍を列ねて遠征したとは考えられない。
しかし、『古事記』『日本書紀』が採録している神武東征の伝承には、現代の学界が否定しきれない部分があるという。
その一つが、神武天皇のような人物を一体だれが想像し作りだせたのかということ。
次に、一旦はヤマト地方の先住勢力に敗れ、天皇の身内にまで死傷者を出しながら、
紀伊半島を回って熊野から攻め込む説を誰が作り上げ、流布させたのであろうか。
やはり神日本磐余彦=神武天皇の原型となる傑出した人物が実在したと考えた方が、空想的学説より、はるかに合理的ではないだろうか。
神武東征が行われたからこそ、伝承として残っているのではないか。ある古代史研究者が「記紀神話の記述の中に、
わずかに含まれている史実、変形や虚構の部分であっても過去の歴史を知るうえで貴重な参考資料である」と述べている。
それを信頼しつつ、合理的な推理を進めてみたいものだと考えながら、思いに耽っていると、ふと思い出したのが十数年前、
一読した産経新聞連載の「古代からの伝言」であった。そこで改めて「古代からの伝言 日本建国」(八木荘司著・角川文庫)を読み返し共感を覚えた。
5 倭国大乱の史料と神武東征年代の推定
日本歴史の黎明期を推定できる古代文献史料は、国内では『古事記』『日本書紀』などと数少ない。
それも年代を特定する史料としては、あまり役に立たない。唯一年代を推定できる史料といえば、外国の古代文献史料か、遺跡を中心とした考古学史料に頼るしかない。
日本の歴史年表を紐解くと、紀元前後の「倭の小国百余国に分立」から西紀57年「倭の国王後漢に入貢、光武帝これに印綬を授ける」、
西紀107年「倭国王帥升ら、後漢の安帝に朝貢して生口160人を献上する」、西紀188年「倭国大乱、抗争続き、ついに卑弥呼を立てて女王とする」といった記事が眼につく。
これらの年表記事は『漢書』地理志、『後漢書』東夷伝、『魏志』倭人伝など古代中国史料が出典であるが、
これらの記事と日本建国及び神武東征の伝承が、どのような点で関連づけられるであろうか。
『古事記』『日本書紀』には、この頃の年代や時代背景は全く記録されていない。中国の歴史書を参考にすれば、
すでに北九州の肥沃な土地に奴国や伊都国が栄え、それぞれ中国大陸に使節を派遣して、華やかな外交が展開されていた。
奴国王は「漢委奴国王(かんのわのなこくおう)」という金印を後漢の皇帝から贈られ、伊都国王だったとみられる倭王、
帥升(すいしょう)は160人もの生口(奴隷)を使節団につけて後漢の都、洛陽に送り込んでいる。
独り日向の国だけが、遅れた土地にいたため時代から取り残された感があった。現実には南九州の後進地域を拠点にしていたことが、遅れをとる最大の理由だったに違いない。
このような時代背景を想定し、『日本書紀』に記された神武東征の年代を推定すると西紀180年頃になる。
この頃、「倭国」は相当な力をもち、船で大陸を往復し、奴隷を運ぶ力を持っていたことが窺われる。ただ「倭国」が、どの辺りを指しているのかが分からない。
恐らく北九州の一地域を指しているのではないだろうかというのが一般的である。
このように日本の歴史は、漠然としているが、この頃から歴史上の人々の姿が浮かび上がってくる。
次に西紀188年「倭国大乱、抗争続き、ついに卑弥呼を立てて女王とする」とある。
この「倭国の大乱」に関し、中国の歴史書で最初に記録したのが『三国志』のいわゆる『魏志』倭人伝である。
これには~その国、もとまた男子を以て王と為す。住(とど)まること7,80年、倭国乱れ、相攻伐(あいこうばつ)すること歴年乃ち一女子を共立して王と為す。
名は卑弥呼という(倭国ではもとは男王が立っていたが、七、八十年にして乱れ、戦いが何年か続いて後、卑弥呼を女王として共立した)~とある。
その後『三国志』より約150年後に書かれた『後漢書』、その約200年後に書かれた『梁書』などにも変形し記録されているが、問題は「倭国の大乱」が、いつ頃であったかということである。
前述の記録を解釈どおり読めば、国内で男王がいた確実な時期は西紀107年の倭国王・帥升の治世であり、
それから7、80年後をもってくると「倭国の大乱」は西紀170年代から180年代になる。
この後、女王卑弥呼が共立されるが、卑弥呼の年齢から大乱の年代を推定すれば、卑弥呼が死んだのが西紀248年として、
享年が満年齢で80歳なら、生まれたのは西紀168年、享年60歳なら西紀188年生れとなる。
十代の若さで女王に共立されたのなら、即位は早くて西紀170年代末となり、三十代で女王になったとすれば、即位は遅くて西紀218年以降になる。
つまり「倭国の大乱」はAD180年頃か、どんなに長引いても西紀220頃には終わっていたはずである。大まかにいえば、2世紀後半から3世紀初め頃となる。
このように「倭国の大乱」の年代を推定できたとしても、これを神武東征と関連付けるには、神武東征の情報が中国に伝わっていたことが前提条件である。
従って、倭国の大乱と神武東征を関連づけるには、なお多くの検討を要するが、今はこれ以上の推定ができない。
6 神武大王(狭野尊)の出自
神武大王の出自を簡単に箇条書きすると次のようになる。
★神武大王=神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)=年少時には狭野(さの)と呼ばれた。
★兄弟
長兄=彦五瀬(ひこいつせ)、次兄=稲飯(いなひ)、三男=三毛入野(みけいりの)の4人兄弟、狭野は末っ子であった。
★母の出自
空想的な伝承…母・玉依姫(たまよりひめ)=鮫の子ではないかという。
★母の姉、豊玉姫は子を産むところを夫に見られてしまうが、そのとき夫が見たのは、鮫がのたうっている姿だったという。
★狭野の父方は、日向(ひむか)の高千穂の峰に天下ったと伝えられる天孫、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)につらなる至高の一族である。
★ただし、日本書紀が伝える狭野自身の言葉は、天孫降臨から実に179万2470余年を経ているとのこと、神秘的というより茫漠たる宇宙的感覚である。
|
 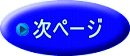 
|