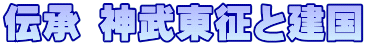 

 |
| 椿井大塚山古墳 |
43 旧邪馬台国(倭国)の女王壱与の運命
ヤマトを中心に近畿一円が統一されたとき、当然ながら倭の女王国は消えた。
彦国牽(第八代孝元天皇)の時代にヤマトに併呑されたとするのが、古事記、日本書紀の記述から推測されるが、
この前後、女王卑弥呼の跡を継いだ女王壱与は、その後、どのような運命を辿ったのであろうか。
卑弥呼の死後、倭国の国々は一旦騒乱状態となったが、やがて女王壱与(いよ)を共立することで合意し、
元通り女王を立てることによって、緩やかな連合体が回復したのである。
西紀266年、女王壱与は倭国連合を代表して、大陸の晋に対し新王朝樹立を祝って使節を派遣している。
壱与としては、従来通りの支援を晋から得たかったに違いない。
一方、ヤマト平野全域を制するという戦略目標を達成したヤマトの政権は、一旦北進を停止するが、国土統一への希望を捨ててはいなかった。
観松彦(第五代孝昭天皇)の没後、後に諡号でいえば孝安、孝霊の両天皇の時代を経て、
彦国牽(第八代孝元天皇)に至って、いよいよ強大に膨れ上がった兵力を背景に、再び北伐を開始する構えをみせる。
彦国牽(ひこくにくる)は大豪族、物部氏の系統から、二人の妃を得ていた。正妃(后)の内色謎(うつしこめ)と、その姪の伊香色謎(いかがしこめ)である。
後の軍事氏族の物部系と姻戚関係を固めることによって、大王家直属の兵を増強し、ヤマト国の版図を一挙に拡大しようと図ったのである。
物部の兵を主力とする軍勢は、ヤマト平野の南部、軽(かる)の地(橿原市)にあった都を出て、ヤマトの北域、今の奈良市へ進出し、大部隊で以て布陣した。
いつでも山背へ突入できる構えをみせ、いわば最後通牒を突きつける形で、女王国側と談判に及んだというのが、古事記、日本書紀の記述から想定できる光景である。
ヤマト側の元首は彦国牽である。対して女王国側は壱与がこの時もなお、女王の地位にあったかどうか明らかではない。
この頃、女王壱与が中国(晋)へ使節を送った西紀266年から10年以上は経っていたとみられ、この前後、
いかなる文献にも女王壱与が姿を現していないところをみると、既に世を去っていたかもしれない。
圧倒的な軍事力を背景にしたヤマト国側の弾圧によって、女王国はヤマトの国に併呑される運命を辿ったと推定される。
卑弥呼の時代から、東アジアの国際舞台に登場した倭の女王国は、この段階で歴史から消え去った。
山背から北河内、丹後に広がる広大な元女王国の領地は、彦国牽のヤマトに属することになったのである。
女王国併呑の時、女王壱与が生存していたか、既に世を去っていたかによって次のように想像される。
女王壱与は西紀236年生まれとみられ、女王国消滅のとき生きていたとしたら、すでに40歳代に達している。
かりに、ヤマト国への併合によって天皇(大王)家と姻戚関係を結ぶことになったと仮定しても、もう彼女自身が妃として迎えられるような年齢ではなかった。
つぎに想像されることは、女王国が消滅する前に、壱与がこの世を去っていた場合である。
考えられる年代は、彼女が晋(西晋)に使者を送った西紀266年から、ざっと10年の間である。
壱与は三十代の女盛りであった。王位についたまま壱与が死んだとすれば、どんな光景が展開されるであろうか。
その光景にぴったり見合う古墳がヤマトの北域、京都府山城町の木津川沿いで発見され、戦後の昭和期に発掘調査が行われた。
椿井大塚山古墳という。奈良市から北へわずか7,8㌔の距離である。旧女王国の中心部といっていい場所にあり、築造されたのは古墳時代のごく初めの頃とみられる。
今の考古学上の年代設定では、その築造時期を仮に西紀266年から10年の間とみなしても、何ら差し障るものはない。
全長169㍍の前方後円墳で、有名な箸墓古墳をちょうど3分の2に縮小したような形をしている。
この古墳から、長さ93.3㌢の中国製の大刀が見つかっているが、学界が最も注目したのは、36面もの銅鏡が現れたことであった。
うち32面は、卑弥呼や壱与の時代につくられた三角縁神獣鏡だった。しかも著名な考古学者の研究では、
同じ鋳型でつくられた複製品(同笵鏡)が近畿、中国を中心に全国23ヵ所の古墳から見つかっているという。
|
 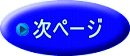 
|