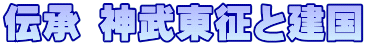 

 |
| 第八代孝元天皇(彦国牽尊)陵 |
42 ヤマト建国後、旧邪馬台国(倭国)を併合
狭野尊(神武天皇)の即位後、2代から9代までの時代は「欠史(闕史)八代」と呼ばれ、
いずれも実在しない架空の天皇だとする見方が、今も学界で大勢を占めている。
しかし、欠史八代の短い記述の中に、日本建国の実像を映し出す貴重な情報が込められ、
それがもしかしたら、女王卑弥呼が君臨したあの邪馬台国の謎を解く鍵になるかもしれない。
まず一つの手掛かりは、八代の天皇が宮殿を建てた地域である。その場所は彦国牽(ひこくにくる・第八代孝元天皇)までは、すべて奈良盆地の南部に限られている。
大日日(おおひひ・第九代開化天皇)に至って、初めてヤマトの北部、今の奈良市内に進出しているのは何故だろうか。
狭野尊が建国したとされるヤマトの領域を辿ってみれば、奈良盆地の南半分から多くは出ていない。
『日本書紀』には神武東征軍が今の大和郡山市のあたりまで、地元勢を追って掃討戦をやったことが記されている以外、北ヤマトへ攻め込んだという伝承はない。
つまり、北の勢力と奈良盆地を南北に分け合った状態が続いたと考えられる。
では、ヤマト平野の北部から山背(京都府南部)にかけての豊かな水系に恵まれた領域を制していたのは、誰れであろうか。
それこそが『三国志』の魏志倭人伝に登場する倭の女王卑弥呼の邪馬台国である。
つまり女王国と九州からきた狭野尊が建国したヤマト国(熊野国・狗奴国)が、西紀245年頃までヤマト平野に並立していたのである。
女王国では南の熊野からヤマトに攻め込んできた日向の勢力を 熊野国と呼んでいたが、
この「くまのこく」の音が中国側に狗奴国と表記され、魏志倭人伝に記録されたのである。
~倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王・卑弥弓呼(ひみくこ)と、もとより和せず~と倭人伝にあるとおり、つねに対立していた両国であったが、
女王壱与(いよ)の時代になって後、いよいよ南からの攻勢が強くなり、ついに女王国が併呑されるという劇的な変化が起きた。
それが彦国牽(第八代孝元天皇)の時代だったとみられるが、『古事記』『日本書紀』では欠史時代であったため、この画期的な出来事が何一つ記録されていない。
次いで大日日(第九代開化天皇)が建国以来、初めて北ヤマトに都を遷し、今の奈良市春日に宮殿を建てたのが、推定では西紀280年代である。
狭野尊が建国したヤマト国は、実は奈良盆地の南側であったと推定されるが、もう一つのデータは『古事記』『日本書紀』にある妃の出身地である。
ヤマト入りを果たして後、国つ神系の本拠、三輪山から大物主神の娘といわれる五十鈴姫を召し入れて正妃にしている。つまり平定した土地から、后(正室)を迎えたのである。
欠史八代の天皇の正妃をみると、第四代までは奈良盆地南部の出身であり、特に南東部の磯城(奈良県磯城郡)の県主の娘という伝承が多い。
ところが、観松彦(第五代孝昭天皇)が尾張から正妃を迎えたあと、彦国牽(第八代孝元天皇)の時代になって状況が一変する。
まず正妃には大和の北東部、今の奈良県山辺郡を本拠とする物部系の穂積一族から、
当主の妹、色謎(うつしこめ)をもらい、その姪の伊香色謎(いかがしこめ)を側室にした。
さらに、北河内の豪族ではないかと思われる河内青玉(かわちのあおたま)の娘、埴安媛(はにやすひめ)を第三の妃にしている。
ヤマト南部の出身女性は一人もいない。そればかりか、側室の伊香色謎は夫の死後、正室の子である大日日(第九代開化天皇)と再婚し、その正妃となっている。
彼女から生まれた長男が、古代史に名高い御間城入彦(第十代崇神天皇)である。
つまり彦国牽(第八代孝元天皇)の時代から、妃の出身地が突如としてヤマトの北方から河内あたりまで広がっている。これは何を意味しているのか、いうまでもない。
彦国牽が旧邪馬台国の領域を併呑し、山背(京都府)から北河内(大阪府)までを支配下に収めたのである。
ついで大日日の時代になると、妃の出身地は日本海側の竹野(京都府京丹後市)にまで及び、
その次世代では近江(滋賀県)から山背、丹波、そして紀国(和歌山県)へと広がっていく。
やはり彦国牽の時代が、歴史の転換点になっているのは間違いない。かつて女王卑弥呼が統治していた国は、狭野尊が建国したヤマト国に統合されたのである。
父祖、狭野尊が目指した建国の大業は、伊香媛(伊香色謎)の夫と子によって成し遂げられたことになる。
狭野尊が日向を出て東征の途についたときから御間城入彦の即位まで、ざっと120年の歳月が流れ、西紀294年頃になるであろう。
|
 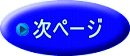 
|