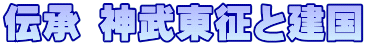 

 |
| 神武天皇(狭野尊)の御陵 |
39 狭野尊は正妃を迎え、奈良盆地南側と熊野一帯を制覇
狭野尊(神武天皇)が正妃として迎え入れた女性は、多分に神話的色彩を帯び『古事記』『日本書紀』に登場してくるが、紛れもなくヤマトの地元女性であった。
『古事記』と『日本書紀』がほぼ共通して伝えるところでは、大久米は三輪山の大物主神(おおものぬしのかみ)の娘、
媛蹈鞴五十鈴媛(ひめたたらいすずひめ)を探してきて、主君のために出合いの場をつくってさしあげる。
狭野尊は五十鈴媛を正妃とし、八井耳(やいみみ)と渟名川耳(ぬなかわみみ)の2人(古事記では3人)を生むが、
二代目大王となる渟名川耳も、後に五十鈴媛の妹を正妃に迎えている。
ここで重要な意味をもつのは、妃たちの出身地である。五十鈴媛の姉妹が、三輪山(奈良県桜井市)の大物主神を父としているように、
伝承の上で名の上がっている他の妃たちも、少なくとも第4代懿徳(いとく)大王まではすべてヤマト南部の出身である。
後世、大王家の婚姻の範囲は尾張、近江、播磨、吉備へと、国家統一の事業が進むにつれ広がっていくが、
懿徳大王までの婚姻関係からみれば、初期の時代に大王家が制覇した地域は、奈良盆地の南側に限られているといってよい。
東征軍が確保した領域は、ヤマト平野の南部とその背後に広がる熊野、菟田などの山間部だけだったとみられる。
狭野尊が建国した最初の国は、奈良盆地南部の狭い領地でしかなかったのである。
40 狭野尊が橿原宮で即位
狭野尊が、橿原宮で即位する時がきた。『日本書紀』にいう辛酉年の1月1日である。
日本人の多くは、狭野尊による建国の伝承が『古事記』『日本書紀』に記載されていることを知っている。
『日本書紀』の伝える即位の日を太陽暦に直せば、「建国記念日」(紀元節)の2月11日になるらしいことも、一応は常識になっている。
しかし、狭野尊の即位の様子がどのように『古事記』『日本書紀』に描かれているかとなると、
実際に確かめた人は稀にしかいないと思われる。狭野尊即位の件(くだり)を次に引用してみる。
まず『古事記』には~かくて、荒ぶる神どもを平定し、伏せぬ者どもを撃退して、畝傍の白檮原宮にあって天下を治められた~とあり、
これがヤマトの平定と治世に関する記事のすべてである。
ここには即位の模様を伝える記述はなく、治世についても原文では~坐畝火之白檮原宮、治天下也~と漢字で12字という、素っ気ないほどの扱いになっている。
『古事記』はよく知られるように、稗田阿礼が勅命によって習い覚えた帝紀や旧辞などを、
太安万侶が筆録して完成させた歴史書であるが、神武天皇の即位については、もとの資料にもほとんど伝わっていなかったものと思われる。
これに対して『日本書記』は、『古事記』より少し詳しく記されているが、即位の記述は、やはり極めて短い。
~辛酉年の春正月元日に天皇(すめらみこと)、橿原宮に即位す。この歳を天皇の元年とす~原文では、わずか25字である。
つまり『古事記』『日本書紀』ともに狭野尊の即位という最も重要な出来事に対して、ほとんど粉飾していないということである。
伝承をそのまま、できるだけ正確に建国の模様を伝えようとしたのではないだろうか。
『古事記』『日本書紀』を編纂した当時の学者たちの歴史、あるいは伝承に対する誠意を感じ取るべきであろう。
ただし、狭野尊即位の年が、西暦で紀元前(BC)660年の辛酉年ということになる『日本書紀』の記述は、そのまま受け入れることはできない。
『日本書記』の場合、原則として持統天皇までの四十代の天皇即位の年と、神功皇后の摂政元年、
崩御年などを干支で表しているが、問題は狭野尊が即位したとする辛酉年に何らかの根拠があったかどうかである。
『日本書記』が原資料とした中に、神武東征の開始を甲寅の年とし、即位の年を辛酉とする記録、あるいは伝承があったに違いないと思われる。
それが西暦に換算して紀元前(BC)660年という遠い昔のことで有り得ないとすれば、一体いつ頃の辛酉年だったのか。
干支は60年で一巡するのだが、結論からいえば、狭野尊(神武天皇)の即位は西紀181年の辛酉年だったと考えられる。
つまり、狭野尊は西紀174年の甲寅年に日向を出発し、岡山で3年を費やすなど足掛け7年かけて東征を終え、西紀181年の辛酉年に橿原宮で即位したことになる。
中国の歴史書にいう「倭国の大乱」が後漢の光和年間(西紀178年から184年)だとすれば、神武東征の甲寅から辛酉までの間は、これに大体見合っている。
その他、瀬戸内海地方に見られる高地性集落の山上遺跡など、さまざまな傍証を積み上げていくと「倭国の大乱」が終わり、
狭野尊(神武天皇)が即位した年、つまり日本の紀元は考古学でいう弥生時代後期になる西紀181年であったと断定しても良いのではないか。
この推論が正しいとすれば、西紀2000年は皇紀1820年ということになり、昭和の末年は皇紀1809年である。
これを神武天皇から昭和天皇までの124代で割って在位年数の平均を出すと、一代14.5年となる。
天皇の在位年数がほぼ確実に分かっているのは、聖徳太子の父の第31代用明天皇辺りからだが、
用明天皇から昭和天皇までの平均をとれば、一代15.0年となって、大体のところ一致する。
つまり古代日本の真実の姿が、皇紀元年を西紀181年とすることによって現れてくる。その悠久の歴史を踏まえつつ、ヤマト建国後の動きを概観してみたい。
41 狭野尊(神武天皇)即位年の辛酉年を検証
日本書記は狭野尊が日向を出発した年を甲寅年とし、これを起点に歴代天皇の即位を干支で表すとともに在位年数を記録しているが、
それによると、狭野尊が即位した辛酉年は、最初の女帝である推古天皇9年(西紀601年)から遡ること1260年前という途方もなく遠い昔のことになってしまう。
日本書記がなぜ、神武即位の年を辛酉年にしたのかについては、明治期の歴史学者、那珂通世(なかみちよ)による仮説があって、
中国古代の俗信である讖緯説(しんいせつ)によれば、1260年(干支21巡目)ごとの辛酉の年に大革命が起きるとされている。
推古天皇9年は辛酉年にあたるので、そこから1260年前の辛酉年を日本の紀元とした、というのである。
もし、この辛酉年が正しいとすれば、推古天皇9年には王朝が転覆するような大変革がなければならないのだが、
この年は聖徳太子が斑鳩に宮を建てたぐらいのことで何事も起きていない。
大体、万世一系の天皇制を記録している日本書記が、王朝転覆を予言するような中国の俗信によって皇紀を定めることがあり得るのか、
といった疑問は問題にならず、那珂通世の仮説が今では、すっかり定説化してしまっている。
讖緯説については、国家滅亡の流言飛語のもとになり、社会不安を煽るというので、中国でもしばしばこれを禁止する措置がとられている。
では、那珂通世の説が的外れな推測にすぎないとすると、なぜ日本書記は神武天皇(狭野尊)即位の年を辛酉年としたのだろうか。
この問題を考える前に、古事記に記してある年代をみると、第十代崇神天皇の崩御の年を戊寅(つちのえとら)の年としているのが最初である。
この戊寅(ぼいん)年を西暦に換算すれば西紀318年にあたり、崇神天皇が亡くなった年としては、ぴったりと現実にあう。
考古学的にも文献上も、4世紀はじめの西紀318年に崇神天皇が亡くなったとして、何一つ祖語をきたすことはない。
つまり崇神天皇=御間城入彦(みまきいりひこ)の死去が戊寅年だったという古事記の記述は、
出鱈目な憶測ではなく、はっきりした根拠があってのことであろうと思われる。
中国の暦法が女王卑弥呼の時代には、既に入っているとみられるので、古事記が拠った資料に「戊寅」の記録があったと考えていいのではないか。
ほかに仁徳天皇西紀427年(丁卯ひのとう)、雄略天皇西紀489年(己巳つちのとみ)、推古天皇西紀628年(戊子つちのえね)など、
古事記の記載する天皇の崩御年はかなり正確なもので、確かな原資料によった記録であるとみて間違いない。
古事記は推古天皇まで33人の天皇について記録しているが、うち崩年干支が記されているのは、崇神天皇をはじめ15人にすぎない。
日本書記の場合、原則として持統天皇までの四十代の天皇の即位の年と、神功皇后の摂政元年、
崩御年などを干支で表しているが、問題は神武天皇が即位したとする辛酉年に何らかの根拠があったかどうかである。
日本書記が原資料としたものの中に、神武東征の開始を甲寅の年とし、即位の年を辛酉とする記録、あるいは伝承があったに違いないと思われる。
|
 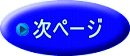 
|