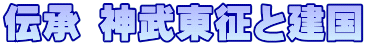 

 |
| 狭野尊の弓先に止まった金鵄の絵画 |
36 饒速日(にぎはやひ)が長髄彦(ながすねひこ)誅殺し降伏
突然、饒速日が配下の長髄彦を誅殺して、首を差し出してきたのである。敵の内部抗争かと思いきや、そうではなかった。
饒速日は彼なりに国の将来を思い、狭野尊に臣従することが最善の道と考えたに違いなかった。
饒速日が末代までの命運をかけて決断したのは、日向から乗り込んできたという狭野尊の人物に魅了されたからに違いない。
事実、饒速日の後裔とされる物部氏は、西紀587年、いわゆる蘇我・物部戦争で宗家が滅ぼされるまで、大王家への忠誠を貫き、ヤマト朝廷を支え続けた。
饒速日が長髄彦を誅殺して帰順したことで、ヤマト平野の少なくとも南側は、東征軍に対抗できる勢力はなくなった。
あとは、彼らが土蜘蛛などと侮蔑的に呼んでいる在地の小勢力のうち、反抗的な部族を掃討するだけであった。
饒速日と長髄彦の部隊を加えた狭野尊の軍は、一気に二倍以上に膨れ上がった。
『日本書記』が記す部族名をあげると、今の奈良県天理市辺りにいたとみられる居勢祝(こせのはふり)や、御所市付近の猪祝(いのはふり)などである。
反抗する者は、容赦なく皆殺しにされた。『日本書紀』には皇師(皇軍)という言葉が使われているが、戦いの現実を美化することは決してしていない。
37 神武東征の勝利宣言
戦いが終わり、狭野尊が東征の勝利を宣言する待望の日がきた。勝利宣言が行われたのは、神日本磐余彦尊の称号の由来となった磐余の地である。
~東征の途に就いて6年、われら天神の威をもって征討を行ってきた。辺土はなお鎮まらず、いまだ禍尽きぬところがあるとはいえ、
中洲(うち)の地は漸くにして鎮定された~『日本書記』には狭野尊の勝利宣言がこのように記されている。
狭野尊の勝利宣言はさらに続いて、都(宮殿)を建設する場所として橿原を指定する。
~かの畝傍山の東南の橿原の地は、けだし国の中枢となるところ、この地を都とすべきである~
畝傍山は天香具山、耳成山とともにヤマト三山といわれ、古代から名の通った丘である。
~すなわち有司(ゆうし)に命じて帝宅を造り始める~日向を出て6年、初めて領地を治める政庁となる宮殿の建設が始まった。
この橿原の地であるが、『古事記』に~畝火の白檮原(かしはら)~と記してあるように、シラカシの林があったらしく、
昭和期の発掘でその跡が確認されている。これも、神武天皇の伝承が虚構でないことを示す傍証の一つと考えてもいいのではないだろうか。
38 狭野尊の勝利と論功行賞
『日本書記』によれば、この後、将兵の論功行賞が行われている。彼らには褒賞として領地、宅地が与えられたのだが、注目すべきはその範囲であった。
まず最大の功労者、後に大伴氏の祖である道臣には、~宅地を賜いて、築坂邑(つきさかのむら)に住まわせ、とくに重用された~とある。
築坂とは、今の橿原市鳥屋町の辺りで、畝傍山の南2㌔ほどのところである。
次いで久米軍団を率いる大久米だが、彼は畝傍山の西の川原の地が与えられた。後に久米邑と呼ばれるところで、築坂より一層橿原宮に近い。
道臣、大久米とも、伝承上は天孫降臨の前からいわば譜代の重臣である。では東征の途上で加わった者はどうであったのか。
東征軍が熊野の山岳地帯を突破し、ヤマトへのとば口ともいうべき菟田の地に至ったとき、
兄と袂を分かって帰順してきた地元勢の弟猾には、その功が評価され猛田邑(たけだのむら)が与えられている。
多分、菟田を治める県主、後世でいえば領主の地位が保障されたのであろう。
同じく最終場面で帰順した黒速は磯城の県主となった。これら論功行賞の領地を繋ぎ合わせていくと、
ヤマトを制したといわれる実態が浮かび上がってくる、勝利宣言にある「中洲の地」とは、果たしてヤマトの全域を指しているのだろうか。
|
 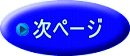 
|