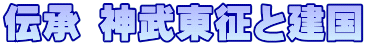 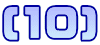

 |
| 弓先に止まった金鵄で反撃する狭野尊 |
32 流浪の軍団に疲労の色
しかし、当面の敵の主力は壊滅したが、他に南ヤマトの十数ヵ所に敵勢力が割拠している。
九州から乗り込んできた軍団がヤマトに現れたことが伝わると、彼ら地元勢は一致団結して逆襲してくるかもしれない。
東征軍としては敵を個別撃破することを作戦の基本としているので、敵勢力を一つにまとめさせてはならない。
そのために本営を移し、動いては撃ち、動いては撃ち、敵勢を蚕食しつつ味方を増やし、互角の勢力になったところで決戦を挑まなければならない。
今、『日本書紀』の記述にしたがって東征軍の動きを追ってみると、この辺りまでは、まるで流浪の軍団であった。拠るべき本拠地を九州に捨ててきたからである。
その後、小規模な戦いであったが連戦連勝の兵士たちに、深い疲労の色が見え始めたのは、ヤマト入りを前にしての山場を迎えたときであった。
士気が著しく落ちているのも、疲労のせいである。東征軍が制した菟田、吉野から兵糧が前線に
送られてくるはずであったが、この地域全体が貧しく、支援は途絶えがちであり、その都度兵は飢えた。
33 鵜飼民の食糧支援で軍団に勢いヤマト入り
直ちに狭野尊から吉野へ食糧支援を促す部隊を派遣せよと指示が出された。
このとき、狭野尊が将卒の心を慰めるために作ったとされる歌が『古事記』『日本書紀』の両方に採録されている。
~戦えば、我はや飢えぬ、嶋のとり、鵜飼いの徒(とも)よ、いま助(す)けに来よ~歌はこのように、吉野の鵜飼い民に食糧の救援を求めるかたちで終わっている。
この後、東征軍はおそらく後背地の菟田の山間部まで退いたのであろう。兵を休めて英気を養ったのち、
再び軍団が前面に登場したのは、ヤマト入りを阻んでいる敵勢の首領、兄磯城との戦いであった。
決戦場となったのは、地元勢が東征軍のヤマト入りを阻止するため構えていた墨坂の麓であった。
東征軍は和戦両様の構えを見せながら、おとり作戦を使って敵を誘い出し、前後から挟撃し一気に殲滅、待望のヤマト入りを果たした。
34 東征軍最後の決戦で連戦連敗
東征軍が南ヤマトの地元勢の首魁、兄磯城(えしき)を破って誅殺したあと、立ち向かってきたのは
ヤマトを守る敵の本隊ともいうべき長髄彦(ながすねひこ)の軍勢であった。
長髄彦は、東征軍が最初に生駒山を越えてヤマトに攻め入ろうとしたとき、打ち負かされ、敗退した相手である。
彼らはヤマト平野の北側を本拠としている部族であったが、彼らの上に立つ勢力に命じられ、
東征軍の進攻で混乱する南ヤマトへ急きょ、兵を移動させてきたのであった。
東征軍にとっては、建国への最後の決戦であった。長髄彦の軍を破らなければ、ヤマトでの建国は有り得ないのである。
両軍が戦端を開いたのは、ヤマト平野の南東部であった。東征軍は一日も早く磐余の地
(奈良県桜井市)を確保し、本営を置いてさらに北進し、ヤマトの中央部までを制圧したかった。
しかし、敵勢力の中核部隊である長髄彦の軍は精強であり、練度が高く、見事な進退をみせた。
この時代、狭野尊の率いる東征軍は、いかなる勢力と比べても戦闘部隊としては抜きん出た水準にあったといえよう。
彼らは農地を耕すでなく、山で働くでもなく、この数年というもの、ただ戦うだけの存在であった。
戦ってその地域を庇護すれば、民が食わせてくれる。先進的な土地であれば、鉄や銅の武器の調達も容易であった。
いわば職業集団と化している彼ら東征軍が、満を持して攻め込んだ決戦の場であったが、なぜか長髄彦の軍に跳ね返されてしまうのである。
連戦連敗であった。まだ総力戦の段階ではなく、部隊ごとに衝突を繰り返している程度であったが、
戦えば必ず負けるということは、どうしたことか、理由が分からなかった。
35 狭野尊の弓先に止まった金鵄で反撃
天孫族である狭野尊の至高の一族に対し、敵側が怖気つくことのない理由があった。
敵の長髄彦を背後で操っている、この地方の支配者、饒速日(にぎはやひ)も、天上から天磐船に乗って
降りてきたという部族の伝承をもち~われらも天神の末裔なるぞ~と呼号し、兵を励ましているというのである。
この饒速日が、後に大伴氏と並んで大王家を支える二大軍閥となる物部氏の祖先だとされているが、
この当時からすでに軍事的に優れた力を持っていたらしく、長髄彦が勝ち続けたのも、彼らの強力な後押しがあったからであろう。
『日本書記』の記述を信じるなら、狭野尊の東征軍が長髄彦を攻めたのは、厳しい寒気が
地を覆う真冬の季節であり、空は陰鬱に曇り、冷たい氷雨が敗勢の兵の全身を濡らしていた。
後世、昭和期まで語り伝えられることになる奇跡は、そんな時に起きた。~すなわち金色のあやしき鵄(とび)あり、
飛び来たって皇弓(みゆみ)の先(弭ゆはず)にとまる~鵄は金色に輝いて見え、まるで電光のようであったたという。
長髄彦の兵士は、その光に幻惑されたのか、攻め続けていた勢いが止まった。東征軍反撃の好機であった。
東征軍の兵に「全軍、踵をかえし総攻撃にうつれ」の指令がとび、たじろぐ敵兵に対し、一斉に攻撃に転じた。
ついに音をあげた長髄彦は、使者を送ってきて和睦のための釈明を始めた。それは以下のようであった。
~自分たちがこの地方の支配者、饒速日に仕えているのは、彼らが天神の一族と称しているからである。
しかるに、ここにまた天孫を名乗る方がきて、この地方を奪うということになると、
いずれを信じればいいのか分からなくなってしまうではないか~というのであった。東征軍にとっては、長髄彦との和睦ということはあり得ない。
~降伏するか、さもなくば死か~それ以外の道を長髄彦に許してはならないのである。
双方、天神の末裔であることを示す家宝(天の羽羽矢という名の矢と、歩靫⦅かちゆぎ⦆と呼ばれる矢筒)を見せ合うと、
長髄彦は東征軍に対しても畏れかしこまった素振りをみせたが、その一方で部隊は要所に張り付けたまま退こうとはしなかった。
狭野尊を前に、重臣たちが長髄彦の処遇について意見を戦わせているとき、全く予想していなかった事態が起きた。
|
 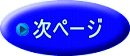 
|