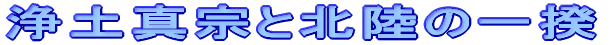 |
|---|
3.2蓮如の吉崎布教 (1) 蓮如と吉崎道場 ○ 吉崎移住までの経緯 長禄元年(1457)43歳で本願寺第8代留守職を継職した蓮如は、当初、近江国堅田、金森、赤野井など琵琶湖周辺の門徒を頼って教線を拡大しました。 従来の聖教に加え、新たに御文(御文章)の授与を始めて門徒衆を拡大していく一方、本願寺や門末に安置された真宗に相応しくない絵像や木像を焼却し、 比叡山延暦寺膝下、近江地方の人々が急速に真宗門徒化するにつれ、比叡山衆徒から無碍光衆の邪徒と厳しく批難され、 さらに真宗高田派専修寺からも無碍光の愚類と批判され、ついには寛正6年(1465)比叡山衆徒によって本願寺を破却されてしまいました。 蓮如は命辛々本願寺を逃げ出し、琵琶湖周辺の末寺を隠れ住みながら布教を続けました。 以後、無碍光本尊の授与を中止し、白紙に『南無阿弥陀仏』の六字を墨書した名号に変更したといわれます。 当寺、近江・山城国では各地に土一揆が頻発し、近江の堅田・金森・赤野井門徒は結束を強めていきました。 これに対し荘園領主・宗教的権力者であった比叡山延暦寺は本願寺門徒や庶民の不穏な動きを憤り、座視できずに武力行使に出ました。 寛正6年(1465)から応仁2年(1468)にかけて近江赤野井門徒、堅田門徒衆は比叡山と対立・激戦となりますが敗退します。 他方、応仁元年(1467)京都では応仁・文明の乱が発生して混乱し、多数の都人が地方へ移り住むようになります。 こうした社会情勢の中、近江での布教活動に限界を感じた蓮如は、他に布教の天地を求める決意をし、 応仁2年(1468)3月下旬、大津を発って布教拠点となるべき適地を探しながら畿内、東海、北陸などを巡錫しました。 応仁3年(1469)春、三井寺万徳院の庇護の下、近江門徒の協力で三井寺山内の近松村南別所に新坊舎を建立、 文明元年(1469)11月完成させると顕証寺と命名し、ここに「根本之影像」を安置し、同寺を仮の本寺と定めました。 ○ 吉崎を最適地とした理由 あらかじめ畿内、東海、北陸などを巡錫しながら適地を探して事前踏査をした結果、蓮如は加越国境に位置する越前国吉崎を最適地と判断しました。 その主な理由は ① 吉崎は興福寺大乗院の所領であり、住持経覚の母は本願寺出身の遠戚、しかも現地の荘官が末寺、和田本覚寺の蓮光であった。 ② 吉崎の地が優れた要塞性を備えた地形を有していた。 ③ この地が北陸街道に近く、舟便の利用も可能な交通至便な位置にあった。 ④ 本願寺派の寺院が越前・加賀に点在し、互いに連携のとれる国境に位置していた。 ⑤ この地の名主である大家彦左衛門吉久が覚如以来の本願寺派末寺、田嶋興宗寺の門徒であったことなどです。 こうして吉崎を布教拠点に決めた後、直ちに移住できなかったのは、応仁の乱が越前・加賀にも波及し、 越前朝倉氏は西軍に属しており、東軍に好意を寄せていた蓮如にとって孝景との交渉に一抹の不安があったことです。 しかし、その不安も朝倉氏が東軍に寝返ったこと、和田本覚寺蓮光の働きで朝倉氏から吉崎使用の了解が得られたことで消えました。 ○ 吉崎へ移住、道場で布教活動 文明3年(1471)5月上旬、58歳の蓮如は大津から越前へ向けて旅立ちました。越前の田嶋興宗寺に着くと和田本覚寺以下坊主衆を集め、 吉崎道場建設の具体的な計画を話し合い、彼らと共に細呂宜郷吉崎へ行って詳細な打合せを行いました。 その後は2、3人の側近衆を連れて約1ヶ月ほど加賀各地を巡錫し、7月中旬、吉崎へ戻ると名主大家彦左衛門方で道場の完成を待ちました。 同年9月中旬、吉崎山上に道場がほぼ完成し、布教活動を始めることになりましたが、道場完成直後から蓮如自身が驚くほど続々と 北陸各地の門徒が群参し、翌年1月には早くも門徒の群集参拝を禁ずるほど盛況となりました。 そして吉崎道場の周辺には次々と多屋が建てられ、その後、商人達や諸物資を生産する職人達が移ってきて、次々と家を構え瞬く間に一大寺内町が出現しました。 ○ 門徒群参現象の淵源 本願寺門徒をはじめ庶民の群参現象の淵源は、北陸地方に古くから培われてきた浄土信仰の蓄積、 室町末期、乱世を覆っていた末法思想の社会情勢、それに蓮如が考え出した斬新な伝道手法が相俟って現出した成果と考えられています。 中でも道場開創初期の吉崎ブームに大きな比重を占めたのが、蓮如の分かりやすい教義と伝道法式、そして積極的な伝道姿勢であったといえます。 北陸各地の寺坊主や道場坊主らに率いられた門徒達は、蓮如が平座で門徒に臨み、同朋・同行を力説し、分かりやすい言葉で弥陀の本願を諄々と説く姿を見て、 これまでの坊主が高座から権威的な態度で門徒に臨んでいた風習しか知らなかった庶民にとって、新鮮な驚きと親しみを感じさせるとともに、熱烈な信仰心の虜にさせました。 こうして無知な庶民達は門徒の列に加わることで現世を生きる希望と来世での願望を併せ持つ「安心」の境地を得るものと信じ込みました。 (2) 蓮如の伝道手法 蓮如が吉崎道場において実行した伝道手法を要約すると次の3点といわれます。 ① 分かりやすい教義 教義を「信心為本」(信心正因)、「称名報謝」(仏恩報謝)、「平生業成」の三本柱にまとめ、分かりやすく「御文(御文章)」の中で述べたことです。 「何人でもただひたすら弥陀の本願を信じて(信心為本)日々感謝の念仏(称名報恩)を唱えさえすれば、それが極楽往生に通ずる早道である。」という教えです。 ② 新しい伝道方式の実践 ア 「御文」を活用した布教 蓮如は真宗の要義を解りやすく述べ、庶民大衆に信仰の大切さを説いて入信を促し、また、一向衆の間にはびこっていた異義を批判し、 正しい浄土真宗の教義を説き、更には坊主や門・信徒の反社会的な言動を戒めて、その守るべき規範を「掟」として示しました。 イ 「講」の結成と組織化による布教 近隣の人々が念仏のために集まる小集会を「寄合」と称しましたが、蓮如は寄合の大切さを説き、互いに話し合うことを奨励しました。 仏の前では全ての者が同朋・同行であるという認識を強め、彼らの信仰心と門徒としての連帯感を深めるためでした。 この寄合がいくつか結合して道場単位の集会に発展したのが「講」であり、講を組織する場となる道場づくりは、 村々の有力者(坊主・ 道場は集落毎の道場のほかに、いくつかの集落で形成された「惣」を基盤にした惣道場というものもありました。 惣道場の坊主は惣村を束ねる名主・沙汰人級の有力者またはその一族が就任することが多かったようです。 蓮如が意図した「講」の組織化は、現実に社会機構の末端をすっぽり包む形で出来上がっていきました。 ③ 勤式の制定と聖教の開版 ア 勤式の制定 宗祖親鸞が作った「正信偈」と六首の「和讃」の イ 聖教の開版 文明5年(1473)3月、「正信偈」に「浄土和讃」「高僧和讃」「正像未和讃」を加えて四帖の聖教を版木を起こして刊行することを考えました。 この吉崎における聖教の開版は大衆伝道の技術的な革命であったといわれています。 (3) 一向一揆の発生 蓮如の熱心な伝道によって参詣する群参者は日毎に増え続けていきましたが、それを また、坊主や門徒の中には反社会的な言動を弄する者も混ざっており、支配者層との軋轢も高まっていきました。 こうした不穏な情勢を憂慮しつつ、蓮如の「御文」は次第に「掟」の性格を帯びてきますが、門徒達の行動を止めることはできませんでした。 室町末期の複雑な支配権が並存する社会体制の中で、過酷な年貢徴収や公事に不満を募らせていた村々に住む国人・土豪達は、 真宗に改宗して門徒達の「講」仲間に加わり、これを利用して支配者(守護)と対決していったのです。 やがて国人、地侍、名主百姓などは門徒達の団結力を利用して、各地で一向一揆を起こしていくことになります |