 


14 弥生時代の人々(2)
●弥生人の特徴
頭蓋骨の計測値で弥生人に最も近いのは、新石器時代の河南省、青銅器時代の江蘇東周・前漢人と山東臨淄(りんし)前漢人であった。
また、眼窩は鼻の付け根が扁平で上下に長く、丸みを帯びていて、のっぺりとしている。歯のサイズも縄文人より大きい。平均身長も162~163㌢ぐらいで、縄文人より数㌢高い。
しかし、こうした人骨資料のほとんどは、北部九州・山口・島根県の日本海沿岸にかけての遺跡から発掘されたもので、
南九州から北海道まで、他の地方からも似た特徴を持つ弥生時代の人骨は発見されているが、それらは人種間の形態とその発生頻度までを確定付けるには至っていない。
近年、福岡県糸島半島の新町遺跡で大陸墓制である支石墓から発見された人骨は縄文的習俗である抜歯が施されていた。
長崎県大友遺跡の支石墓群から多くの縄文的な人骨が発見されている。さらに瀬戸内地方の神戸市新方遺跡からの人骨も縄文的形質を備えているという。
ただ、福岡市の雀居(ささい)遺跡や奈良盆地の唐古・鍵遺跡の前期弥生人は、弥生系の人骨だと判定されている。
つまり、最初の弥生系と考えられている北部九州や瀬戸内・近畿地方でさえ、弥生時代初期の遺跡からは弥生系の人と判定される人骨の出土数は縄文系とされる人骨より少ない。
水田耕作の先進地帯でも、縄文人が水稲耕作を行っていたのではないか。絶対多数の縄文人と少数の大陸系渡来人との協同のうちに農耕社会へと移行したと考えられる。
鈴木尚は、縄文時代から現代までの南関東の人骨を比較研究後、縄文人から弥生人への体質変化を生活環境の変化と考えた。
狩猟・漁労生活から農耕生活へと生活環境を一変させた変革こそ形質を変えることになったと理解した。
一方、1960年代になると金関丈夫が、山口県土井ヶ浜遺跡や佐賀県の三津永田遺跡などの福岡平野の前・中期の弥生人骨の研究から、
弥生時代の人の身長は高く、さらに頭の長さや顔の広さなどが中国大陸の人骨に近く、縄文時代人とは大きな差があると指摘し、
縄文人とは違った人間が朝鮮半島を経由してやってきて、縄文人と混血して弥生人になったと考えた。
その後の調査で、前述のように中国山東省の遺跡から発掘された人骨との類似も指摘されている。
また、埴原和郎は、アジア南部に由来する縄文人の住む日本列島へ中国東北部にいたツングース系の人々が流入したことにより弥生文化が形成されたとの「二重構造モデル」を1991年に提唱した。
埴原は、人口学の推計によれば弥生時代から古墳時代にかけて、一般の農耕社会の人口増加率では説明できない急激な人口増加が起きていることから、
この間、100万人規模の渡来人の流入があったはずだとする大量渡来説も提唱していた。
佐原真は福岡平野・佐賀平野などの北九州一帯で、縄文人が渡来人と混血した結果、弥生文化を形成して東に進み、
混血して名古屋と丹後半島とを結ぶ線まで進み、水稲耕作が定着したとしている。
混血が起きた地域を西日本と限定すると、東日本では鈴木尚の説のように在来の縄文人が弥生人化したと理解している。
また、丸橋賢は、弥生人の形質は生来的に退化し易い形質で、「食生活の向上」による咀嚼の減少が咀嚼力の退化に繋がり、それが結果的に日本人の生命力自体の退化に繋がったとしている。
そもそも弥生人は単一民族ではなく複数の系統が存在するという見方もある。
●中国との通交
中国との通交は渡来系弥生人に遡ることができる。近年、DNAの研究が進み、渡来系弥生人の多くは中国大陸の長江流域、江南地方から来たと言われている。
更に遡ると現在の中国・青海省付近にまで遡ることができるという調査結果がある。稲作については、弥生米のDNA(SSR多型)分析によって、
朝鮮半島には存在しない水稲の品種が確認されており、朝鮮半島経由のルートとは異なる、中国中南部から直接渡来したルートが提唱されている。
また近年、渡来系弥生人のDNAと酒に弱い人の遺伝子の関連性が調査されている。
弥生時代の開始について、かつては中国・春秋戦国時代の混乱と関連づける考えがあったが、
弥生時代の開始年代を繰り上げる説に関連し、これを否定するか、或は殷から周への政変に関連づける考えが検討されるようになった。
中国の史書では、後漢の『論衡』が周代の倭に関する知識を伝え、ついで漢書が前漢代のこととして倭人が多数の国に分かれて住んでおり、使節を送ってくると記している。
『後漢書』(南北朝時代、432年成立)には、57年に倭奴国王が後漢光武帝から金印を授かり、また107年には倭国王帥升(または倭面土国王帥升)が生口を後漢へ献じたことが見える。
三国志の『魏志倭人伝』には、3世紀の倭国の状況が詳しく記されており、邪馬台国の卑弥呼女王が統治していたことなどを伝えている。
中国の三国時代の呉と倭国が公的に交渉を行った文献は全くないが、遺物として呉の年号を記す画文帯神獣鏡が二面存在する。
▪ 山梨県西八代郡市川三郷町大塚の鳥居原塚古墳出土の赤烏(せきう)元年(238年)の紀年銘をもつ。
▪ 兵庫県宝塚市安倉古墳(あくらこふん)出土の赤烏七年(244年)の紀年銘をもつ。
●弥生人の食糧
◇ 水田農耕
弥生水田の収穫量はどのくらいであったのか。弥生時代前期が下田・下々田、中期は下田・下々田、後期(登呂)は中田・下田注1であり、収穫量は多いとは言えない。
一日当たりのコメの摂取量は先進地帯でも前期は1勺程度、中期でも6勺~1合程度、後期でも2合を超えることはなかった。
でんぷん質不足量をドングリなどの堅果類で補っていた。その他オオムギ、ヒエ、キビ、アワ、ソバなど雑穀類の栽培やアズキ、大豆なども栽培していた。
注1:奈良時代の水田の100㎡当たりの収穫量は、上田50束・8斗4升6合・玄米105.7㎏、中田40束・6斗7升7合・玄米84.63㎏、下田30束・5斗8合・玄米63.5㎏、下々田15束・2斗5升4合・玄米31.75㎏
沢田吾一『奈良朝時代民政経済の数的研究』冨山房
◇ 狩 猟
弥生時代の狩猟の様子は、遺跡から見つかる狩猟道具や銅鐸などに描かれた絵画によって知ることができる。
出土品の中で狩猟道具となるものは石や骨、金属で作られた鏃であり、矢を発射するための弓も知られている。
弥生人が描いた狩猟風景でも弓矢が使われていたことが分かる。それらの多くはシカを捕えようとしているものである。
鳥取県青谷上寺地遺跡からもシカの骨が多数見つかっている。また近畿地方に多い絵画を描いた土器の画題をみると、シカが断然多い。弥生人にとってシカは身近な存在だったのではないだろうか。
ところが、実際に弥生時代の遺跡から見つかる動物の骨を調べると、一番多いのはイノシシである。弥生時代にはすでにイノシシを飼育していた考えもある。
弥生人の食料対象はイノシシで、シカは各種の儀式に関わる特別な存在であったようである。青谷上寺地遺跡ではイノシシの肩の骨に石で作られた鏃が刺さっていたものがあった。
鏃は刺さったときの衝撃で折れており、弓矢の威力を改めてしることができる。
◇ 家畜利用
弥生時代に水田農耕が行われるが、中国大陸における農耕がブタやウマ、ウシなど家畜利用を伴うものであったのに対し、
日本列島では長らく家畜の存在が見られなかったため「欠畜農耕」であると理解されていた。
これに対し、1988年・1989年に大分県大分市の下郡桑苗遺跡で関係のイノシシ頭蓋骨3点、ブタ頭蓋骨が出土した。
イノシシ類頭蓋骨に関して、西本豊弘が形質的特徴からこれを家畜化されたブタであると判断し、以来弥生ブタの出土事例が相次いだ。
また、1992年には愛知県の朝日遺跡で出土したニワトリの中足骨が出土している。
弥生ブタの系統に関しては、縄文時代からイノシシの飼養が行われていたが、イノシシからブタに至る過渡的な個体の出土事例がなく、
また、日本列島では島嶼化によりイノシシ個体のサイズに大小があるのに対し、弥生ブタは、この地域差からかけ離れた個体サイズであるため、弥生ブタは大陸から持ち込まれたと考えられる。
弥生ブタの系統の検討には、ミトコンドリアDNA分析を用いた分析が行われている。2000年の小澤智生による分析では12点の試料のうち11点が二ホンイノシシと判定された。
2003年の石黒直隆らが小澤とは異なる手法を用いて分析を行い、10点の試料のうち6点は現生二ホンイノシシと同一グループ、
4点は東アジア系家畜ブタと同一グループに含まれるとし、両者で異なる結果が出た。
なお、石黒らは後者のグループが西日本西部の一部地域に限られて分布している点を指摘している。
また、縄文時代に狩猟に用いたイヌに関して、大陸から食用家畜としてイヌが導入されたものという。
◇ 漁 労
縄文時代の関東地方では東京湾などで大規模な貝塚が形成され、クロダイ・スズキ漁を中心とする縄文型内湾漁労が行われていた。
関東地方では縄文晩期に貝塚数が減少し、弥生前期には縄文型貝塚が消滅するに至る。一方、三浦半島など外洋沿岸地域では引き続き外洋漁労が行われている。
外洋漁労の痕跡を残す洞穴遺跡では外洋沿岸岩礁のアワビやサザエ、外洋性回遊魚のカツオ、サメ、外洋沿岸魚のマダイが出土している。
アワビは縄文時代において出土事例が少なく、弥生時代には潜水漁が行われていたとも考えられる。
遺物では漁具として釣針、銛(もり)、ヤスなどが出土しており、特に縄文後期に東北地方太平洋沿岸で特徴的に見られる回転式銛頭が出土している点が注目される。
弥生中期には全国的に内湾干潟の貝類であるハマグリ・イボキサゴを主体とする貝塚の形成が行われるが、小規模で数も少ない。
漁労においても大陸から渡来した管状土錘を使用した網漁が行われ、網漁は後に増加・多様化し、瀬戸内海で特に発達した。また、内湾型の漁労としてイイダコの蛸壺漁も行われている。
こうした縄文以来の漁労活動が継続した関東においても弥生中期には稲作農耕社会が成立する。稲作農耕と漁労の関係を示す遺跡として神奈川県逗子市の池子遺跡がある。
池子遺跡は弥生中期の集落遺跡で、稲作農耕と外洋漁労の痕跡を示す貝塚が共に見られる。
池子遺跡では銛漁やカツオの釣漁、網漁が行われていたと考えられており、カツオなど農繁期と重なる夏場に漁期を持つ魚漁が見られることや、
専門性の高い銛漁・釣漁が行われていることから、農耕民とは別に漁業を専門とする技術集団がいたと考えられている。
▽ 淡水漁労の開始
弥生時代には稲作農耕の開始により、水田や用水路など新たな淡水環境が生まれたことで、淡水産魚類・貝塚を対象とした漁労も行われる。
愛知県清須市の朝日遺跡は大規模な貝塚を伴う漁労と稲作農耕を兼ねた集落遺跡で、内湾漁労の他タニシ、コイ科、ブナ、ナマズ、ドジョウを対象とした淡水漁労も行われている。
淡水魚漁の成立に伴い専用の漁具も生まれ、大阪市八尾市の山賀遺跡や静岡県春日市の辻畑遺跡では淡水魚を捕獲する筌(うけ)と考えられている漁具が出土している。
▽ 各地の漁労活動
北海道では稲作農耕が需要されなかったため縄文型漁労が継続し、海獣漁や寒流性の魚類を対象とした狩猟・漁労が行われた。
九州北部では縄文時代に外洋漁業が発達し、西北九州型結合式釣針と呼ばれる独自の釣針が生まれた。
この釣針の分布は縄文時代には北部九州に留まっているが、弥生時代には山陰地方へ普及している。
関西地方では大阪湾岸の宮ノ下貝塚など縄文型の貝塚が継続した事例が見られ、縄文晩期から弥生中期に至るまで継続して貝塚が営まれている。
|

 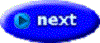 
|