 


15 弥生時代の人々(3)
◇ 戦乱の時代(環濠集落と高地性集落)
弥生時代は集落・地域間の戦争が頻発した時代であった。集落の周りには濠を巡らせた環濠集落や、
低地から100㍍以上の比高差を持つ山頂部に集落を構える高地性集落などは、集落や小国家間の争いがあったことの証拠であり、
また武器の傷を受けた痕跡のある人骨(受傷人骨)の存在なども、戦乱の裏付けであるといわれる。一方、これに対する反論も存在する。
北部九州から伊勢湾沿岸までには、環濠集落・高地性集落、矢尻の発達、殺傷人骨、武器の破損と修繕などの戦争に関わる可能性のある考古学事実が数多くそろっており、戦争が多かったと推定される。
南九州・東海・南関東・長野・北陸・新潟は、戦争があったと考えられる考古学的事実の数が比較的少ない。
北関東と東北には戦争があった可能性を示す考古学的事実はほとんどない。遠江、静岡県浜松市には環濠集落はあるが、
登呂などの静岡市周辺の大規模な弥生ムラには環濠はなく、戦争があった可能性は薄い。
神奈川県逗子市周辺は農耕的性格を示していながらも食料採集にも大きく依存していたことを示しており、戦争はなかったと考えられる。
環濠集落の北限は、太平洋側では千葉県佐倉市の弥生ムラ、日本海側では新潟県新八幡山である。
ただ、秋田市地蔵田B弥生ムラが4軒の家を柵で囲んでおり、これを入れるとすると日本海側の防御集落の北限がさらに北上する。
戦争による緊張感は、日本海側の方が北まで広がっていたと考えられる。しかし、北関東と東北地方の広い範囲は、
コメの生産高が低かったからこそ戦争とは無関係であったのであろうと推測する説もある。
弥生時代前期の墓には、人骨の胸から腰にかけての位置から15本の石鏃が出土した例がある。
このように多くの石鏃が胸部付近に集中して見つかる墓の事例は、瀬戸内海を中心とする西日本一帯に比較的多く見られる。
以前には、こうした例は戦闘の際に矢を何本も射込まれて、やっと倒れた人物と解釈されることが多く、「英雄」などと呼ばれた。
近年では、矢を特定の部位に集中して射込まれていることの不自然さから、刑罰として処刑されたとか、
何らかの儀礼的行為の際の犠牲(生贄)となって胸に矢を射込まれたなどといった解釈もある。
平和的な解釈としては、埋葬の際に副葬品として鏃を胸のあたりに埋納したと考える者もいる。
北部九州では、前期から中期にかけて銅剣・銅戈・石剣・石戈の切っ先が棺内から出土することが多い。
こうした例は、武器を人体に刺突した際に先端が折れて体内に残ったものと解釈されている。
しかし、武器の先端を折り取って副葬品として棺内に埋納するという風習があったのではないかと云った反論をする者もいる。
佐賀県吉野ヶ里遺跡や福岡県筑紫野隈・西小田遺跡などでは、中期前葉の男性甕棺数が女性の倍にも達する事実があり、男性が戦闘に参加する機会が多いことを示すと考えられる。
甕棺内に頭部を切断された胴体だけが埋葬されていたと考えられる事例が見つかっており、戦闘の際に敵に首を切られた死体を持ち帰り、埋葬したものと理解されている。
戦争やテロの時に敵の首を取る慣習は、戦国時代や幕末でも続いていたが、その始まりは弥生時代にあった。
しかし、このような例が本当に戦闘の犠牲者なのかは論証されておらず、何らかの儀礼的行為によるものと主張する者もいるが、いまだ論証されていない。
受傷人骨の中でも、明らかに武器によってつけられたと考えられる傷のある人骨の存在は、戦闘の存在を示す証拠である。
例えば額から右眼にかけて致命的な傷痕があり、更に右手首を骨折していた人骨が見つかっているが、
右手首の骨折は、攻撃から身を守る際につけられる、防禦創と呼ばれる種類の傷としては一般的なもので、戦闘による受傷者である可能性が極めて高い。
また人骨に武器の切っ先が嵌入している事例も、北部九州を中心に数例が確認されているが、これらは武器による受傷人骨であることが明らかである。
このような受傷人骨の例は縄文時代にもないわけではないが、弥生時代には前代と比べて明らかに数が増加しており、縄文時代と比べて戦争が頻繁に起こった事は確実といえる。
また、戦闘の証拠とされる前記のような事例のうち、武器の切っ先が棺内から出土する例、頭部がない人骨、或は人骨に残る受傷例などは、
前期後半から中期前半の北部九州地域、特に福岡県小郡市を中心とした地域に多く認められることが特徴的である。
弥生前期後半から中期前半は、西日本の多くの地域で集落が可耕地に乏しい丘陵上へと一斉に進出することが指摘されており、
各地域において弥生集団が急激な人口の増加を背景に可耕地の拡大を求めた時期であるとされる。
この可耕地の拡大が原因となって、各地で土地と水に絡む戦いが頻発したものと考えられ、中でも北部九州における受傷人骨の多さは、
こうした争いが頻発した証拠と考えられている。なお、中期後半以降は受傷人骨や切先が棺内から出土する例は減少する。
環濠集落は、このような集団同士の争いに備えた防禦集落であったと考えられている。但し、環濠集落の出現は、未だ戦闘の証拠がほとんどない弥生時代早期に遡ること(福岡県江辻遺跡、同那珂遺跡群など)、
受傷人骨などの事例から戦乱が頻発したと考えられる前期後半-中期前半、特に中期初頭以降の北部九州ではむしろ環濠集落の事例は少ないこと、
しばしば環濠を掘削する際に排出された土を利用して環濠の外側を盛り土をした痕跡のある事例が報告されているが、
環濠の外側に盛り土をすることによって外敵を有利にしてしまう(盛り土を矢避けにしたり盛り土の上から攻撃できる)ことなどから、
環濠集落と戦乱とを直接的に関連づける、すなわち環濠集落を防衛集落と考えるのではなく、
環濠を掘削するという大規模な土木作業を共同で行うことによって共同体の結束を高めることが目的であった、
又は環濠によって集団を囲い込むことによって集団意識を高めることが目的であったとする議論も提出されている。
しかし弥生時代後期の高地性集落にしばしば環濠が掘削されていること、環濠内に逆茂木(さかもぎ)と呼ばれる防禦施設が設置された事例が認められること(愛知県朝日遺跡など)などから、
環濠自体に防御的な機能を持たせた事例が多いこともまた明らかである。環濠の性格については地域・時期によって異なる意味づけを持たさせるべきではないかといった主張がある。
一方、やはり古くから防衛集落と目されてきた集落の類型として、高地性集落が挙げられる。
高地性集落は、弥生時代中期後半-末(Ⅳ期後半-末)、そして後期中葉-末(Ⅴ期中葉-末)に瀬戸内沿岸から大阪湾にかけて頻繁に見られるもので、
弥生時代の一般的な集落からみて遥かに高い場所(平地からの比高差が50~300㍍以上)に営まれている集落のことである。
北部九州から北陸・中部・東海地域などといった広い範囲に分布する。1970年代までは、畿内Ⅳ期がおおよそ北部九州の後期前半、
畿内Ⅴ期が後期後半に併行するとされ、実年代では紀元50年-250年ごろに比定されていた。
史書にある、いわゆる倭国大乱は、各種の史書に記載された年代が凡そ2世紀後半-末にあたり、当時の年代観では凡そ畿内Ⅳ期末-Ⅴ期前半期に該当していた。
このため、高地性集落の盛行は倭国大乱を原因とするものだという理解が主流であった。畿内と九州の年代の併行関係が是正されると、倭国大乱は畿内Ⅴ期後半-末に該当する。
畿内Ⅳ期の高地性集落とは時代的に整合的でないとされ、これらは倭国大乱とは無関係とする意見が主流を占めるようになった。
畿内Ⅳ期の高地性集落については、この時期に史書には記載されない戦乱があったという主張が多いが、背景に戦乱を想定する必要はないという意見も見られる。
後者の場合、見晴らしがよい立地に住むことで、海上交通の見張り役となっていたとか、畑作を主とする生活をしていた集団であって水田耕作に有利な低地に住む必要がなかったなどといった様々な議論が行われている。
一方、後期後半期の近畿の高地性集落(大阪府和泉市観音寺山遺跡、同高槻市古曾部遺跡などは環濠を巡らす山城)については、
その盛行期が、前述の理由から北部九州・畿内とも凡そ史書に記載された倭国大乱の年代とほぼ一致することから、これらを倭国大乱と関連させる理解が主流を占めている。
大規模な集団殺戮を示す遺跡としては、鳥取県の青谷上寺地(あおやかみじち)遺跡が代表例である。
日置川と勝部川の合流点の南側に弥生中期から村が形成され、弥生後期後葉に戦争の結果とみられる状況で集落が廃絶したと思われる(住居跡は未発掘)。
東側の溝(防禦施設と港の機能を兼ねていたか)から100人分を超える人骨が見つかり、少なくとも10体、110点の人骨に殺傷痕が見られた。
人骨は女性や老人、幼児も含めて無差別に殺されており、刀剣による切り傷が付いた骨、青銅の鏃が突き刺さった骨がある。
治癒痕はなく、骨に至る傷が致命傷となってほぼ即死したと思われる。出土状況も凄惨で、溝に多数の死体が埋葬ではなく折り重なって遺棄されている
遺物も原型を保った建築物の一部や、様々な生活用品が通常の遺跡ではあり得ないほど大量に出土している。
死者の中に15~18歳の若い成人女性がおり、額に武器を打ち込まれて殺されている。殺戮した後、死体の処理と施設の破壊を兼ねて、死体や廃棄物で溝を埋め立てたものと思われる。
略奪はしただろうが、破壊した住居や不要な生活用品は捨てられた。通常なら再利用や腐朽で失われるものが、保存条件もよくて大量に残存した。虐殺以後は集落は復興せず、現代まで水田として利用された模様である。
◇ 倭国大乱
魏志倭人伝には、卑弥呼が邪馬台国を治める以前は、諸国が対立し互いに攻め合っていたという記述がある。
また、後漢書東夷伝には、桓帝・霊帝の治世の間、倭国が大いに乱れたという記述がある(倭国大乱)。
近年、畿内の弥生時代Ⅳ・Ⅴ期の年代観の訂正により、これらは凡そ弥生時代後期後半-末(Ⅴ期後半-Ⅵ期)に併行するという考えが主流になった。
この時期には、畿内を中心として北部九州から瀬戸内、或は山陰から北陸、東海地域以東にまで高地性集落が見られること、
環濠集落が多くみられることなどから、これらを倭国大乱の証拠であるとする考え方が有力となっている。
ところが、前代に比べて武器の発達が見られず、特に近接武器が副葬品以外ではほとんど認められないこと、
受傷人骨の少なさなどから、具体的な戦闘が頻発していた主張する研究者はあまり多くない。倭国大乱がどのような争いであったのかは未だ具体的に解明されていないのが現状である。
邪馬台国畿内説では、北部九州勢力が大和へと移動したことを示す物的証拠は考古学的にはほとんど認められないとしており、
近年ではむしろ北部九州勢力が中心となって、鉄などの資源の入手や大陸からの舶載品などを全国に流通させていた物流システムを畿内勢力が再編成し直そうとして起こった戦いであったという。
一方、邪馬台国九州説では、弥生時代後期中葉以降に至っても瀬戸内地域では鉄器の出土量は北部九州と比べて明らかに少なく、また、鉄器製作技術は北部九州と比べて格段に低かった。
倭国大乱の原因については、古事記、日本書紀等の神武天皇東征の記述と結び付け、北部九州勢力が大和へと移動してヤマト朝廷を建てたとする。
◇ 地域勢力と大型墳丘墓の出現
時代が下るにつれ、大型集落が小型集落を従え、集落内で首長層が力を持ってきたと考えられている。
首長層は墳丘墓に葬られるようになった。このことは身分差の出現を意味する。弥生時代後期になると墓制の地域差が顕著になっていく。
近畿周辺では方形低墳丘墓がつくられ、山陰(出雲)から北陸にかけては四隅突出墳丘墓が、瀬戸内地方では大型墳丘墓がそれぞれ営まれた。
▽ 吉備地域
瀬戸内地方の中でも吉備と呼ばれる岡山県と広島県東部の地域では、弥生時代後期の最大級の墳丘墓は、岡山県倉敷市の楯築墳丘墓(最大長約80㍍)である。
この地域では首長の葬送儀礼には、特殊器台形土器と特殊壺形土器が数多く使用された。これらの土器は、吉備地方で発生後、美作・備前・備中・備後の地域に分布する。
その発達の中心は、備中南部の平野であった。そして、これらの地域の周辺地域では使用されていないのが特徴である。
▽ 山陰地域
中国山地の三次で発生したと推定され、出雲地域で発達した四隅突出型の墳丘墓(大きなものは約45㍍×約35㍍)が現れる。
これらは後の古墳時代に匹敵する土木建築を駆使したもので、その分布は山陰の出雲地方や北陸の能登半島にまで拡がっている。
出雲地域に存在する安来・西谷の両墳丘墓集積地には台形土器と壺形土器。出雲と吉備の両地域に同盟関係が生まれていたことを示していると考えられている。
これらの墓の特徴が寄り集まって後代の古墳(前方後円墳など)の形成につながったとされている。
弥生時代の地域勢力は、北部九州・吉備・山陰・近畿・三遠(東海)・関東の勢力に大別することができる。
時代の進行とともに連合していき、一つの勢力が出来ていった、と考えられる。水田農耕発展のために農地の拡大と農具となる鉄の獲得のため、
また地域間の交易をめぐる争いのために戦いが起こり時代が進行していった。近畿では、環濠集落は弥生前期末に現れ、中期以降に普及した。
|

 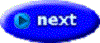 
|