 


10 弥生時代(1)
●弥生時代
北海道、沖縄を除く日本列島における時代区分の一つで、紀元前11世紀から紀元後3世紀中頃までに当たる時代である。
弥生時代は、水稲耕作による稲作の技術をもつ集団が列島外から北部九州に移住することによって始まったとされる。
●時期区分
弥生時代の始まりを、いつの時点とすべきかは諸説ある。元々弥生時代は、弥生式土器が使われている時代という意味であった。
ところが、弥生式土器にはコメ、或は水稲農耕技術を伴うことが明らかになってくると、弥生時代は水稲農耕による食糧生産に基礎を置く農耕社会であって、
縄文時代(狩猟採集社会)とは、この点で区別されるべきだとする考え方が主流になっていった。
そのような中、福岡市板付遺跡で、夜臼(ゆうす)式土器段階の水田遺構が発見され、従来縄文時代晩期後半と考えられていた夜臼式土器期に、
すでに水稲農耕技術が採用されており、この段階を農耕社会としてよいという考えが提起された。
その後、縄文時代と弥生時代の差を何に求めるべきかという本質的な論争が研究者の間で展開され、
集落の形態、水田の有無、土器・石器など物質文化の変化など様々な指標が提案された。
現在では凡そ、水稲農耕技術を安定的に受容した段階以降を弥生時代とする考えが定着している。
近年では弥生時代の時期区分は、早期・前期・中期・後期の4区分論が主流になりつつある。また、北部九州以外の地域では(先Ⅰ-)Ⅰ-Ⅴの5(6)期に分ける方法もある。
(早期は先Ⅰ期)前期はⅠ期、中期はⅡ-Ⅳ期、後期はⅤ期にそれぞれ対応する。これまで(早期は紀元前5世紀半ば頃から)
前期は紀元前3世紀頃から、中期は紀元前1世紀頃から、後期は1世紀半ば頃から3世紀半ば頃までと考えられていた。
しかし2003年、国立歴史民俗博物館の研究グループが、炭素同位対比を使った年代測定法を活用した一連の研究成果により、弥生時代の開始期を大幅に繰り上げるべきだとする説を提示した。
これによると、早期の始まりは約600年遡り紀元前1000年頃から、前期の始まりは約500年遡り紀元前800年頃から、
中期の始まりは約200年遡り紀元前400年頃から、後期の始まりは紀元50年頃からとなり、古墳時代への移行はほぼ従来通り3世紀中頃となる。
|

 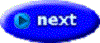 
|