 


6 人類と石器文化の発達・変遷
● 前期旧石器時代(約200万年前~約10万年前)
▽猿人…アウストラロピテクス
原始的な礫石器、骨角器を使用
▽原人…核石器(握斧)、剥片石器を使用
ホモ・エレクトスの一種、北京原人、ジャワ原人など
猿人は最も原始的な礫石器を骨角器とともに使った。原人は石を欠いて、その芯の部分を使った核石器(握斧)、石材から剥ぎ取った剥片を使った剥片石器を作り、様々な用途に利用した。
● 中期旧石器時代(約10万年前~約3万5千年前)
▽旧人…ホモ・ネアンデルターレンシス
細石器、小型石器(鏃)を使用
ネアンデルタール人など
旧人は石器をより巧みに複雑に軽量化し、狩猟など生活技術を進歩させた。この時代の食生活は極めて不安定で、
多くは野生植物の採集、狩猟、漁労に依存する生活であった。度々厳しい寒さや飢えに脅かされたと考えられる。
● 後期旧石器時代(約3万5千年前~約1万5千年前)
=第4氷河期末期(3万数千~1万4千年前)
▽新人…ホモ・サピエンス
小型の石刃、精巧な骨角器、優れた洞窟芸術
クロマニオン人、グリマルディ人、山頂洞人、浜北人、
港川人など
新人が活躍した第4氷河期の末期、前代よりずっと華々しい文化期で、各種の目的に利用できる小型の石刃や精巧な骨角器を盛んに作って、狩猟や漁労、その他日常生活に活用し、知能が著しく進んだことを示している。
特に洞窟内の天井や壁に描き残した動物の着色絵画や彫刻は、優れた洞窟芸術として有名である。
● 後期旧石器時代晩期・縄文時代草創期(約1万5千年前~約1万2千年前)
▽新人…磨製石器、土器製作
◇約1万6千5百年前…無文土器出現…最古の土器、紋様がない。
細石刃を列島にもたらした民族がサハリン経由で
土器作り伝える。
◇約1万2千年前…豆粒文形式土器出現…朝鮮半島経由で長崎に伝わ
る。
日本の歴史上、最初の変革期…縄文時代の幕開け、縄文時代草創期。以後、縄文時代は1万年余り続く。
7 日本民族の形成
1)中期旧石器時代(約10万年前~約3万5千年前)
● 約12万2千年前…砂原遺跡(出雲市多伎町砂原)…旧石器出土
石英斑岩製の石核、玉髄製剥片など出土
●約9万~8万年前…金取遺跡(岩手県遠野市)…旧石器出土
硬質砂岩・粘板岩製の両面加工石器など
●約7万~5万年前…西アジアから来た古モンゴロイド系人が東アジアへ
移動、中国北部に達した北東アジア人…石刃技法を
開発。
●約5万年前~約3万年前…竹佐中原遺跡(長野県飯田市)…旧石器出土
●約4万8千年前~約3万3千年前…長野県・野尻湖底・立ヶ鼻遺跡。
ナウマンゾウの臼歯発見、その他獣骨大量出土。
道具類(皮剥ぎ用石器、ナイフ形石器、骨製ナイフなど)
出土。
旧人或は新人の狩猟民が大型食用動物を追ってきた。
2)後期旧石器時代(約3万5千年前~約1万5千年前)
● 約2万年前…岩手県・花泉遺跡…大量の獣骨化石発見
ナウマンゾウは約35万年前から約1万7千年前まで生息していたアジア象である。
この頃、日本列島へ旧人或は新人の狩猟民がナウマンゾウやオオツノジカなど大型食用動物を追って樺太経由で北海道、東北地方へやって来たものであろう。
しかし、彼らを縄文人或は日本人の祖先とするには、やや無理があるようだ。それは野尻湖人も花泉人も時代的に、かなりのずれがあり、列島的な広がりが認められないからである。
●アフリカ単一起源説による人類の足跡
この説によれば、日本民族の歴史スタートは、新人が日本列島に到来した後期旧石器時代(約3万5千年前~約1万5千年前)以降となる。
日本列島の旧石器時代=無土器時代、先土器時代と呼んでいる。後期旧石器時代の遺跡…国内で約5千ヵ所発見。
(1) ナイフ形石器文化圏形成(約3万2千年前~約1万3千年前)
日本へ渡来した二つの民族集団…ナイフ形石器人=最初の日本人か。東西文化の違いが発生。
二つの民族集団は、いずれも古モンゴロイドの形質を持ち、一見さほど差異はなかったが、この二つの集団が数万年ぶりに日本列島で再会した。
この頃、石刃石器(石刃技法を使った石器)が出現した。この技法は原石に適当な加工を施して石核を作り、
その石核から石刃と呼ぶ縦長の剥片を連続的に剥ぎ取っていく、大変優れた画期的な石器製造技術である。
約2万年前以降、石刃技術は進歩し、ナイフ形石器時代を形成、多様で精巧な美しい石器が大量に製造・使用された。
a)バイカル湖周辺から渡来した民族…東日本の祖先
中国北部にたどり着いた古モンゴロイド系の集団から、更に遠くアメ
リカ大陸など北部を目指した集団の中で豊富な食料資源をもつバイ
カル湖 地域に落ち着いた集団を先祖とする。
◇3万年前~2万7千年前…大型哺乳動物が南下、これを追って南下
進入した民族
◇2万年前…シベリア直系の細石刃文化を伝えた民族
…東の「杉久保・東山型注1ナイフ形石器文化圏」形成
注1:杉久保・東山型…新潟から山形中心に分布する「杉久保型」、東北中心に分布する「東山型」がある。
b)華北・黄河付近から断続的に渡来した民族…西日本の祖先
新人が西アジアからヒマラヤの北側を通って中国北部にたどり着いた
集団、すなわち最初期の北方古モンゴロイド系を先祖とする。
◇3万~1万2千年前…中国北部から朝鮮半島経由で断続的に流入
◇2万年前…集団が渡来、西日本各地に住み着き、ナイフ形石器
文化をもたらす。
…西の「茂呂・国府型注2ナイフ形石器文化圏」形成
注2:茂呂・国府型…近畿・中国を中心に分布する「国府型」、関東・東海を中心に分布する「茂呂型」がある。
(2) 細石刃文化の形成(約1万3千年前~1万2千500年前頃)➡縄文時代草創期
a)バイカル湖文化系の東日本人…北海道を含む日本列島の東地区
◇バイカル湖付近から北東アジア人が樺太経由で北海道、東日本に
流入、特殊な彫器(荒屋型)を持った細石刃文化
…楔(くさび)形細石刃石器群(荒屋型彫器注1を含む)の到来。
以後、東日本のナイフ形石器文化は消滅する。
注1:荒屋型彫器…荒屋遺跡(新潟県)から出土した彫器。同種のものが北海道、東日本に広く分布する。
b)華北・黄河文化系の西日本人…九州、四国を含む日本列島の西地区
◇半円錐形細石核を使用する細石刃文化の出現
◇この時期を境に東日本と西日本に大きな人口差異が発生。
◇華北系細石刃石器群文化…九州地方に東日本とは異なる楔形
細石核文化(荒屋型彫器を含まない)の出現。
(3) 華北(福井)型細石刃文化の形成(約1万2千700年前~約1万2千400年前)
後期旧石器時代の後半期、長崎県佐世保市、福井川右岸の洞穴から福井(洞穴)型細石核や細石刃が大量に出土すると共に、爪形文土器、隆線文土器の破片が発見された。
この時期、西日本地区の楔形細石刃石器群文化(荒屋型彫器含まない)は、福井型細石刃文化に代わる。
(4) 神子柴(みこしば)型石器文化の形成(~約1万2千年前)
長野県上伊那郡南箕輪村の神子柴遺跡から優美な形や精巧な技術を持った石器群が発掘された。
この石器群は特有な局部磨製石斧をはじめ、神子柴型尖頭器、掻器、彫器などの組み合わせを持っていた。
この神子柴文化は、北海道から本州東北部に集中しており、細石刃文化に続く時期に、北方から東日本地区に南下してきたものらしい。
後期旧石器時代の末期に、バイカル湖系の細石刃文化とは別の文化が渡来していたことになる。
(5) 有舌(茎)尖頭器文化の形成(~約1万2千年前)
福井洞穴から出土した隆線文土器は、日本列島から東方へ遡るように伝播した。愛媛県美川村・上黒岩岩陰遺跡からも隆線文土器が出土したが、
ここでは細石刃は全く伴わなかった。共伴したのは基部が舌状のでっぱりのある有舌尖頭器であった。
ここに土器が伝わった時は、すでに細石刃文化は去り、有舌(茎)尖頭器の時代になっていた。
その後も隆線文土器と有舌(茎)尖頭器はセットになって、東へ東へと伝播していった。
● 後期旧石器時代晩期(約1万5千年前~約1万2千年前)➡縄文時代草創期
▽ 縄文時代草創期(約1万6千5百年前)…青森県・大平山元Ⅰ遺跡から無紋
土器を発見
…最古の土器か、紋様がない。
細石刃をもたらした民族がサハリン経由で土器作りを伝えたと考えられる。
▽ 縄文時代草創期(約1万2千年前)…豆粒文形式土器
…長崎県佐世保市「泉福寺洞穴」から出土。
…朝鮮半島経由で伝播したと考えられる。
▽ 縄文時代草創期(約1万2千年前)…有茎尖頭器と隆線文土器が卓越
…神奈川県大和市・月見野上野遺跡で出土。
隆線文土器が初期土器文化の全国スタンダートになり、縄文時代幕開け
3)日本列島における後期旧石器人
(1) 後期旧石器群の変遷
ア) 前半期(約3万5千年前~約2万9千年前)
a) 前半期前葉(約3万5千年前~約3万3千年前)
台形様石器(又は台形石器)、局部磨製石器…列島に広く分布
ナイフ形石器(縦に長い剥片を加工、尖らせた石槍石器)…東日本中心
b) 前半期後葉(~約2万9千年前)
石刃技法が確立…石槍の発達が顕著…東日本中心
横長剥片剥離技術の発達…近畿・瀬戸内地方中心
イ) 後半期(約2万9千年前~約1万5千年前)
a) 後半期前葉(約2万9千年前~約1万7千年前)
ナイフ形石器を盛んに制作
b) 後半期後葉(約1万7千年前~約1万5千年前)
細石刃を盛んに制作
ただし、北海道は樺太、沿海州と陸続きであったので細石刃を含
む石器群が約2万3千年前には製作・使用されていた。
後半期(約2万9千年前~約1万5千年前)は、ほぼ最初から地域性が確立し、北海道を除き、東北、関東、中部、近畿、瀬戸内、九州などと区分できる。
それぞれの地域で石器の様式性が著しく発達し、東北の「東山型」、新潟から山形の「杉久保型」、
近畿の「国府型」などの各種「ナイフ形石器」や瀬戸内から九州の「角錐状石器」、九州の「剥片尖頭器」、「台形石器」などと呼称される。
いずれも槍ないしナイフとして使用されたと推定される大型の石器に、その特徴が現れた。
これらの石器を製作するための材料である石材も、その地域ごとに異なる産地のものが利用される傾向が強かった。
楔型は中国東北部から当時、陸続きだった北海道を通じて東日本を中心に広がり、角錐状や船形は中国南部から直接九州に伝わってきたらしいことが明らかになったという。
こうした石器と石材の変化は、当時の人々の移動生活や生業活動の変化と関係している。
前半期(約3万5千年前~約2万9千年前)には、それまで広く分散していた滞在・居住場所が河川流域に集中するようになり、その数自体も急増したことから、人口が増加したのではないかと推定されている。
また、そうした移動・居住の変化を促す背景として、気候や動植物生態系の変化が関係していたとも考えられている。
2万9千年前を過ぎる頃から、地球規模で急激に寒冷化が進行し、約2万5千年前を前後する頃には最終氷期最寒冷期を迎えたからである。
後半期(約2万9千年前~約1万5千年前)の終末には、北海道に相当遅れて古本州島(陸続きになっていた本州・四国・九州と属島)にも細石刃石器群が展開する。
細石刃は、長さ3㌢以下、幅0.5㌢以下の小さくて薄い石器で、剃刀のような使い方をしたようだ。
細石刃のように小さく薄い石片を連続して剥がし取るには、事前に原石を剥離しやすい形に加工しておかなければならない。
日本列島では、この時期に楔形の石核にする方法と、円錐形の石核にする方法の2つの技法が用いられた。
楔形を使う湧別技法注1と呼ばれる北海道の技法は、1万8千年前頃、本州に伝わり、茨城・山形・新潟辺りまで広まった。
これより西は矢出川技法注2という円錐形の石核から細石刃を作り出す技法が主流となり、東日本と西日本地区の2地域色が出て大別される。
湧別技法は「荒屋型」といわれる特徴的な彫刻刀形石器(彫器ともいう)を伴うが、矢出川技法は彫刻刀形石器を伴わない。
「ナイフ形石器」と「細石刃」がほぼ列島全域に展開したのに対し、尖頭器石器群は東日本でも特に中部・関東地域において地域的な発展を見せる。
尖頭器は、魚の鱗のような小さな剥片を繰り返し剥がして整形し、木の葉形を呈する様に作り上げた石槍の先端部のことで、サイズは10㌢以下が多い。
中部・関東地域においては、ナイフ形石器群が小型化し、細石刃石器群が登場する頃までの、後半期後葉にこのような尖頭器が制作された。
注1:湧別技法…1961年、北海道湧別川の源流に近い白滝村の露頭で楔形の石核から細石刃を作り出す湧別技法という最高級の石器が確認された。
細石刃文化期の日本列島と周辺地域の関連を考える上で重要な指標となる技法である。ロシア極東からシベリアへと系統が辿れる北方系の細石刃石器群でもある。
注2:矢出川技法…1953年、細石器文化が初めて日本列島で確認されたのが長野県野辺山高原にある矢出川遺跡である。
細石刃文化は小さな細石刃を組合せて道具とした旧石器時代の石器文化であるが、不定形の柱状素材を細石刃石核原形として細石刃を剥離する技術、この技法は円錐形の石核から細石刃を作り出した。
その出自は明らかでないが、列島の南から広がっているようにであり、朝鮮半島や中国に系譜が追える。
(2) 住居と墓制
日本列島の旧石器時代の遺跡は、台地・段丘・丘陵・高原などの見晴らしの良い更新世の台地縁辺にあることが多い。
日常生活の場としての拠点遺跡、獲物の解体場遺跡、石器製作場遺跡などがある。定住住居跡の出土例が少ないことから
旧石器時代人は、一定の生活領域内を移動しながら狩猟採集生活をしていたと考えられている。
この時代の人々は多く洞穴や岩陰を住みかとして利用していたことが知られているが、そうした中にあって少ないながらも竪穴住居が見つかっている。
大阪府藤井寺市のはさみ山遺跡の住居である。住居は、約2万2千年前の木材を組み木にして草や皮で覆ったもので、形の整った径6㍍、深さ20㌢の円形竪穴住居である。
外周に柱穴をもつもので径10㌢くらいの材を20本近く、斜めに立て並べ、中央で簡単な組み木を施している。
この住居跡からは、構造がよく分かったうえにサヌカイト製のナイフ形石器や翼状剥片が約200点も一緒に出土している。
調理・暖房・採光のための石囲炉、地床炉、土坑炉などがあり、熱のため赤色化していたことで火が使われていたことが分かる。
土坑の形態は多様で、貯蔵穴かどうか分かっていない。礫群は、こぶし大前後の川原石が径12㍍の範囲に数十個以上密集したもので、
火熱を受けて赤色化しており、調理施設に関連したものと考えられている。1個から数個散らばっている配石は、
幼児頭大の礫で、火熱を受けた跡がなく、厨房や作業台に使ったものと考えられている。
(3) 土器の出現
日本で最初の土器が、どのようにして出現したのかははっきり分かっていない。ただ、世界でも最古級(約1万6千5百年前)の土器が青森県・大平山元遺跡から出土している。
旧石器時代の終末に、九州では豆粒文土器(長崎県・泉福寺洞窟)、本州では無文土器が出現している。
一般に土器は、運搬・貯蔵・煮炊きに使われているが、出現期の土器の役割はまだ十分解明されていない。
(4) 木の文化
石器時代の文化といえば、石器を思い浮かべるが、日本列島の豊かな森林資源を忘れてはならない。これまでに板状の木製品と木の柱を使った住居跡が見つかっている。
板状の木製品は、明石市西八木遺跡で約6~5万年前の砂礫層の中からハリグワという広葉樹を用いた板状の木製品(加工痕のある木片)が出土している。
この木片は長さ23.4㌢、最大幅4.8㌢、厚さ4㍉で、少なくとも2種類の石器で加工されている。用途はまだ分かっていない。
この砂礫層の年代の板だとすると、中期旧石器時代の板ということになり、旧人が工作した板ということになる。円形竪穴住居の木材の組み木使用は、前述の通りである。
竪穴住居が旧石器時代に遡っただけでなく、旧石器時代人が石器だけでなく木を使っていたことが分かってきた。
木に石器を取り付ければ、鍬・斧・槍・矢・スコップなどの生産用具を作り、生産効果を上げることができる。
(5) 食糧の獲得
旧石器時代人は、主として狩猟によって食糧を得ていた。当時の遺跡からは、野牛・原牛・ナウマンゾウなどの大型哺乳類の骨、ニホンシカ、イノシシ、ノウサギなどの中・小哺乳動物の骨が発見されている。
そして、大型哺乳動物を解体する作業場となるキル・サイトも発見されている。このように、旧石器時代人は、大型哺乳動物を追う狩猟民たちであったと思われる。
竪穴住居跡を伴う遺跡がほとんど発見されていないのは、旧石器時代人がキャンプ生活をしながら移動を繰り返していたからとも推定されている。
漁労の直接的な証拠は発見されていないが、そのような活動があっただろうと推測されている。伊豆諸島の黒曜石が南関東で出土しており、同諸島で細石刃が発見されている。
ここから、旧石器人も何らかの航海技術や海上交通の手段を持っていたことが想像できる。
さらに、日本の旧石器文化がシベリアとの強い関連性があることが分かっており、そのシベリアで固定式のヤスや離頭式の銛頭(もりがしら)が見つかっている。
日本は酸性土壌のため人骨や獣骨が残りにくいが、日本でも同様の道具を用いて刺突漁を行っていた可能性がある。
旧石器時代の人々は狩猟が主体であったようだ。当時は数百㎞にも及ぶ距離を移動していたというから、それは移動性のある動物の行動生態と関連しそうであるし、
また彼らの道具を見ると、植物質資源の加工・処理に有利で頑丈なタイプの石器(削器や石斧)よりも、
狩猟具に使えそうな先の尖った石器(有背石刃、尖頭器)や壊れやすいが鋭い刃(石刃、細石刃)のある石器というような道具が発達したからである。
(6) 人類化石
旧石器時代の遺跡に人骨・獣骨化石が残る例がほとんどない。こうした中でもこれまで更新世人類化石として知られていた例も多かった。
しかし、C14年代測定法などで再検討した結果、それらの多くが更新世人類化石の地位を失い、静岡県・浜北人と沖縄県・港川人だけが更新世人類とされた。
ア) 浜北人
静岡県浜松市浜北区根堅の石灰石採石場で、1960年から1962年に発見された頭骨片と四肢骨片の人骨化石である。
上下2つの層から出土した。AMS法(加速器質量分析)による炭素年代測定の結果、上層が約1万4千年前、下層出土の脛骨が約1万8千年前を示した。
イ)港川人
沖縄県島尻郡八重瀬町の港川採石場の石灰岩フィッシャーで1967年~1969年に人骨の断片が発見された。上部港川人骨と呼ばれている。年代は約1万2千年前と考えられる。
1970年に同じ港川採石場から数体の人骨化石が発見された。人骨は少なくとも5体を数え、男性2体を含み、約1万8千年前とされる。
顔は四角く、目は窪み、鼻はやや広く、立体的で頑丈であることなど現代日本人とは全く違っており、縄文人と似ているところが目立つ。
頭蓋は骨が厚く、前頭骨が小さく、脳頭蓋の下部が幅広いなど独自の特徴で原始的である。また、男性の推定身長は153~155㌢で、上半身は華奢であり、かなり小柄である。
後期更新世の沖縄港川人はアジア大陸の南方起源である可能性が高いが、北海道~九州地方の縄文時代人とは、
下顎形態に多数の相違点が見出され、両者の間の系譜的連続性を認める従来の仮説は見直される必要があるという主張もある。
ウ)山下町洞人
1968年に沖縄県那覇市山下町第1洞穴で発見された。約3万2千年前とされる6~7歳の子供の大腿骨と脛骨で、
国内では最古級の人骨である。最近の検討では、初期現代型新人の特徴に一致するという。
エ)石垣島・白保竿根田原洞窟の人骨
2010年、沖縄県石垣市白保(石垣島)の新石垣空港建設敷地内にある白保竿根田原洞穴で人骨が発見された。
そのうち1点、男性の頭頂骨を放射性炭素年代測定で約2万年前のものと分かった。発見された人骨片のうちの右頭頂骨片は、20416±113年前(BP)という推定年代値を得た。
これは放射性炭素によって直接ヒト化石の年代を推定した値としては国内最古のものであった。
オ)サキタリ洞人
沖縄県南城市サキタリ洞で発見された断片的な人骨は、約1万2千年前のものとされた。
同じ地層から発見された石英製の剥片石器や海産貝などは人為的に持ち込まれたものと考えられている。
|

 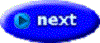 
|