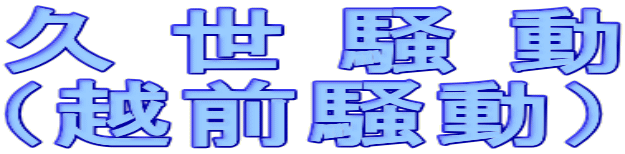
1 久世騒動とは、どんな騒動だったのか?
江戸時代のお家騒動といえば、伊達騒動、加賀騒動などが有名ですが、久世騒動(越前騒動)とは聞き慣れない事件でした。
どんな騒動だったのか調べてみると、越前藩(福井藩)の重臣同士が対立した大事件でした。
その発端が福井市北東部、森田地区の農民に起因していたので、尚更、興味を抱き調べてみました。
2 江戸初期の越前藩
豊臣秀吉の死後、慶長5年(1600)関ヶ原合戦に勝利した徳川家康は国内を制覇し、家康の次男、結城秀康を越前国68万石の領主にしました。
越前北庄城主になった秀康ですが、7年後の慶長12年(1607)34歳の若さで急死したため、秀康の嫡男忠直が弱冠13歳の若さで後を継ぐことになりました。
しかし、藩の実権は秀康時代の重臣が握っており、当時、筆頭家老(秀康の付家老)本多伊豆守富正注1と家老(秀康の越前移封時の付人)今村掃部助盛次注2が、その序列を巡って競い合っていました。
今村掃部助は、藩内の主導権を握るために家老の一人、清水丹後守孝正注3らと組み、忠直の生母清涼院の威風を利用するため、
その実兄中川出雲守注4を味方に引き込んで忠直に取り入り、筆頭家老本多伊豆守を凌ぐ実権を手に入れようとしました。
注1:本多伊豆守富正 府中城主、知行高3万9千石、与力知行1万9千石
注2:今村掃部助重次 丸岡城主、知行高2万5千石、与力知行1万5千350石
注3:清水丹後守孝正 敦賀城主、知行高1万1千石、与力知行6千石
注4:中川出雲守 藩主忠直の生母清涼院の実兄、知行高4千石
3 騒動の経緯
この頃、御普請与頭の久世但馬守注5領内の古市村(福井市古市町)の百姓Aは妻Bを置いて佐渡へ出稼ぎに出ていました。
出稼ぎ後3年間は妻へ仕送りをしていましたが、次第に音信不通になり仕送りも途絶えました。
それでも妻は夫の帰りを待っていましたが、生死のほどが分かぬまま7年が過ぎ、
親類の勧めを受け入れ、町奉行の岡部伊予守注6領内の石森村(福井市石盛町)の百姓Cと再婚しました。
さらに、7年ほど過ぎたある日、前夫Aがひょこりと古市村へ帰ってきて、妻Bが留守中に他家へ嫁いでいることを知り、復縁を迫りました。
妻Bは再婚して、すでに子どもでき平穏な生活を送っていましたので、前夫Aの復縁を断りましたが、前夫Aはしつこく復縁を迫りました。
ところが、話がつかない間に前夫Aは何者かにやみ討ちで殺されてしまいました。
犯人は何者か、殺害の動機は何か分からないまま時が過ぎ、そのうち村の中で「殺したのは石森村の現夫Cではないか」という噂話が出始めました。
この噂話を聞いた久世但馬守は、領内の百姓Aが殺されたことに腹を立て、家来木村八右衛門に密かに百姓Cを殺害するよう命じました。
木村八右衛門は夜中に石森村の百姓Cの家を釘付けにして火を放ち、夫婦諸共一家を焼き殺してしまいました。
このことを、木村の馬取りをしていた下男Dが、重臣の一人、牧野主殿助注7に密告したのです。
これを知った町奉行、岡部伊予守は牧野主殿助に密告者を出すよう要求しますが、「そんなことは知らぬ」と拒否されました。
牧野主殿助は、この件を家老の一人、竹嶋周防守注8に相談すると、竹嶋周防守は大事件になってはまずいと考え、秘かに密告者の下男Dに誓約書を書かせて逃がしました。
それを知った久世但馬守は、他の下男Eに命じて下男Dの後を追わせ、文殊山の麓(福井市西部)で追いつくと下男Dを殺し、死体を薪を積み重ねた下に埋めて隠しました。
この事を町奉行、岡部伊予守に訴えた者がおり、死体を掘り出した岡部伊予守は家老今村掃部助に、この件を相談したのです。
こうして事件は藩の上層部へと拡大していきました。これを知った牧野主殿助は責任が我が身に降りかかるのを恐れ、京都へ逃げ、さらに高野山に入って剃髪してしまいました。
注5:久世但馬守 御普請与頭 知行高1万石 与力知行4千石
注6:岡部伊予守自休 町奉行 知行高1700石 与力知行420石
注7:牧野主殿助 知行高3000石
注8:竹嶋周防守 家老 知行高5500石
4 大騒動へと発展
岡部伊予守は重臣今村掃部助、清水丹後守らに相談、久世但馬守は筆頭家老本多伊豆守、竹嶋周防守らと協議するなど、
本件は久世家と岡部家の対立から越前藩の重臣らを巻き込んだ藩を二分する大騒動へと発展していきました。
藩主松平忠直は、弱冠18歳で本件を処理することができず、御側付き重臣の意見に任せました。
筆頭家老本多伊豆守は、久世、岡部両者の仲裁に入り、何とか和解させようと岡部をなだめ
「百姓Aを殺したのは誰なのか、証拠が不十分である」などと、本件を穏便に収めようとしました。
しかし、岡部伊予守は、本多伊豆守が久世但馬守に好意を持っていることに不満を抱き、家老今村掃部助らに相談しました。
相談を受けた今村掃部助は、かねてから筆頭家老の本多伊豆守が目障りだったので、この機会に二人を除こう企て、
藩主忠直の実母清涼院の兄、中川出雲守に「本多伊豆守を除けば重臣に推挙してやる」と誘いかけ、
藩主忠直と清涼院には「本多伊豆守は先君秀康の御恩を受けながら殉死もせず、不忠第一の人物である」と讒言するなど、
密かに五騎十騎と侍を北庄へ呼び寄せ、屋敷周りの警戒を厳重にして策謀実行の機会を狙っていました。
そして慶長17年(1612)10月7日、家老の一人竹嶋周防守を城中に押し込め、本多伊豆守に使者を遣わし「久世但馬守を預かれ」と主命を伝えました。
本多伊豆守が「それでは御目付役を一人つけていただきたい」と申し出ますと、前言を翻し、
「それなら預からなくてよい、その代り一人で久世家屋敷へ出向き、訴人の書付を読み聞かせ切腹を命ぜよ」と伝えてきました。
今村掃部助にしてみれば、本多伊豆守が久世但馬守の屋敷へ一人で行けば殺されるに違いない。
殺されたらそれを理由に久世但馬守を殺すことができると読み、一石二鳥の妙案だと考えたのです。
5 本多伊豆守、久世但馬守の屋敷へ
本多伊豆守も、主命とあれば逆らうことができません。運を天に任せて久世屋敷へ一人で出向き、「切腹せよ」との主命を伝えました。
しかし、久世但馬守は「私に悪いところはない。一万石を拝領する重臣の一人として一度も岡部伊予守と対決させることなく、
一方的に罪人扱いで切腹せよとは承服できぬ。主命に背き討ち取るというなら一戦交えてもよい。」と拒絶しました。
本多伊豆守は、なおも諄々と説得しましたが、久世但馬守の意思は変わりませんでした。
彼も前藩主結城秀康の寵愛を受けた武士であり、かつては関白秀次秘蔵の家来(一説には佐々成政の家来)です。
その久世但馬守が浪人中に本多伊豆守が藩主結城秀康に推挙し、一万石で召抱えさせた経緯がありました。
世間では越前藩が久世但馬守を召抱えたとき「これで越前藩も後顧の憂いなく安泰だ」と評されたほどの人物です。
しかし、一方で譜代家臣の中には外様武士が一万石も与えられたことを快く思わない者もいました。
そんな人物でしたから秀康に使いこなせても、若輩の忠直に使いきれるはずがありません。
本多伊豆守は久世但馬守に「主命に背けば私が討手の大将になるがよいか。」と念を押すと
「やむを得ない。このまま切腹では武士の一分が立たない。」と主張しました。
久世屋敷には武装した家来たちが控え、本多伊豆守をその場で殺そうと機を窺っていましたが、
久世但馬守は家来たちを制し、「本多伊豆守の他に私の言い分を聞いてくれる人がいるか。」と叱り、家来たちを宥め、無事、屋敷から退出させました。
今村掃部助らの策謀は失敗しましたが、使者を遣わし「早々に久世但馬守を討ち取れ」という主命を本多伊豆守に伝えてきました。
6 本多伊豆守、久世但馬守と戦い討ち取る
主命を受けた本多伊豆守は、やむなく兵を引き連れ久世但馬守の屋敷を攻めました。この様子を今村掃部助父子は、天守閣から見物していました。
そのうえ、今村掃部助は、同派の重臣多賀谷左近注1を本多伊豆守軍勢の後備えに配して、
本多伊豆守が攻撃命令を下すと、その後方から兵に鉄砲を撃ちかけさせるという無謀な策を命じていました。
このため本多伊豆守の軍勢は久世但馬守の軍勢より、味方側軍勢の無謀な戦術に危険な目に遭わされました。
これを見た本多伊豆守の家臣磯野城之助は、多賀谷左近の軍勢に駆け寄り「その場所から鉄砲を撃ってはならぬ」と制止し、久世但馬の軍勢が守備する屋敷に突入しました。
この戦いで久世但馬守父子は屋敷に火を放ち自害しました。本多伊豆守も鉄砲で高股を撃たれましたが、鎧に当たり事なきを得ました。
しかし、この戦によって本多側は討死にした家臣13名に多数の負傷者を出しました。
一方、久世側は一族はじめ150人全員が討死しましたが、本多伊豆守は家来に「首を刎ねるな」と命じ、一人の首も取りませんでした。
注1:多賀谷左近 知行高3万2千石
7 江戸幕府の裁許
この騒動は江戸幕府の知るところとなり、慶長17年(1612)11月、本多伊豆守富正と今村掃部助重次両名は
江戸城西の丸に召しだされ、両御所(家康と将軍秀忠)直々の裁許が行われました。
席上、今村掃部助は弁舌さわやかに申し立て、本多伊豆守の及ぶところではありません。
このままでは本多伊豆守が不利と見た老中本多佐渡守正信が「もう他に申すべきことはないか」と本多伊豆守に尋ねると巾着から書付を取り出し差し出しました。
それには次のように書かれてありました。
1 私の所在地府中(越前市)は往来頻繁なところであり、秀康様から3千石の賄料を賜っています。
しかるに丸岡(坂井市丸岡町)は辺地で賄料が不要にもかかわらず、今村掃部助は幼君(藩主忠直)を騙して賄料3千石を取っています。
2 久世但馬守成敗のとき、多賀谷左近を私の後尾に付け。後ろから鉄砲を撃たせ、今村掃部助父子は天守で見物していました。
3 私は越前で高禄を拝領し、一老とされていますが、今村掃部助は私を軽んじ主人を欺き悪口を言っています。
この書付をご覧になった家康は、今村掃部助に向かって「不忠の曲者なり、早々に追い立てよ。」と大いに怒りました。
こうして本件の主な関係人処分が次表のように行われました。
| 人 名 |
知行高 |
処 分 |
| 今村重次 |
25,050石 |
磐城鳥居家預け |
| 清水孝正 |
11,020石 |
仙台伊達家預け |
| 林 定正 |
9,840石 |
山形最上家預け |
| 岡部自休 |
1,720石 |
死 罪 |
| 中川出雲 |
4,000石 |
信濃配流 |
| 広沢兵庫 |
2,800石 |
配流(場所不明) |
| 落合主膳 |
10,000石 |
紀伊配流 |
| 谷伯耆守 |
3,000石 |
改 易 |
参考1:中川出雲以下は慶長18年の処分
参考2:由木西安(2,000石)・上田隼人(600石)が久世但馬に与して自殺
参考3:知行高は「秀康給帳」による
参考4:「家譜」「譜牒余録」「寛政重修諸家譜」など諸書により諸説がある
本多伊豆守富正は、「忠義正法なり、幼少の忠直を今後とも補佐せよ」とのお言葉を賜りました。
8 越前藩の重臣1名増加
慶長18年(1613)本多伊豆守は江戸へ上り、「越前藩は大国であり、政務が多いので同職一人を賜りたい」と幕府に願い出ました。
すると「適任者を推挙せよ」といわれましたので、従兄の本多成重注1を推挙しました。
幕府は直ちに本多丹下成重を召し出し、「急いで越前へ行き、本多伊豆守と心を合わせて国を治めよ」
と申し渡し、本地3,000石に3万7千石を加増し4万石を賜り、丸岡城主にしました。
二人は同道して越前へ向かい、その後、本多伊豆守に男子がいなかったため、本多丹下の子大膳を養子に迎え、名前を志摩と改めました。
注1:本多丹下成重 幼名仙千代、後の飛騨守
9 騒動の真相と戦国の遺風
この騒動の真相は、藩内の重臣本多伊豆守と今村掃部助の主導権争いが最大の原因と考えられます。
当時、家臣間の騒動に武力が使われたことは戦国の遺風が色濃く残っていたことが窺われ、一つ間違えば越前藩改易もあり得る深刻な事件だったといえます。
弱冠18歳の藩主忠直には重臣同士の争いを処理する力はなく、幕府の裁許に委ねられました。
この騒動で今村一派は一掃され、本多伊豆守は「国中仕置」を申し付けられて、名実ともに筆頭家老になりました。
ただ、徳川親藩である越前藩で起こった騒動でしたから幕府が積極的に関わり、迅速な処分を下し、幕府の威光を内外に示して幕藩体制の基盤強化につなげた事件でもありました。
10 終わりに
久世騒動を振り返ってみますと、当時、家臣の知行地で発生した百姓の殺人事件から推測できるのは、給人知行権が強かったことです。
この頃、領主にとって最大の課題は、百姓を土地に居つかせ耕作に専念させることでしたが、
いまだ確実に浸透していなかったようで、知行地の百姓が他国へ出稼ぎに出ていることでも窺えます。
400年前の百姓の出稼ぎ、殺人事件が起きた古市村、石森村(石盛村)は福井市森田地区にあり、
近年まで森田地区も農村風景が色濃く残っていましたが、土地区画整理事業が推し進められ大きく変貌しました。
それに残念なことは、昔も今も同じような権力闘争や内部告発が尽きることなく続いていることです。
人間の我欲がもたらすものとはいえ、平穏で安楽な世界は人間社会が続く限り、永遠の課題なのでしょうか。
|
主な参考文献
南条郡史 南越前町
武生市史 越前市
福井県史通史編3近世一 福井県
福井県の歴史 山川出版社 |

|