

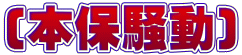

1 「一揆」と「騒動」
江戸時代は幕藩体制の下、戦のない平穏な日々が続きますが、一方で百姓は厳しい支配を受け、過重な年貢、諸役の負担に苦しみました。
そのため、しばしば年貢の減免、諸負担の軽減等を求め各種訴願を展開し、時に支配秩序の枠組みを越え強訴したり、集団的な実力行使に及びました。
これが百姓一揆で、全国で3,000件を越え、越前・若狭でも62件ほど発生したといいます。注1
ただ、この時代の支配層は集団的な社会行動を、多くの場合「騒動」と表現し、「一揆」と使い分けています。
それは武器を持ち戦闘につながる争いを「一揆」と呼び、集団的な社会行動を「騒動」と表現しているからです。
幕府は「一揆」を反乱として厳しく弾圧し、百姓・町人が戦闘用の武器を所持することを禁止しました。
この結果、武士であれ、百姓・町人であれ、一般に反社会的、反権力的な集団行動を「徒党」と表現し、幕府・諸大名等はこれを厳しく取締り、弾圧しようとしました。
注1:百姓一揆発生62件は1641年から1880年までの件数、出典:福井県史通史編4近世ニ
2 蓑虫騒動の発生
越前では百姓一揆のことを「蓑虫」と呼び、本保騒動の頃から使い出したようです。百姓が雨具、防寒具として「蓑」で身を包み、一揆に参加したので、それが呼称として定着しました。
その代表的な蓑虫が宝暦6年(1756)1月22日夜、幕府領内で起きた本保騒動です。蓑虫800人ほどが、胴蓑を着し、鉢巻き、頬被りで、斧、鉈、鎌などを持って、頭百姓宅4軒を打毀したのです。
これまで見られなかった大規模な一揆でしたから、越前各地に与えた影響は大きかったようです。そこで本保騒動の経緯をみていこうと思います。
3 騒動の経過
(1)第1回一揆(蓑虫)の発生
宝暦5年(1755)この年、越前は天候不順のため水害、虫損被害によって大凶作に見舞われました。福井藩は藩領高の約半分が損害を受けたと幕府に届け出ています。
騒動が起きたのは翌年の1月22日のことでした。越前本保陣屋注2支配下のうち、丹生郡、今立郡の百姓が昼から夜にかけ、府中河原(日野川)に勢ぞろいしました。
その数、400人とも800人ともいわれ、丹生郡本保村注3、池上村注4、二丁掛村注5、片屋村注6の頭百姓宅4軒に押し寄せ、打毀しを行ったのです。
翌日は本保陣屋へ迫るという噂が立ち、慌てた代官所は福井藩府中本多氏注7や鯖江藩に応援を求めました。
注2:越前本保陣屋:越前市本保町
越前国の幕府領を統括した役所。享保6年(1721)から明治3年(1870)まで約150年間、丹生郡本保村(現越前市本保町)に置かれた。支配地は丹生・南条・今立・大野郡内約180ヵ村、約6万石を領した。
注3:本保村:越前市本保町
日野川中流左岸、愛宕山の東麓に位置。丹生郡のうち、幕府領、村高721石余、家数58 人数267
注4:池上村:越前市池ノ上町
武生盆地の南西部に位置。南条郡のうち、貞享3年(1686)幕府領、明和元年(1764)三河西尾藩領。村高1196石余、家数53、人口308
注5:二丁掛村:鯖江市二丁掛町
日野川中流左岸に位置。丹生郡のうち、貞享3年(1686)幕府領、元禄10年(1697)高森藩領、幕府領、宝暦8年(1758)美濃郡上藩領、村高1372石余、戸数38、人口178
注6:片屋村:越前市片屋町
日野川中流左岸、鬼ヶ岳東麓の愛宕山西麓に位置。丹生郡のうち、貞享3年(1686)幕府領、元禄10年(1697)高森藩領、宝永6年(1709)幕府領、明和元年(1764)三河西尾藩領、村高1143石余、戸数135、人口761
注7:府中本多氏:越前市
慶長5年(1600)結城秀康が越前国68万石を支配し北庄(福井)に城を築いたとき、筆頭家老本多富正を府中領主4万5000石に任じた。以後府中本多氏として明治維新まで続いた。
(2)第2回一揆(蓑虫)の発生
幸い翌日は何も起こりませんでしたが、4日後の1月26日、今立郡上真柄村注8庄屋宅を数百人で襲うという情報が入り、
代官所は再び「騒動を鎮圧し、数人でも召捕って欲しい」と書状で福井藩へ要請しました。
要請を受けた福井藩では、目付熊谷小兵衛以下総勢400人を編成し、1月26日未明福井城下を出発させました。
同日昼過ぎ、福井藩領の今立郡北小山村注9に到着し、同村の組頭注10宅に本陣を置きました。
まもなく、本陣に「味真野河原に百姓が集まっている」との情報が入り、次いで「上真柄村庄屋七郎右衛門宅へ押し寄せ打毀しをしている」との報告が入りました。
福井藩兵が直ちに現場へ駆けつけると打毀しの最中で、庄屋宅へは事前通告してあったのか家人は逃げ出した後で、
家具や戸障子、縁板類まで片付けた後を一揆勢約300人が「斧、まさかり、懸矢、鎌、鉈、鳶口」等を持って打毀し、四方の壁の大部分、柱も残らず傷つけました。
注8:上真柄村:越前市上真柄町
浅水川(文室川)上流域、味真野扇状地扇端に位置。今立郡、貞享3年(1686)幕府領、万延元年(1860)鯖江藩領、文久2年(1862)幕府領福井藩預所、村高1000石余、戸数64、人口312
注9:北小山村:越前市北小山町
鞍谷川上流域、味真野扇状地の扇端に位置。今立郡、福井藩領、村高500石余、家数38、人口166
注10:組頭
庄屋を補佐した村役人、長百姓ともいう。江戸時代、百姓代とともに庄屋を補佐して村の事務を取り扱った役。
(3)福井藩兵と一揆勢の対峙
味真野河原(文室川)に移って福井藩兵と一揆(蓑虫)側が対峙し、一揆側から3人の代表者が出てきました。3人は今立郡宮谷村注11、西尾村注12、萱谷村注13の百姓でした。
福井藩目付熊谷小兵衛が質問すると、次のような決起理由を述べました。「近年、定免注14で重い負担に耐えていますが、昨年は100年来の不作でした。
せめて3分の免引き注15を願うため、頭百姓に江戸への訴願を依頼し、苦しい中から高10石に銀1匁5分ずつの割合で与内銀注16を負担し合い送り出しました。
ところが、彼らは訴願どころか、逆に1000石分の「増免」を引き受け、その上、廻米舟の上乗庄屋に任ぜられるという『良きご褒美』を貰って帰ってきたのです。
その他囲籾の払い下げの件でも不満があり、同じ百姓でありながら裏切られたという思いが募り、この上は餓死覚悟で一同決意し制裁のため立ち上がりました。」
熊谷は彼らの話に理解を示しつつ、しかし、これ以上騒動を続ければ、実力行動に出なければならない。
また、お前達の処罰も重くなる。本保代官所へよく伝えておくから、この場は鎮まり解散するよう説得しました。
これに一揆(蓑虫)側も納得し引き上げました。その後、流言はありましたが、再び騒動は起こりませんでした。
注11:宮谷村:越前市宮谷町
浅水川(文室川)上流域、味真野扇状地の西端に位置。今立郡、貞享3年(1686)幕府領、村高1026石、戸数91、人口474
注12:西尾村:越前市西尾町
日野山の北東麓、浅水川(文室川)上流域に位置。今立郡、貞享3年(1686)幕府領、宝暦9年(1759)501石が旗本金森氏(白崎領)、村高1028石余、戸数88、人口481
注13:萱谷村:越前市萱谷町
日野山東麓、浅水川(文室川)上流域の山間部に位置。今立郡、貞享3年(1686)幕府領、宝暦9年(1759)旗本金森氏(白崎領)、村高225石余、戸数32、人口179
注14:定免(じょうめん)
江戸時代の徴税法の一つ。免は年貢の賦課率のこと。過去5年、10年、20年間などの田租額を平均して租額を定め、一定の期間内は、その年の豊凶に関係なく定額を徴収
注15:免引き:年貢の賦課率を下げること
注16:与内銀(よないぎん):農民負担の一種、村々で負担した金。
4藩兵の出兵と本保代官所の処分
徳川幕府は享保19年(1734)8月、全国の代官に幕府代官所の支配地で一揆が発生して、
急を要するときは幕府に伺いを立てずに隣接の大名に援兵を頼むよう指示し、各大名にもこの事を伝えてありました。
1月26日、本保代官所から要請を受け出兵した藩兵は次の通り福井藩兵400人、福井藩本多氏兵100余人、鯖江藩兵221人、大野藩兵124人は出兵体制を整えました。
しかし、本多氏兵、鯖江藩兵は、当日、本保代官所陣屋を警護したため、直接一揆側と接触したのは上真柄村へ向かった福井藩兵でした。
この頃、全国的に百姓一揆が多発していたため、領主側は平素から鎮圧体制を整えていたようです。
また、福井藩は出動前に藩の方針として百姓を捕縛しない、騒動の鎮圧だけに努めると決めてあったので、一人も捕縛せず引き上げました。
本保代官所では、騒動が鎮まった後、急きょ江戸から代官 内藤十右衛門忠尚が到着し、騒動後の指揮をとりました。
代官所では騒動の参加者とその頭取の確認と吟味に努め、8月、この騒動に対する処罰を断行しました。
処罰は幕府が寛保元年(1741)に定めた規定を適用した厳しい内容で、獄門注171人、死罪注182人、遠島注192人、追放注2017人、所払注214人の 計15ヵ村26人に及びました。
加えて獄門、死罪、遠島者には田畑家財闕所注22追放者には江戸十里四方追放の場合は、越前での田畑家屋敷闕所か財産没収、所払の者は田畑だけ取上げとなりました。
これ以外にも庄屋51人に銭5貫文ずつ、長百姓58人に計70貫文、余田村注23には別に25貫文を科し、
外に余田(はぐり)村、上石田村注24で10貫文ずつ2人、上野田村注25、下野田村注26、小泉村注27、下氏家村注28の長百姓6人に7貫文の過料注35が科せられました。
過料となった百姓たちは全員、村役人を解かれました。この騒動の関係村数は丹生郡25ヵ村、今立郡20ヵ村の計45ヵ村に及びました。
余田村庄屋の処罰理由を示す「獄門札」に「頭百姓共を疑って禁制の徒党頭取となり、上野田村、下野田村、気比庄村注29の者と申し合わせ、家財破却を実行させ不届至極」と記してありました。
なお、宝暦9年(1759)6月「本保騒動百姓仕置書付」には西尾村注30、萱谷村注31、大手村注32について百姓共は「急度叱」注33、水呑百姓共は「御叱」になったと代官手代が記しています。
8月25日、本保村で獄門、死罪の処刑が行われました。遠島者は直ちに江戸送りとなりましたが、その一人、小泉村庄屋のために親戚の者が後を追って金子などの「貢物」を江戸へ持参しています。
これ以後、関係した村人は重い処分に長く苦しみ、後々までこの騒動を語り伝えたといいます。
本保代官所は処分結果を記録にとどめ、宝暦9年(1759)幕府領の一部が旗本金森左京家領注34になったとき、同家へ前述の「仕置書付」を申し送りました。
代官所の指示があったのか、宝暦10年(1760)「下野田村差出明細帳」には処分者名が明記されています。
こうして本保騒動は鎮まりましたが、この騒動は頭百姓の制裁に重点が置かれたために、一揆側の成果は何もありませんでした。
年貢は宝暦7年(1757)夏、前年に続く大きな水害が発生したため、全体的に軽減されましたが、翌年の宝暦8年(1758)から、また元に戻っています。
注17:獄門:刎ねた首を獄門に架け三日二晩晒した。情状により引廻しの付加刑を科した。
注18:死罪:首を刎ね死骸取捨て。情状で引廻し付加刑を科し、かつ田畑・家屋敷・家財の闕所。
注19:遠島:江戸より大島・八丈島などへ、京・大阪より薩摩・五島の島々などへ流罪。必要的付加刑として田畑・家屋敷・家財共に闕所の厳刑であった。
注20:追放:延享2年(1745)から町人・百姓に対し重・中・軽追放とも江戸十里四方・住居国、犯罪国を立入禁止地域とし、田畑・家屋敷を闕所とした。
注21:所払:追放刑の一種。享保6年(1721)5月から在方の者は居村、江戸町人は居住町に住むことを禁じた。
注22:田畑家財闕所:正刑の付加刑として田畑・家財などを取り上げた。
注23:余田村:越前市余田町(はぐりちょう)
日野川中流左岸、三床山南東麓に位置。丹生郡、貞享3年(1686)幕府領、宝暦8年(1758)村高1374石余のうち471石余が美濃郡上藩領となる。人数413、宝暦9年郡上藩領の家数34、人数158、分郷のため幕府領・郡上藩領に庄屋以下三役が置かれた。
注24:上石田村:鯖江市石田上町
日野川中流左岸に位置。丹生郡、正保2年(1645)吉江藩領、延宝2年(1674)福井藩領、貞享3年(1686)幕府領、明和元年(1764)三河西尾藩領、のち幕府領、村高1010石余、日野川沿いに越前海岸に至る浜街道の渡し場あり渡し船を共有、家数98、人口387
注25:上野田村:鯖江市上野田町
三床山の東南、日野川左岸の平野部に位置。丹生郡、貞享3年(1686)幕府領、元禄10年(1697)高森藩領のち幕府領、明和元年(1764)三河西尾藩領、村高373石余、戸数25、人口139
注26:下野田村:鯖江市下野田町
三床山の東南、日野川左岸の平野部に位置。丹生郡、貞享3年(1686)幕府領、元禄10年(1697)高森藩領、宝永2年(1705)松平(本庄)宗長領、正徳2年(1712)幕府領、明和元年(1764)三河西尾藩領、村高1084石余、家数70
注27:小泉村:鯖江市小泉町
日野川中流左岸に位置、丹生郡、福井藩領、正保2年(1645)吉江藩領、延宝2年(1674)福井藩領、貞享3年(1686)幕府領、元禄10年(1697)高森藩領、宝永2年(1705)松平(本庄)宗長領、
正徳2年(1712)幕府領、明和元年(1764)三河西尾藩領、村高193石余、万延元年(1860)の家数80外に僧1、医師1、大工1、鍛冶1、小売店15、絹織商売5
注28:下氏家村:鯖江市下氏家町(しもうずえ)
丹生山地東端、三床山の東、日野川左岸の平野部に位置。丹生郡、貞享3年(1686)幕府領、元禄10年(1697)高森藩領、その後幕府領、明和元年(1764)三河西尾藩領、村高690石余、天保9年(1838)家数66、人数270
注29:気比庄村:丹生郡越前町気比庄
天王川と和田川に挟まれた所に位置。丹生郡、貞享3年(1686)幕府領、元禄10年(1697)高森藩領、正徳2年(1712)幕府領、村高1503石余、正徳2年人数333、馬11
注30:西尾村:越前市西尾町
日野山の北東麓、浅水川(文室川)上流域に位置。今立郡、貞享3年(1686)幕府領、宝暦9年(1759)一部旗本金森氏(白崎領501石余)、村高1028石余、戸数88、
注31:萱谷村:前述注13参照のこと
注32:大手村:越前市大手町(おおで)
日野山の北麓に位置。今立郡、貞享3年(1686)幕府領、宝暦9年(1759)旗本金森氏領、村高221石余、元文3年(1738)の戸数13、人口61
注33:急度叱
御仕置のうちで最も軽い刑。奉行が囚人を御白州に呼び出し、その罪につき叱責し、宣告後、与力が請書を取り、差添人が連署し拇印をした。そのやや重いのを急度叱といった。
注34:旗本金森左京家領
宝暦8年(1758)旗本金森可英(よしひで)に越前国内で7000石が与えられた。これが金森氏領で南条郡白崎村に陣屋が置かれた。金森左京家といわれ白崎領と呼ばれた。
注35:過料
江戸時代、本刑に代えて科した金銭罰。
江戸時代の通貨は金・銀・銭貨の三種類、相場制であった。勘定は十進法ではなく、複雑であった。概ね金一両は四分、一分は四朱、銀六十匁が金一両に相当、銭千文が一貫文で、一分に相当した。
三貫文は銭三貫文のこと、文化6年(1809)の相場で金一両は銭六貫四百文であった。村高過料はその収穫率を定め、各反別に乗じて反高を計算し、
その石高を一村の総石高に応じて徴収した。実際は高100石につき銭ニ貫文の割合で徴収したという。
5 一揆の参加者と打毀し対象
(1)一揆参加者
1月22日参加した一揆勢の数は明らかでありませんが、1月26日味真野河原で福井藩兵と対峙した時には約800名いたようです。
しかし、この時の参加者は丹生郡内の百姓は一人もおらず、「宮谷、大手、水間之谷注36、萱谷、服部谷注37」など今立郡26ヵ村の百姓だけでした。
これらの百姓はどのような計画で参加したのでしょうか。当初計画では高100石に3人の割合で参加することになっていましたが、一揆実行の段階で「家毎に1人宛て」の参加になったといいます。
参加各村の庄屋・長百姓などが多数参加し、庄屋層を中心に「小百姓」の高持百姓などが参加した一揆でした。
注36:水間之谷(みずまのたに)
今立郡内、水間川流域に形成された小谷を水間谷と呼び、その流域に10ヵ村あった。
注37:服部谷(はとりたに)
今立郡内、権現山の北を西流する服部(はとり)川流域に形成された谷を服部谷といい、その流域に12ヵ村あった。
(2)打毀し対象者
訴願のため江戸へ赴いたのは池上村、上真柄村、二丁掛村、坪谷村注38の4人の百姓でしたが、これ以外の家も打毀しの対象にされました。
彼らは、いずれも一揆側からみれば頭百姓と呼ばれていた者やかつて郡中惣代注39を務めたような大庄屋でした。打毀し対象は次の村々の家です。
○ 本保村 丈左衛門
○ 池上村 又兵衛
○ 片屋村 与次兵衛
○ 二丁掛村 加兵衛
○ 上真柄村 七郎右衛門
○ 宮谷村 新兵衛
○ 坂下村注40十兵衛
注38:坪谷村:福井市坪谷町
丹生山地東端に当たる乙坂山の北麓、谷あいに位置。丹生郡、貞享3年(1686)幕府領、明和元年(1764)三河西尾藩領、天保2年(1831)一部が幕府領、村高627石(西尾藩566石)
注39:郡中惣代
代官所の行財政の補完的役割を担う者として江戸後期から置かれた。宝暦・天明期以降存在した村役人の代表。代官所支配管下(郡中)の庄屋を代表する(惣代)の意味で郡中惣代庄屋と呼ばれた。
注40:坂下村:越前市南坂下
今立郡内の月尾川最上流域、月尾谷の最奥部に位置。今立郡、貞享3年(1686)幕府領、元禄5年(1692)大阪城城代土岐頼殷領、
正徳2年(1712)幕府領、享保5年(1720)鯖江藩領、村高81石余、享保6年(1721の)家数28、人数111、明治14年(1881)南坂下村に改称
6一揆の準備と論理
この一揆は早くから組織的、計画的に実行されました。宝暦6年(1756)1月16日、糺野(川濯堂の森か)で集会を開き、同月18日には同所で傘連判状注41を作成しています。
一揆実行時の主な約束事は次の通り
○もし事前に露見した場合は府中の米問屋に向かうと答えること。
○怪しまれないよう鯖江町で草履を購入しておくこと。
○大寺へ食事を頼む手配を調えておくこと。
○打毀しの前に代表8人が事前通告し近村へも同じく触れておくこと。
○火の用心、家財道具を持ち出し焼いた場合は窃盗の嫌疑がかからないよう
一部を残すこと。
○農具以外には剃刀のような武器をもたないこと。
等々を確認しました。
また、後の罰を恐れて「北在は南在辺りへ、東之者は西へ」と入り交わり、青、黄、赤、白、黒や各氏神等を合言葉とすることも定めていました。
彼ら惣百姓の願いは第1 年貢軽減にありました。
それが逆に増加となり、苦しい中から出しあった与内銀が全く無駄に終わったことです。その上、江戸へ赴いた4人の頭百姓が納庄屋注42に命じられたことへの反感が輪をかけました。
第2 囲籾注43の払下げも困窮した百姓にとって切実な願いでした。
第3 頭百姓の裏切り行為が許せませんでした。
彼らは「自然の道」を外したから、制裁するのは道理であると主張しました。つまり、蓑虫は頭百姓共が「天然自然之道理」を踏み外したから、
逆に小百姓共が、その道理に従って現れたもので、「蛆虫が涌き候道理」と百姓らしい表現で強調しています。
つまり、頭取はおらず、一人一人が「誠に風に木葉の誘うが如く、湧く蛆虫のように罷り出候」と答えています。
頭百姓が人々の期待を裏切り、しかも「金子貯家財心之侭」であるのに対して、我々は「餓死之躰」であり、同じ身分の百姓として許せないという論理です。
したがって制裁行動は十分に正当性があると主張しました。加えて第4本保代官所の下代注44が4人の百姓と結託していると指摘しています。
ただ、役人に特別不満はないと言い、領主の支配に敵対するものではないと断っていることです。
幕藩制支配の枠の中での百姓間の問題としているところが、この騒動の特徴ですが、これは他の百姓一揆にも共通しています。
注41:傘連判状
一揆参加者が意思確認を目指し連判状を作成したが、その一種に傘連判状があった。署名人の名が放射状に円く書かれ、形が傘に似ていて署名人の序列が分からないよう作成したもの。
注42:納庄屋
廻米舟の上乗庄屋で代官所から給銀が与えられることから希望者が多く、百姓間の関心が高い役であった。
注43: 囲籾
囲い米に同じ。江戸期、幕府、諸藩、郷村で備荒貯蓄・米価調節・軍事用などに米を蓄えたこと、また、その米のこと。
注44:下代
江戸初期の代官頭の下に置かれた手代の別称。江戸中期以降に郡代、代官などの下役として農政を担当した下級役人。
7騒動の余波
この蓑虫騒動の熱がまだ冷めやらない頃、越前国内の村々で起きた騒動らしい動きは次のようなものがありました。
(1) 宝暦6年(1756)2月1日
福井藩領丹生郡山干飯13ヵ村注45の百姓が府中の米会所を襲うという話が伝わりました。
福井藩本多氏の家臣は直ちに手分けし警戒に当たるとともに福井藩へ応援を求めました。
寺々の鐘を突いて合図をするというので、寺の鐘突きが禁止されました。この話の発端は大阪商人で府中に店を開いた米問屋の評判が悪く、米の値段騰貴は彼の仕業だと憎まれたことからのようです。
前年秋にも家に「火札」が2,3度貼られたといいます。しかし、これは噂話で終わり、騒ぎは起きませんでした。
(2)宝暦6年(1756)2月19日
三国町 尾張屋五郎兵衛、室屋惣右衛門及び丸岡藩領梶浦注46の又兵衛の3軒を潰すという風聞が広がり、
2月20日、22日、25日、30日のいずれかの日に幕府領の百姓たちが押し寄せるというものでした。
三国へは福井藩金津奉行が鉄砲を用意し兵を率いて到着しました。その頃、町内では戦が始まったような混乱だったといいます。しかし、ここでも実際は何も起きなかったようです。
このように本保騒動は越前において、かつて見られなかった大規模な一揆だったことから、これが越前各地の村々に与えた影響は大きかったといわれます。
注45:山干飯13ヵ村:やまかれい現越前市・越前町宮崎
慶長国絵図には「山干飯上之郷」「山干飯下之郷」7514石余と見え、前者には現越前市域の北寄り、中山、勾当原、小野、勝蓮花、丸岡、糠口、仏原、堀、菖蒲谷、土山、宇戸、菅の12ヵ村が、
後者には越前市北西部の曾原、安養寺、粟野、小杉、牧、若須、中野、荻原、黒川、杉本、千合谷、二階堂の12ヵ村と旧宮崎村西部一帯の小曾原、古谷、熊谷の3ヵ村が含まれていた。
注46:丸岡藩領梶浦
坂井郡陣ヶ岡台地北端に位置、北は日本海に面する。梶浦は崎浦、安島浦とともに三ヶ浦と呼ばれ、鎌倉期から見える浦名である。
慶長3年(1598)の石高491石余、年貢率、免四ツとある。はじめ福井藩領、寛永元年(1624)丸岡藩領、石高441石余、家数55、人数311、明治22年雄島村の大字となる。
|
主な参考文献
福井県の歴史 印牧邦雄著
福井県の歴史 隼田嘉彦他3名著
江戸時代の罪と罰御仕置 藤井嘉雄著
福井県史通史編4近世ニ 福井県
日本地名大辞典18福井県 角川書店 |

|